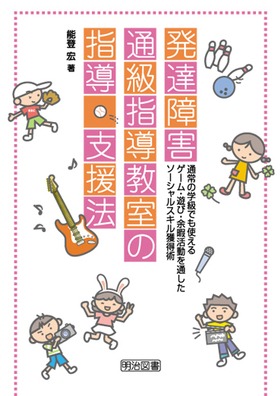- 推薦文
- まえがき
- 第1章 発達障害通級指導教室とは?
- 1 通級指導教室とは
- 2 当教室の概要
- 3 当教室の運営方針
- (1) 三者(保護者,在籍校学級担任,当教室担当者)の連携を大切に
- (2) 児童生徒の実態を考慮した柔軟な指導の形
- (3) ティーム・ティーチング
- 4 当教室の指導の目標
- 5 指導の目標の設定条件と評価方法
- (1) 指導の目標の設定条件
- (2) 指導の目標の評価方法
- 6 当教室の指導の内容
- (1) ソーシャルスキルトレーニング
- (2) 当教室の指導領域とスキル
- 7 興味・関心,家事や余暇の領域について
- (1) 興味・関心を基にした活動
- (2) 家事や余暇のレパートリー
- 8 1単位時間の活動
- 第2章 ソーシャルスキルが楽しく身につくゲームや遊びの実践事例
- 1 低学年グループの事例
- (1) 低学年の指導の基本的な考え方
- (2) ゲームや遊びの紹介
- (3) 指導のヒント
- 2 中学年グループの事例
- (1) 逆行性(背向型)チェイニングによる支援の紹介
- (2) 「仲間の入り方」のロールプレイング
- (3) ゲームや遊び,ロールプレイングなどの紹介
- 3 高学年グループの事例
- (1) ゲームや遊び,ロールプレイングなどの紹介
- (2) 会話の仕方
- 4 中学生グループの事例
- (1) 「どの会話が楽しい?」
- (2) 三角ベース,ボウリング,ビリヤード,そしてマージャン
- (3) 意欲がなければできない
- (4) 行くことになっていた陶芸活動
- (5) フラワーアレンジメント,海,買い物,ハーブルームと広がっていった活動
- (6) たどりついた調理活動
- 5 いくつかのグループに実施した活動の実践例 「仮装写真サービス屋台」
- (1) きっかけは
- (2) 小学校高学年の例
- (3) 中学生女子グループの例
- 6 お楽しみ会の事例
- (1) 初めてのお楽しみ会
- (2) お楽しみ会に向けたSST
- (3) だんだんと慣れてきて
- (4) 少しずつ工夫しながら
- (5) ついに「お祭り屋台村」出現
- 第3章 生活単元的な学習活動の実践例
- 興味・関心を基に学習活動を設定し保護者,関係者・機関と連携した授業
- ~小学校高学年グループ「テレビ番組を制作しよう」の実践から~
- 1 授業づくりの構想
- (1) 学習活動の設定にかかわる児童の実態
- (2) 年間の指導の構想
- (3) 「テレビ番組を制作しよう①」の構想(全7時間:1単位時間は60分)
- 2 Aさんの実態と目標・評価
- (1) Aさんの実態
- (2) 三者共通の願いと長期目標・1学期の短期目標の設定
- (3) 評価について
- 3 授業の実際
- (1) 活動の様子
- 第4章 通級教師の独り言
- 1 子どもたちとの会話
- (1) 彼らの世界に入り込む
- (2) てれるなー
- (3) マシンガントーク
- (4) てゆうか
- (5) 話に加わるきっかけ
- 2 こだわり
- 3 ティームティーチング
- (1) 共通で理解する支援
- (2) STの位置
- (3) 子ども役をするST
- 4 支援の基本的な理念
- (1) 机が突然倒れる
- (2) ときにはグループの友だちの力を生かして
- (3) クールダウン
- (4) プチ「ロールプレイング」
- (5) ほめればいいの?
- 第5章 おすすめの支援グッズ・カード
- (1) 「石の上にはあがりません」カード
- (2) 校外学習の事前指導
- (3) 「いやがることばはつかいません」カード
- (4) 「席を立っていいですか」カードは有効?
- 参考文献
- あとがき
まえがき
「発達障害通級指導教室で何が行われているのか,よく分からない。」
発達障害通級指導教室の担当者である私の疑問です。ましてや,通常の学級担任の先生方にとっては,なおさら何をしているのか分かりにくい教室です。
発達障害通級指導教室担当者同士の横のつながりはありますが,実際に授業を参観し合うことはあまりありません。研究的な授業を広く公開するという機会も,プライバシーにかかわるため,なかなか実現できません。
このような現状を打破し,発達障害通級指導教室での日々の営みを保護者や教育関係者に知っていただきたい,というのが本書執筆の動機です。
本書では,新潟大学教育学部附属特別支援学校に設置された発達障害通級指導教室における3年間の実践を紹介しています。発達障害通級指導教室の実践といえば,まずソーシャルスキルトレーニング(SST)があげられます。本書では,ゲームや遊びを中心としたSSTだけではなく,生活単元的な実践,社会生活学習的な実践なども紹介しています。どのような活動を行っても,SSTに結びつくと考えるからです。児童生徒の興味と関心を基にさまざまな楽しい活動を行います。その中で「成功体験をさせて称賛する」ということを信念にしています。
実践の紹介だけでなく,運営の方針,目標設定と評価,保護者や在籍学校との連携の実際などについても記述してあります。日々の指導にとどまらず,発達障害通級指導教室の運営全般も参考にしていただければと思います。
うまく支援できた実践だけではなく,失敗した実践も紹介しています。また,私が普段考えていることを「通級教師の独り言」として,思いつくままに書いています。通級担当という立場の教師が何を感じているのか,共感していただければ幸いです。
2008年6月 著者
-
 明治図書
明治図書- 通級指導教室の指導の仕方を具体的に学ぶことができました。2020/4/1040代・小学校教員