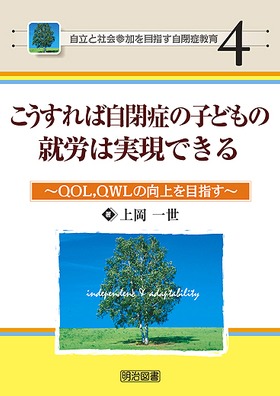- まえがき
- 第1章 自閉症教育の課題と展望
- 1 地域中心の生活
- 2 子ども中心の生活
- 3 自立と社会参加
- 4 地域で支える
- 5 社会生活力の向上
- 6 指導者の意識改革
- 第2章 自閉症教育で重視すべき目標
- 1 彼らの世界を理解する
- 2 学校,家庭,地域で適応する
- 3 我々の世界に近づく
- 4 QOLを高める
- 5 地域社会で自立する
- 6 生活力の向上
- 7 考えることができる
- 8 働くことに喜びを感じる
- 9 感謝の気持ちが持てる
- 10 主体的な生活ができる
- 11 余暇を利用できる
- 第3章 QOLを高める支援・対応の実際
- 1 基本的生活習慣とQOL
- 2 基本的生活習慣の具体的指導法
- 3 基本的生活習慣の確立が生活のベース
- 4 生活リズムの確立が主体的行動を引き出す
- 5 集団参加能力の向上とQOL
- 6 家庭生活力の向上とQOL
- 7 職業生活の向上(技能)とQOL
- 8 職業生活の向上(態度)とQOL
- 9 社会生活力の向上とQOL
- 10 余暇の利用とQOL
- 11 教科学習とQOL
- 12 不適切行動とQOL
- 13 QOLを高めるために必要なこと
- 第4章 QOLを低下させないために必要なこと
- 1 対症療法的対応はやめよう
- 2 行動のパターン化はやめよう
- 3 見通しの意味を理解しよう
- 4 構造化の意味を理解しよう
- 5 保護者の願いに応えよう
- 6 主体的行動を引き出そう
- 7 最大限の適応を目指そう
- 8 短所よりも長所に目を向けよう
- 9 キーパーソンになろう
- 10 可能性を引き出そう
- 第5章 就労を実現するための基本的支援
- 1 支援の基本条件
- 2 指導プログラムの活用
- 3 教師の専門性が最大のポイント
- 4 基本的生活習慣の確立が将来を決める
- 第6章 就労を実現する取り組み
- 1 企業就労と福祉的就労の違い
- 2 就労するために必要なこと
- 3 就労実現のために家庭が重視しなければならないこと
- 4 すべての人の就労を実現する
- 5 就労支援のポイント
- 6 就労支援の基本
- 7 教育の質,連携の質が就労を実現する
- 8 機能する連携を行う
- 9 重度の子どもの就労を実現するためには
- 10 就労実現のために,まず取り組むべきこと
- 11 学校教育12年間で行うべきこと
- あとがき
まえがき
自閉症の人たちの就労の実現は難しいのでしょうか。就労しても職場に適応するのは難しいのでしょうか。決してそうではありません。
私は多くの自閉症の人たちの就労支援にかかわり,彼らの就労実現に努力してきました。なぜ,これほど彼らの就労にこだわるかというと,彼らが,知的能力や障害の程度にかかわらず就労できる人たちであること,彼らは就労することで成長,発達すること,職場や社会で生き生きと活躍している自閉症の人たちがたくさんいること,を確認できているからです。
私がかかわった人の中には,知的に最重度で,表出言語を持たず,また,様々な不適切行動を持っているにもかかわらず就労を実現し,20年近く,職場でなくてはならない存在として働き続けた人がいます。20年間には学校時代には考えられないほどの成長,発達を見せました。ことばにならない声を出し,手振り,身振りで意思表示ができるようになりました。理解言語は保護者も驚くほど向上し,日常生活,職業生活でまったく不自由をしないほどになりました。職場での仕事能力は一般従業員も太刀打ちできないと言われました。これはほんの一例ですが,こうした成功事例を考えると,どうしても,もっと多くの自閉症の人たちに,多くの人にかかわりながら職業生活,社会生活を送って欲しい,そして人生の質を高めて欲しい,と願わざるを得ないのです。
今回,この本をまとめるきっかけになったのは,最近の学校教育,家庭教育を見ていると,教師や保護者の中に,「自閉症の人は就労は無理である」「自閉症の人が就労できるはずがない」と最初からあきらめたり,決めつけたりする人がかなりいると感じたからです。自閉症だからという理由だけで彼らの将来への可能性まで放棄しようとする対応があまりにも多い,と思うのですがどうでしょうか。教師や保護者の勝手な判断で彼らの貴重な人生を決めつける対応に,「教育とは何か」を今一度問い直してみたいと思いました。
とは言え,教師や保護者が意識を切り替え,就労を目指す取り組みを行うことで,就労が実現できるかというと,必ずしもそうではありません。
では,どういう指導,支援をすれば彼らの就労が実現できるのでしょうか。本書では,私の今までの就労支援の実際と現在の自閉症教育の課題を交差させながら,今後の自閉症教育を展望し,一人でも多くの自閉症の人たちの就労を実現するための取り組みのあり方をまとめてみました。
言うまでもなく,自閉症の人は一人ひとり障害の程度,偏りが違います。一人ひとりに合った指導,支援がどれほど適切に行われるかによって就労の実現の可能性はまったく違ってきます。本書では,主に就労を実現するための基本的な取り組み姿勢や考え方を,具体例を挙げながら整理しています。是非,参考にして個々に応じた就労を実現するための適切な指導,支援の方策を見出して欲しいと思います。
本文にも書きましたが,本書を通して,先生方や保護者の方が「自閉症の人は就労できないのではなく,就労できるような指導,支援が行われていないからできないだけである」「彼らは職場で働きたい,地域社会で活動したい,という強い願いを持っている」ということを確認し,彼らを主体にして,早期より就労に向けた取り組みが行われることを願っています。日々の取り組みを通して,彼らの人生の質が向上することが,実は我々,教師や保護者の人生の質を向上させることになることを是非実感して欲しいと思います。
私は,「教育の原点は障害児教育にあり,障害児教育の原点は自閉症教育にある」と考えています。そういう意味では,本書は自閉症の子どもを中心にまとめていますが,知的障害の子どもについても同じ取り組みを行えば十分通用すると思われますので,是非,参考にしていただきたいと思います。
なお,本書はシリーズ「自立と社会参加を目指す自閉症教育」(明治図書刊)の第4作となっています。第1作『自閉症の理解とその支援』,第2作『自閉症の子どもが地域で自立する生活づくり』,第3作『自閉症の子どもが職場で自立する生活づくり』も取り組みの参考にして欲しいと思います。就労を実現するために必要な具体的な指導,支援内容,及び適切な指導,支援の時期については,拙著『指導年齢がわかる自立と社会参加を実現する個別の指導プログラム』(明治図書刊)を合わせてご利用いただければ,一層効果的だと思われます。
2007年6月 /上岡 一世
-
 明治図書
明治図書