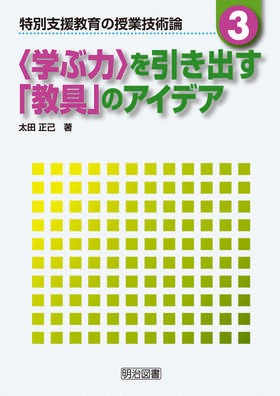- はじめに
- 第1章 教具の創造
- 1 授業と教具
- 2 教具の創造
- 3 教具とは何か
- 4 教具の構造
- 5 教具の創造と工夫の観点
- 6 教具としての教師の手
- 7 教具づくりのために
- 第2章 子どもの力を引き出す教具
- 1 教具の操習性
- 2 自然環境の操習性
- 3 教具が引き出すもの
- 4 引き出された力はどうなるか
- 5 教育課程の開発に向けて
- 6 ○△□のはめ板の現在
- 7 授業と転移
- 第3章 「おおきなかぶ」という教具
- 1 教具「おおきなかぶ」
- 2 「おおきなかぶ」と「おおきなだいこん」
- 3 抜けない「おおきなかぶ」
- 4 あまいあまい「おおきなかぶ」
- 5 「おおきなかぶ」をひっぱるねずみ
- 第4章 教具の背景
- 1 教具の背景
- 2 特別支援学校学習指導要領にみる教具の活用
- 3 生活用具
- 4 教材の現実度
- 5 「具体的」か,「現実度」か
- 6 ロビンソン・クルーソー的
- 7 学習上の特性
- 8 内容の現実度か,方法の現実度か
- 第5章 「具体的・実際的・総合的」論
- 1 「具体的・実際的・総合的」論
- 2 各教科等の内容と生活単元学習
- 3 合わせて指導を行う場合
- 4 「具体的・実際的・総合的」論考究
- 5 学習によって得た知識や技能
- 6 「具体的・実際的・総合的」論再考
- 7 「ごっこ」か,「仮想現実」か
- 8 仮想現実から現実へ―教具のリアリティ―
- おわりに
はじめに
その伝える意味がもっとも明白であるように思える「ことば」でさえ,それが使用される文脈によって,意味するところとは違っている。教材・教具は「ことば」のように直接にはその意味を語っていない。それは,教師がどのような文脈や状況で使用するかによって,使用の仕方によって,その意味は異なってくる。
教材や教具にまつわる話で筆者が思い出すのは,昭和30年代後半,知的障害養護学校用の教科書がはじめて編集されるときの編集委員会でのエピソードである。それは,滑稽な話である。そのエピソードについて触れた文書を読んだとき,筆者は,次のような編集会議の場面を想像した。
編集委員の人たちは,それまで積み上げてきた実践と研究の結果を生かすために,つまり生活教育の中でどのように教科書を取り入れるかということを考えていた。あるときの編集委員会でひとりの委員Aが言った。
A:教科書よりも指導書をさきに出版して,この教科書を使用するまえに知的障害児の「数」はどのように指導すればよいかについて予め十分理解を深めていただいてはどうですか。
B:そうですね。指導書を最初から終わりまで読んでいただくことをかさねてお願いしましょう。
委員全員が教材としての教科書を生活教育の考えを生かすべく使用するためには,養護学校の教師に指導書を熟読してもらうことが重要であると考えていた。そして,Aの意見にBをはじめとしてほとんどの委員が賛成しかけたとき,Cが立ち上がって発言した。
C:教科書が出てないのに指導書があるはずがない。
その一言に,ざわめいていた会場は一瞬静まり,そして皆は我に返ったように大笑いした。
結果的に大笑いをしたとしても,「教科書よりも指導書をさきに」と議論するほど,編修委員の中では教科書の使い方が重要と考えるあまりにこのような議論になったのである。
本書で中心的に取り上げる教具についても同じことが言える。授業の中で教具をどう扱うかである。例えば,教室の真ん中にぽつんと置かれた布でつくられた「おおきななぶ」。教師には,おじいさんが引っ張っても抜けない「おおきなかぶ」である。ある子にとっては何に見えているのであろうか。
教室の真ん中におかれた教具が,子どもたちや教師にどのように見えるのか。それは,教室がどのように演出されているのか。教師がどのようにその教具にかかわるのかによって異なってくる。また,教師の教具の扱い方の違いは,時代背景の違いも反映している。
そこで,教具がどのような状況におかれてきたかを歴史的な背景に探ることも含めて,「〈学ぶ力〉を引き出す『教具』のアイデア」について検討することが必要である。
最後に,これまでと同様に『特別支援教育の授業技術論』をシリーズ化する機会を与えていただいた,教育書編集部の三橋由美子さん,また貴重なアドバイスと丁寧な校正をしてくださった川村千晶さん,まことにありがとうございました。なお,本書でも,共同研究者やスーパーバイザー等の立場で,いろいろな学校の多くの先生方の授業を参観させていただきました。その機会に提供いただいた授業案等を資料とさせていただきました。先生方には,心より感謝申し上げます。
平成22年11月 小春日の光の中で /太田 正己
-
 明治図書
明治図書