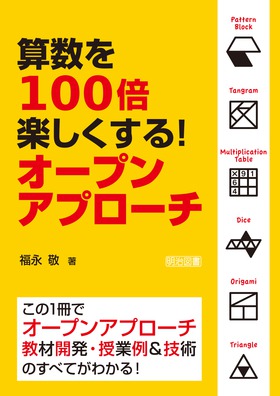- �͂��߂�
- �P�́@�I�[�v���A�v���[�`�Ƃ�
- �P�@�I�[�v���A�v���[�`�Ƃ�
- �Q�@�I�[�v���A�v���[�`�̐�s�����ƕ���
- �R�@�I�[�v���A�v���[�`�@�\���̂悳�ƂR�̎w���@�\
- �S�@�I�[�v���A�v���[�`�łȂ��w���@
- ��������Z���b�@�u��������v�̉̂��g�������̑̑�
- �T�@�I�[�v���A�v���[�`�̓K�p
- ��������Z���b�@�̂��Ċo����I�@�傫�Ȑ��̒P��
- �U�@�I�[�v���G���h�A�v���[�`�̖��͂ƋA�[�@�̌����E�l����
- ��������Z���b�@����Ԃ͂�������H
- �V�@�I�[�v���v���Z�X�A�v���[�`�̖��͂Ɖ�㈖@�̌����E�l����
- �W�@�I�[�v���v���u�����A�v���[�`�̖��͂ƏW���̌����E�l����
- ��������Z���b�@�Ԃ��v�Z�@���v�Z
- �Q�́@�I�[�v���A�v���[�`�̗l��
- �P�@�I�[�v���G���h�A�v���[�`�̗l��
- ��������Z���b�@���Z�M�Z�E�A���S���Y���̉�
- �Q�@�I�[�v���v���Z�X�A�v���[�`�ɂ��l��
- �R�@�I�[�v���v���u�����A�v���[�`�̗l��
- ��������Z���b�@�Z���D���ɂȂ���Z�̋�����
- �R�́@�I�[�v���A�v���[�`�̋��ނƎ��Ɨ�S
- �P�@�g���C�A���O���_�C������i�R�N�@�O�p�`�j
- ��������Z���b�@�P�[�j�q�X�x���N�̋�
- �Q�@�Q�}�X�Ђ�~���l�߂悤�i�T�N�@��Ƌ����j
- �R�@�O�ʕM�Z�����悤�i�S�N�@�P���������鐔�j
- �S�@�݂�ȂŐw���Q�[�������悤�i�S�N�@�ʐρj
- �Z�����q����邽�߂̕\�L���᎑���@
- �S�́@�I�[�v���G���h�A�v���[�`�̋��ފJ��16
- ���ނ̃|�C���g�E���낢��ȓ����i�G���h�j�E���Ƃ̑�܂��ȗ���
- �P�@��P�w�N�@���{����10
- �Q�@��Q�w�N�@���肪�݂��S�ɕ����悤
- �R�@��Q�w�N�@100�����낤
- �S�@��R�w�N�@���W�ʑ̂ŃT�C�R���Â���
- �T�@��R�w�N�@�X�ł�������܂�
- �U�@��R�w�N�@99�������Ă݂悤
- �V�@��R�w�N�@�Q�l�ŕ�����Ƃ������͂�����
- �W�@��S�w�N�@���O�p�`�̕~���l�߂���͗l
- �X�@��S�w�N�@�W�ł���Ă݂悤
- 10�@��S�w�N�@������
- 11�@��S�w�N�@�T�C�R���ʂŐ����ƕ��s
- 12�@��S�w�N�@����������
- 13�@��S�w�N�@���肪24cm�̒����`�̖ʐ�
- 14�@��S�w�N�@�^���O�����ŁC���낢��Ȏl�p�`�Â���
- 15�@��S�w�N�@�����̓��b�L�[�H
- 16�@��T�w�N�@�����̂����Z�Ɛ����`�̖ʐ�
- �T�́@�I�[�v���v���Z�X�A�v���[�`�̋��ފJ���S
- ���ނ̃|�C���g�E���낢��ȉ������i�v���Z�X�j�E���Ƃ̑�܂��ȗ���
- �P�@��S�w�N�@��������Ƃ�����
- �Q�@��S�w�N�@�u�S�̂S�v�łP�Â���
- �R�@��T�w�N�@�d�Ȃ�̖ʐς́H
- �S�@��T�w�N�@25���������畉���ł�
- �U�́@�I�[�v���v���u�����A�v���[�`�̋��ފJ���V
- ���ނ̃|�C���g�E���낢��Ȗ��i�v���u�����j�E���Ƃ̑�܂��ȗ���
- �P�@��R�w�N�@�X�ł�������܂�
- �Q�@��R�w�N�@���̕\�̂����Z
- �R�@��S�w�N�@���Z�X�S���N
- �S�@��S�w�N�@�ѕ����Ɖ�����
- �T�@��S�w�N�@�X�|�[�c�X�Ōv�Z
- �U�@��S�w�N�@�[�H���ׂ����悤
- �V�@��S�w�N�@�P�ȏ�ɂȂ镪���̂����Z
- �Z�����q����邽�߂̕\�L���᎑���A
- �V�́@�I�[�v���A�v���[�`�̎��ƋZ�p��T��
- �P�@�I�[�v���A�v���[�`�̉ۑ�̂Q�ʐ�
- ��������Z���b�@�K�E�X���N�̉������z����
- �Q�@�I�[�v���A�v���[�`�̖₢�̂�������
- �R�@�I�[�v���A�v���[�`�̂��C�̂��������\�P�C�Q�łn�j�C�R�Łu����H�v�\
- �S�@�I�[�v���G���h�A�v���[�`�ɂ�����q�ǂ��̒Nj��̂�����
- �T�@���ׂ̒��ɂ݂�\�����鉿�l
- �U�@���c����������
- �V�@�I�[�v���G���h�A�v���[�`�ƃI�[�v���v���Z�X�A�v���[�`�̂Ȃ���
- ��������Z���b�@�q�ǂ��Ɗy����ł݂����v�Z
- �W�@�I�[�v���G���h�̐���̎��s�Ɛ����̗�
- �X�@�I�[�v���G���h�A�v���[�`�̖��Â���
- 10�@�I�[�v���v���Z�X�A�v���[�`�̖��Â���
- 11�@�I�[�v���v���u�����A�v���[�`�̋��ނÂ���
- 12�@�I�[�v���v���u�����A�v���[�`�̖��̂�����
�͂��߂�
�@�Z���̎��Ƃ́C�y�����Ȃ���Ȃ�܂���B����́C���E�ɏA�����Ƃ�����̐M�O�ł��B
�@�Z���̎��ƂŎq�ǂ��������C���X�ƎZ���Ɋւ���C�Â��\���Ă����Ƃ��C�Ⴄ�ꍇ�͂ǂ����낤�Ǝ��������Ƃ��C�ς��Ă݂Ăǂ��Ȃ�̂�����Ă݂悤�Ǝ��g�ݎn�߂��Ƃ��C�Z�����y����ł���ȂƎv���܂��B
�@�Z�����y������C�Z�����g�������Ȃ�܂��B�Z�����y������C�Nj��������Ȃ�܂��B�Z�����y������C�Z���̐��E���L����܂��B�Z�����y������C�݂�ȂɎ������킩�������Ƃ����������Ȃ�܂��B�Z�����y������C�݂�Ȃ������������Ă��܂��B�Z�����y������C�w�Z���y�����Ȃ�܂��B�Z���̊y�������傫�ȍ�p�������Ă����܂��B
�@���E�ɂ����N�C���ɂƂ��Ă̓^�C�����[�ȋ��E�������̎Z���ȎG�����n������܂����B�w�y�����Z���̎��Ɓx�i�����}���j�Ƃ����{�ł��B���̎G�����̌��t�̋����̂悳�ɂ��ꂵ���v���܂����B�Z���̊y�������㉟������܂����B�䂪�ӂ���ƐS�����v���܂����B�����C�y�������O�ʂɏo���G���́C���̑��ɂ͂���܂���ł����B
�@���N�C�}�g��w�������w�Z�ɂ���ꂽ�蓇���N�搶�́u���Ƃւ̒���V���[�Y�v��P���w�Z���Ȗ������̎��Ɓx�i�����}���j�Ƃ����{���o�ł���܂����B���̖{�͎��̎Z���Ȏ��Ƃ̃o�C�u���ƂȂ�܂����B���̐�����C�P�����ς�邾���ŁC�������q�ǂ��̔������ς����̂��Ǝv���܂����B�ʏ�ł́C�P��łP�̉����ł��Ȃ����ł����C���̒��Ɂ������Ď����ł��̒��ɐ������Ă�������̓������o�Ă���Ƃ������Ƃ��a�V�ł����B���̂Ƃ��C���߂ăI�[�v���G���h�Ƃ������t��m�邱�ƂɂȂ�܂����B���̖{�̒��̎q�ǂ������́C���Ɏ��瓭�������C���瓮���C����C�Â����C����l�����L���Ă������Ƃ��Ă��܂����B
�@��ł킩��܂������C�I�[�v���G���h�́C1971�N������Ɍ������n�܂��Ă��܂����B�������w���̂Ƃ��ɂ́C���łɂ��̎w���@�����݂��Ă����̂ł��B�������C���̂悤�Ȏ��ƂŁC�����������Ă���������Ƃ͂���܂���B�܂��āC���̂悤�Ȍ������L�����ĂP�̃u�[���̂悤�Ɍ������ꂽ�Ƃ������Ƃ������܂���B�����̐��ʂ��]�߂�̂ɁC���̎w���@���L�܂�Ȃ��͎̂c�O�Ȃ��Ƃł��B
�@���́C�蓇���̒�����ǂ�ŁC�I�[�v���G���h�̂悳�ɋ����䂩���悤�ɂȂ�܂����B�����āC���̎w���@���܂߂����̂��I�[�v���A�v���[�`�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B���̎w���@�Ȃ�C�Z���̖{���̊y�������q�ǂ����炪�����Ă������Ƃ��ł���ƁC�m�M���܂����B���̂߂������ƃX�^�C���������Ă��܂����B
�@�I�[�v���G���h�A�v���[�`�Əo����āC�����ƌ���������Ă��܂��܂����B���N�ɂ킽���Ēǂ������Ă����y�����I�[�v���A�v���[�`�̂悳���C�������ď����ł��Љ�ł��邱�Ƃ́C���ꂵ�����Ƃł��B
�@���̂悤�ȋ@���^���Ă��������������}���ҏW���̖؎R���ߎq����C�Z�����Ă����������O�Y�]���q����C�w�y�����Z���̎��Ɓx��ʂ��Č𗬂��C�����Ă����������������}���ҏW���̐����ÓT����ɐ[�����ӂ��Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂��B
�@�����ł��C�ǎ҂݂̂Ȃ���ɃI�[�v���A�v���[�`�̂悳���`���C�����̖ړI���B������܂��B�Ȃ��C�܂��܂������̓r��ɂ�����e�ł��B��������̂��w���₲�ӌ���������������ꂵ���v���܂��B
�@�@����24�N�V���@�@�@�^���i�@�h
-
 �����}��
�����}��