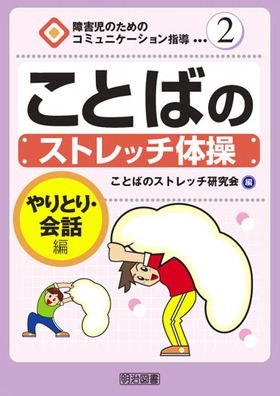- はじめに
- 第1章 会話する力の発達のとらえ方
- ―やりとり・会話する力のストレッチのために―
- 1 会話する力の発達
- 2 コミュニケーション態度の発達
- 3 会話が成立しない子へのアプローチ
- 4 やりとり・会話する力のストレッチ
- コラム 今,保育園で
- 第2章 事例
- 事例1 生活の基盤からの見直し−A君
- 事例2 音声的な基盤づくりから会話へ−Bさん
- 事例3 やりとりの基礎の指導−C君
- 事例4 やりとりの基本形をつくる−D君
- 事例5 オウム返しから応答的会話へ−E君
- 事例6 音声以外の方法でのやりとり−F君
- 事例7 ことばでのやりとりの獲得と,自己コントロールの高まり−G君
- 事例8 ことばと行動と心のモニタリング−H君
- コラム D君家の構造化
- 第3章 やりとり・会話指導の実技
- 1 生活の有り様
- 【工夫】
- コミュニケーションが必要になる家―やりたいこと一覧アルバム―
- 【母親へのアドバイス】
- 毎日違う連絡帳
- 親子遊び
- 親子遊び─D君の場合─
- 母と子日記
- 2 コミュニケーションに向かう
- リラクゼーション
- 指導者モデル法―「ぼくもしたいよ」―
- 呼びかけ法「〇〇せんせい」
- つながり遊び
- お店やさんごっこ
- 「いりません」「わかりません」
- 3 聞 く
- 【基礎】
- 〜はどれ? 〜するものはどれ?
- カード取り「最後まで聞く」
- カード取り「読み手交替」法
- 4 やりとりの基礎形成
- 【基本的姿勢】
- 「座る」こと
- 学習スケジュール,自分で進行
- セッションのスケジュール―お楽しみの挿入―
- 制止法(待ちましょう)
- 制止法(聞きましょう)
- 5 やりとり・役割交代
- 【番の理解】
- ローソク吹き消し法―「番」を理解する―
- 交替ゲーム法
- マイク法
- 【やりとり基本】
- ボールやりとり法
- 指さしのストレッチ「どっち?」「こっち!」
- 【やりとり場面繰り返し法】
- 要求応答繰り返し法―「〜ちょうだい」「〜して」―
- 日常あいさつ繰り返し法
- やりとりパターンの学習―日常生活で生かされる技法―
- 「どうぞ」「ありがとう」
- 【やりとりきっかけ法】
- 文字カード裏返し法
- 陰の声法―会話のモデルを聞く―
- ギャグ活用法
- 【発話のコントロール】
- ボリューム・コントロール法
- 設定おしゃべりタイム
- 【やりとり素材】
- 文づくり
- もしもし,〇〇さんですか!(電話でお話)
- 交渉ごっこ
- ぼくの宝物〈お話コーナー〉
- 【やりとり補助】
- 折りたたみ50音表─超簡便AAC─
- 6 表情・動作サイン・感情理解
- 表情福笑い法
- シールべたべた法
- 透明シートで表情変化法
- 「そおっと」
- コラム インリアル・アプローチ
- 〈資料1〉 2005年度ことばのストレッチ訓練キャンプ基本スケジュール
- 〈資料2〉 ことばのストレッチ訓練キャンプ要項
はじめに
ことばはあるが,発語行動が乏しい子がいます。発語行動はあっても,独語や反響言語が多くコミュニケーションのためにことばを使えない子がいます。それぞれの教育現場でこのような子どもたちに対する取り組みがなされていると思います。しかし,ことばでやりとり・会話する力をつけることをテーマにした書物は少なく,多くの教師は試行錯誤しながら取り組んでいるのが現状です。
ことばのストレッチ研究会では,2001年から発音・発語の指導と平行して,会話する力をつけることをテーマに実践研究に取り組んできました。この取り組みで分かったことは,発語が課題となる子ども以上に会話が課題となる子どもにとって,生活の有り様をどうとらえ,どう変えていくかが大切であるということでした。そしてその点をおさえた上で,いろいろな指導の工夫をすることで効果があがるということがわかってきました。この取り組みは継続中ですが,やりとり・会話編として現時点でのまとめをすることになりました。
第1章は,ことばで会話する力をつけるには,子どもの現状をどうとらえたらいいのか,指導する上でどのような点に気をつける必要があるのかについて述べました。
第2章は事例の報告で,我々の実践研究の中心です。これらの事例への取り組みの中から,第1章の考え方や,第3章の実技ができてきました。
第3章は各事例への取り組みの中で,指導者が工夫してきたことで,他の事例でも応用できそうなものをまとめました。教室でもすぐに利用できるものが多くあると思います。
本書で対象としているのは,中程度の知的障害がある子どもです。これらの子に対する指導では基礎的なコミュニケーション態度をつけることが重要です。一方,軽度発達障害の子どもで,会話はできるが,不自然さがあったり,トラブルがあったりしてディスコミュニケーションを起こすという子に対しては,メタコミュニケーションの力,語用論的能力をつけることが重要だと考えられます。この点については次の軽度発達障害編で述べます。
私たち現場にいる教師の実践研究の特徴は,一人または数人の子どもと密接に関わりながら,指導により子どもが変わっていく姿を見ながら研究するというところです。一人の子どもとしっかり関わることができます。しかし一方では,いろいろな子どもを知ることは難しいという面があります。自分の限られた経験に引き寄せて考えるなど,独りよがりになる可能性も出てきます。そこで必要になるのが共同研究です。ことばのストレッチ研究会では,それぞれのメンバーが少しでも経験を広げ多様な見方ができるように,お互いの経験を共有し,自由闊達に討論しながら取り組んできました。また,2004年からは,北田辺保育園との共同研究にも取り組んできました。本書の内容はまだまだ不十分なところもありますが,多くの方と共同研究し,ご指導いただきながら中身を高めたいと考えています。
このやりとり・会話編をまとめる中で,北田辺保育園の先生方には幼児の発達についてずいぶん教えていただきました。また,コラム「今,保育園で」で,幼児期のことばの発達について,具体的な様子がよくわかるようにまとめていただきました。
出版にあたりましては,発音・発語編に引き続き三橋由美子さんにお世話になりました。ありがとうございました。
2005年12月
-
 明治図書
明治図書