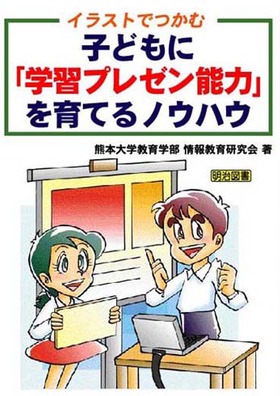- 1 はじめに
- ―教育にプレゼンテーションがなぜ必要か /塚本 光夫
- 現代の玉手箱/ 情報とは心を知らせること/ 道具だけが高度/ コンピュータは一つの道具/ 伝えたい心
- 2 プレゼンテーションの基本
- /澤 栄美
- プレゼンテーションはパフォーマンス/ こんなプレゼンテーションはつまらない/ 人を引きつけるテクニック
- 3 構成の立て方
- (1) 基本構成をこうつくる /前田 康裕
- (2) 小学校の事例 /前田 康裕
- (3) 中学校の事例 /上妻 昭仁
- (4) 養護学校の事例 /鶴田 雄二
- 4 ビジュアルプレゼンテーションのいくつかの方法とテクニック
- (1) 画面作りのポイント /吉冨 一樹
- (2) 紙を使う /吉冨 一樹
- (3) OHPを使う /島木 浩次
- (4) VTRを使う /島木 浩次
- (5) コンピュータを使う /吉冨 一樹
- (6) デジタルカメラを使う /岩田 秀樹
- (7) 書画カメラを使う /吉冨 一樹
- 5 いくつかのメディアを合わせて使う
- /田口 浩継
- 組み合わせのメリット/ メディアの特徴/ メディアの分類/ 組み合わせるときの留意点/ メディア選択の能力
- 6 学校でプレゼンテーション・スキルをこう高める
- /前田 康裕
- プレゼンテーション・スキルを高めるための三つのチェック/ リハーサル前の自己チェック(1)(練習前に)/ リハーサル前の自己チェック(2)(練習中に)/ 学級内でのリハーサル/ リハーサルの様子をビデオを使って自己チェック/ 児童生徒が自分でチェックするシステム
- 7 学習発表会をこう企画・運営する
- (1) テレビ会議で学習発表(小学校編) /岩田 秀樹
- (2) ジグソーセッションで学習発表(中学校編) /緒方 信行
- (3) 劇を通した学習発表(養護学校編) /中山 龍也
- 8 あとがき
- /塚本 光夫
1 はじめに―教育にプレゼンテーションがなぜ必要か(冒頭)
/塚本 光夫
現代の玉手箱
「むかし、むかし、あるところに……」
で、大抵の昔話は始まります。この「むかし、むかし」はいったい、いつのことでしょうか。本書では、いつのことかを明らかにするつもりはありませんが、学校の学芸会や文化祭で催される昔話を演じるときの衣装は、縄文や弥生時代のものでもなく、かといって江戸時代や明治時代のものでもなさそうです。昔話の中には時代を限定させるものはほとんどありませんので、どうやら幼いときに読んだ昔話の絵本の「絵」の印象によるようです。「絵」が与える印象とはそれほど強いものなのです。「百聞は一見にしかず」のことわざのとおり、眼から受ける印象は強く、記憶力の優れた人はほとんどの事柄を映像として記憶するというのもうなずけます。
数千年後の絵本では、桃太郎は洗濯機から飛び出し、浦島太郎は水中眼鏡をしているかも……。
現代は高度情報社会といわれていますが、コンピュータはさしずめ現代の玉手箱のようなものかもしれません。その中には情報がたんまりと入っていて、開けたとたん洪水のように情報があふれ出してきます。特に、インターネット時代の玉手箱にはとんでもない量の「煙」が詰め込まれています。ただし、現代の玉手箱は開けると年を取るのではなくて、開けないと最新の情報が得られないことになってしまうのが、ちょっと違うところです。
昔話の玉手箱は竜宮城に行かないと頂戴できない代物でしたが、現代の玉手箱は誰にでも手に入れることが可能になりました。学校現場も自由に利用できるような環境になり、家庭に玉手箱があるという子どもたちもいます。
現代の玉手箱はそこここにあります。
情報とは心を知らせること
ある大学生が、卒業論文のために、ある学校で自分の開発したソフトウエアを児童生徒たちに利用してもらいました。おそらくは開発したソフトウエアに自信があったのでしょうが、そのソフトウエアがまったく利用できる代物ではないとわかり打ちのめされてしまいました。しかし、改良したソフトウエアを利用してもらうと、子どもたちは楽しそうに使うようになりました。別に子どもたちは開発者である大学生に「かわいそう」だからという同情心があるわけもなく、的確な評価を与えていたにすぎません。
その大学生には、相手が見えていなかったのです。
相手を見る、すなわち相手を十分に知ることの大切さは誰でも理解していることですが、実際には忘れがちなことでもあります。相手を知ること、それは相手の心を知ることであり、その心に自分の心で伝えることが肝心なのです。
情報の「情」は「なさけ」で、「報」は知らせることを意味します。つまり、情報とは「心を知らせる」ことであり、心のこもった内容を相手に伝えることが重要です。
一人の人が多くの人に自分の心を伝える方法がプレゼンテーションです。心の中身が重要であることは当然ですが、相手に正しく自分の心を理解してもらうにはそれなりの手段が必要で、それもまた重要なことです。
自分の真意が相手に伝わらず、困ったことは誰にでもあるはずです。
-
 明治図書
明治図書