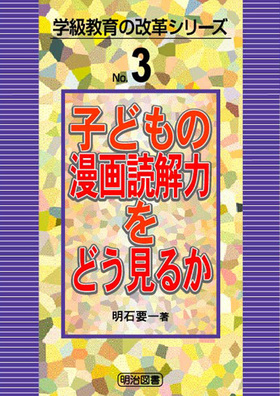- はじめに――四つの疑問に答える
- 1 漫画っ子の特徴
- 一 漫画に熱中する子どもの特徴
- 1 子どもの漫画接触行動
- 2 「漫画読み」行動
- 3 どんな漫画を読んでいるか
- 4 漫画熱中タイプはどんな子どもか
- 二 元気印の漫画熱中子ども
- 1 漫画熱中タイプはよく外遊びをする
- 2 漫画熱中タイプは自信を持つ
- 3 熱中タイプは強い願望の持ち主
- 三 学校図書館に通う漫画っ子
- 1 学校図書館はどんな子どもが利用するか
- 2 漫画好きな子どもは図書館に行くし、要望も強い
- 2 漫画の効用
- 一 落書きに見る豊かな漫画表現
- 1 子どもの落書きは「楽書き」となる
- 2 多い漫画表現の落書き
- 二 成長させる漫画
- 1 漫画はどんな影響を与えるか
- 三 喜怒哀楽の体験がある漫画
- 1 漫画で「涙」を流す
- 2 漫画を読んで「怒る」
- 3 主人公に「恋」をしたことがあるか
- 四 漫画読解力を測定する
- 1 漫画読解力とは
- Ⅲ 親・教師・社会は漫画をどう見ているか
- 一 母親は子どもの漫画読みをどう見るか
- 1 母親の漫画観
- 2 なぜ母親は子どもの漫画読み行動に寛容になったのか
- 3 母親から見た漫画の将来像
- 二 授業に漫画を活用する教師
- 1 道徳の授業で漫画の資料を活用する
- 2 漫画活用の授業はどう展開したか
- 3 吹き出しの内容と学習成果
- 三 漫画は国境を超えるか
- 1 漫画は世界の共通語か
- 2 『少年ジャンプ』が六〇〇万部を超えた秘訣
- 四 日本の子どもの特色はどこにあるか――漫画っ子誕生
- 1 戦後の子どもの漫画環境の変遷
- 2 米国の日系の子どもと日本の子どもの違い
- 終わりに――漫画と勉強の関係の捉え直し
- 1 漫画読解力のない大人たち
- 2 漫画読解力の効用
- 3 勉強の意味の変遷
- 4 学校が権威を失ってきた
- あとがき
はじめに――四つの疑問に答える
日本が漫画王国と呼ばれるようになって久しい。確かに子どもにとって漫画はなくてはならないものになっている。寝るときに、漫画を読むという中学生が大半という報告まである。
こうした漫画好きは子どもだけにとどまらない。電車の中で漫画を読む成人男子は今や珍しくない。
日本人論を語るとき漫画抜きにはできなくなっている。
ところが、漫画論は多く出版されてはいるもののこれまでの漫画研究は、漫画に書かれたヒーローの分析やストーリー展開を中心とした内容分析に基づくものが多かった。
子ドもを対象にした実証研究は意外と少ない。例えば、次のような素朴な疑問に答える研究が少ない。
一つは、漫画の読み取り能力と学校の教科の成績は結びつくのだろうか、である。
漫画の読みの早い子どもは、学校の国語や算数の成績もよいのであろうか、という素朴な疑問である。
二つ目は、子どもたちはいつごろから漫画を読み始めるのだろうか。漫画を読み取る基礎能力はどのように発達するのであろうか。そして、漫画を読まなくなるのはいつごろだろうか、である。
三つ目は、五〇歳を超えた大人が『少年ジャンプ』を読めなくなったり、少女漫画についていけないのはなぜだろうか、である。
活字が小さいからなのか、それとも老眼が進んでいるからだろうか。
四つ目は、漫画に熱中している子どもは、果たして教師や親が言うほどにおかしな行動特性を持っているのだろうか、という疑問である。
漫画に熱中するというエネルギーは、その子なりのよさではなかろうか、という考えもできるのではなかろうか。
そこで私は、そうした疑問に答えようとした。これから報告することは、「現代児童文化研究会」がまとめた『子どもと漫画』―「漫画読解力はどう発達するか」――を土台にしている。それは次の二つの実証研究を行った。
一つは、子どもと親を対象にしたアンケート調査である。
二つ目は、子どもが好きなドラえもんの漫画を実際に読んでもらう、というアクション・リサーチである。しかし、執筆した内容に関しては筆者にすべて責任がある。
調査対象は千葉県下の小学四、六年生と中学二年生約一二五六名、調査時期は平成四年の七月。母親調査は幼稚園と小学生を持つ親五二七人、時期は子どもと同じ。
千葉大学教授 /明石 要一
-
 明治図書
明治図書