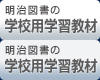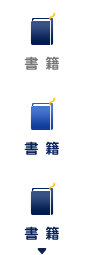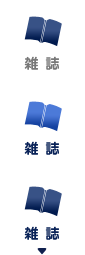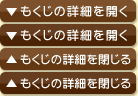- まえがき
- はじめに――子どもを「主人公」として育てるということ
- 第1章 「表情する身体」と向かい合い、応答し合う
- 一 教育実践の現実――「表情する身体」としての子どもたちとの出会い
- 二 子どもたちが「居場所」を実感するとき
- 三 子どもは「説明」される対象ではない、「理解」されるべき個性である
- 四 語りかけ、応答し合う「関わり」のなかでしか個性は見えない
- 第2章 自他関係としての存在感
- ――「あてにする―あてにされる」関係の成立
- 一 新学力観に応える新授業観
- 二 「頭と体」の分裂と、その統一 ――「あてにする―される」関係のなかで
- 三 身体の「居場所」(庇護感)
- 四 授業成立の現象(学)
- 第3章 歴史的身体としての子どもを「現在」の視点でとらえる
- ――「個を生かす」教育のために
- 一 「個に応ずる」のではなく「個を生かす」ことを
- 二 障害を「個性の一部」として受容し、理解する
- 三 「歴史的身体」を生きている子ども
- 四 過去と未来の「同時存在」としての現在を生きる子ども
- 第4章 「否定」を「肯定」に転化する
- ――「現在の矛盾」を生きる子どもたちのために
- 一 一人のなかの「二人の自己」――歴史的現在を生きている子どもたち
- 二 自己内対話の成立――「自己(主人公)となる」ために
- 三 「教育する」ことの知と技術
- 四 個性の発見と肯定的評価
- 第5章 「教える」ことの「知の考古学」
- ――「指導」(指さして導く)概念の確立を求めて
- 一 「指導」の概念が揺れている
- 二 「教える」と「学ぶ」の弁証法
- 三 子ども主導か、教師主導か――二元論の克服のために
- 四 「教える」ことの「知の考古学(原型)」
- 第6章 「発見学習」の歴史と現代授業論の課題
- 一 「発見学習」の歴史的系譜
- 二 「発見学習」の近代的性格
- 三 現代教授学の課題
- 第7章 現代教授学の課題
- 一 人間における「自然」概念の再検討
- 二 教育における「集団」概念の再検討
- 三 授業における「指導」概念の再検討
- 第8章 西ドイツにおける教授学研究の方法論
- 一 教育科学研究における三つの立場
- 1 解釈学的方法
- 2 経験科学的方法
- 3 社会批判的・イデオロギー批判的方法
- 二 教授学研究における三つのモデル
- 1 教授学研究の背景
- 2 教授学研究のモデル
- 三 授業研究の方法
- 第9章 授業研究への接近と方法
- 一 授業研究への接近
- 二 わたしにとって授業研究とは何か――「辞書」と「テレコ」との間
- 三 授業を「見る」ことから「つくる」ことへ
- 1 「授業研究」への出発
- 2 「見る」授業から「つくる」授業へ
- 四 「教える―学ぶ」の「知の論理」――戦後授業論における「二つの典型」
- 1 教育実践を捉える「知のモデル」
- 2 「たぐりよせ」と「うなずき」の論理――東井義雄における「学習帳」
- 3 「授業が成立する」ということ
- 4 可能性を引き出す「介入」と「ゆさぶり」の論理――斎藤喜博における「指導案」
- 5 「教える―学ぶ」における「学習帳」と「指導案」
- 第10章 授業研究キーワード
- [1] まなざしで身(固有名詞)に呼びかける――最初の「居場所体験」として
- [2] 「語る」ということ――「話す」ではない
- [3] 語る=騙るということ――評論・判定ではない
- [4] 個性を「理解」する――「説明」ではない
- [5] 「導入」とは何か――「自ら学ぶ関心、意欲、態度」を呼び起こす
- [6] 「ヤマ場」とは何か――思考力、判断力、表現力を鍛える
- [7] 対話と討論と問答を――新学力観に応える授業のために
- [8] 体験知・身体知とは何か
- [9] 内発的な学習意欲――「外から」の動機づけではない
- [10] 達成感・上達感ということ――達成の結果ではない
- [11] 「個を生かす」ということ――「個に応ずる」ではない
- [12] 「発見としての肯定」評価――過程評価・指導と評価の一体化
- [13] 授業に「参加する」ということ――「出席」ではない
- [14] 一人のなかに「二人を見る」子ども感――新しい指導観のために
- [15] 身に「ふれる」ということ――肉体に「さわる」ではない
- [16] 教えねばならないことは「教えてはならない」
- [17] 「指さし」としての発問――「尋問・質問」ではない
- [18] 「授業のわかり易さ」ということ――教材を「軽くする」ことではない
- [19] 教師のタクトとは何か――「生まれつき」「天性の器用」ではない
- [20] 「呼びかけ・問いかける」指導案を――「伝達」でも「支援」でもない
- [21] 「向かい合う」という関係――「天使」にも「悪魔」にも成る
- [22] 「ドラマ」としての授業――「事件」としての授業ではない
- [23] 「無限の」可能性は、呼び起こされねばならない
- [24] 他人のなかに自己を見る力
- 第11章 教師の「まなざし」と「タクト」を鍛えるために
- 一 教室を「まなざしの範囲」にする
- 1 「まなざし」は「眼」ではない
- 2 学校は「まちがう」ところ
- 二 子どもを「人間」としてとらえる力と感性
- 1 レッテル貼りの問題点
- 2 一人のなかの「二人の自分」
- 三 教師における技術と徳
- 1 教師の徳とは何か
- 2 教えることの技術の独自性
- 四 授業研究とタクトの自己形成
- 五 教師が教師になるときに、子どもが子どもになる
- 1 職場づくりの原点
- 2 授業公開と校内研究
- あとがき――教えると学ぶ、その統一のあり方を求めて
- 解説 教授学の知と現代授業研究への問いかけ /白石 陽一・湯浅 恭正
- 1 教授学における「人間学的」問い方――その課題的成果
- 2 「まなざし」と「身体」の教授学
- 3 競争原理との対峙と権力関係への関心
- 4 現代学校への期待と教授学研究
- 5 授業づくり研究へのスタンス
- 6 教師の成長と授業研究
- 付記
- 吉本 均の主要著作と略年譜
まえがき
本書は、吉本均の「著作選集」の一冊である。吉本均は、戦後わが国の大学に制度的に誕生した教育方法学という学問領域を教授学研究の立場からリードし、教育実践の現場においては授業研究にもとづく学習集団づくりを推進した研究者として知られている。二十一世紀に入り、教育について混迷の度を増すこの時期に、吉本均の多数の著作を「学級の教育力を生かす吉本均著作選集」として編集し、刊行を決断したのは、吉本均の教授学や学習集団づくりの理論と実践に関する知見が、こんにち、なお意味があり、現代社会は、いまこそ、吉本均の著作や言説を必要としていると考えたからである。吉本均の著作は、次の五つの観点から読みつがれる必要がある。
第一に、吉本均の提起した教授学や学習集団づくりの理論は、「学級の教育力」を生かして授業を成立させ、発展させるものである。それは、学級に「ともにある」子どもたちと教師が、ちからをあわせて、よい授業をし、よい学級をつくろうとするものである。こんにち学校教育は、学力向上の成果のみにとらわれていて、授業は生き方や態度の形成をもめざしていることを忘れている。子どもたちの連帯は失われ、学習は、個人主義的なもの、周囲との関係から逃避する利己主義的なものに変質し、そのため安易な「学級解体」論が横行したりしている。
しかし、近年、わが国の授業研究は、世界から「レッスン・スタディ(Lesson Study)」として注目されている。そこでは、日本の授業が、子どもたちの関心や情緒を喚起して、子どもたち相互を親密にかかわり合わせ、「間違い」や「つまずき」を大切にした集団的な学習であることが着目されている。吉本均は、「連帯のある学級」をつくることと「わかる授業」をするということを同時に実現するように授業を構成すること、授業が子ども相互の親密な連帯を基盤として営まれることを説いてきた。世界が日本の授業研究に注目する時代に、あらためて「学級の教育力」を生かした授業を実現することを追究してきた吉本均の著作は、読みつがれる必要がある。
第二に、吉本均の授業の構想は、「底辺」の子どもたちに「まなざし」をそそぎ、そうした子どもたちが授業に参加し、授業内容にかかわって発言するようになることを見通したものである。「習熟度別授業」が学校現場に広がるなか、学級のなかの「できる」子どもも「できない」子どもも、「ともに」授業に参加し、授業のなかで発言し、相互にかかわり合うことによってこそ、一人ひとりの学びを深めることができ、学力を保障するものになるという学習集団づくりの知見を、いまこそ引きつぎ、発展させなくてはならないと考えたからである。
学習集団づくりが誕生した時代は、学校へ行くこと、授業に参加することが積極的意味を持っていた時代であった。「全員参加」や「全員発言」という言葉が、そのまま実践の推進力になりえていた。しかし、こんにち学校へ行く意味が問われる時代、公教育の意義が問い直される時代がやってきた。学校に来ることを拒む子ども、学校に来ても発言を拒む子どもには、「全員参加」や「全員発言」は、ある種の「成果主義」に映らないだろうか。われわれは、子どもたちが学校へ行くことには、いまなお意味があると考える。また、子どもたちにとって意味があるように公教育を維持し、発展させなければならないと考える。しかし、こうした状況の変化に対して、学習集団づくりは再構成される必要がある。しかし、そのさい、吉本均が、どのような「まなざし」で学習集団を組織しようとしたかの原点を継承し、こんにちの状況に合わせて読みひらかれる必要がある。
第三に、吉本均の学習集団づくりによる授業の構想は、「~さんの発言につけくわえます」「~さんの発言に反対します」といった「発言形式」を発展させて、発問による「対立=分化」から「真理=真実」の共有をめざした「接続語のある授業」を求めた。授業は、教室のなかで教師の教材解釈をもとに行われる。学習集団づくりの授業においても、教師は、教材解釈をもとに発問をし、集団思考を組織する。学習集団の授業は、教授行為の主体である教師と学習行為の主体である子どもたちとの「対決」ととらえて、ときに子どもたちが教師の教材解釈を乗り越えうることを示してきた。
授業のなかで、子どもたちは、教科書や板書を読み、ノートに書き、教師や同級生の発言を聞き、教師や同級生のほうに向かって自分の考えを話す。読み、書き、聞き、話すのは一人ひとりの子どもたちであるから、その意味では学習は個人的なものである。しかし、読み、書き、聞き、話すには、相手や他者が必要であるという意味では、学習は集団的、社会的なものである。このような、読み、書き、聞き、話すという言語行為を媒介として、学力は育てられる。そうすると学力とは教科内容にかかわった読み、書き、聞き、話す能力のことであり、その視点から学習集団づくりの理論や授業の構想は、教科内容論と言語行為論とを結合させて発展させられなければならない。この意味で、学習集団づくりにおける言語とコミュニケーションの理論がとらえなおされ、発展させられねばならないのである。そのためにも吉本均の著作が読みなおされる必要がある。
第四に、吉本均が授業実践の現場で新しい学問的知見を取り込みながら、たえず更新しつづけた教授学の構想は、学校教育や授業という枠をこえて、保育や看護といった福祉やヒューマンサービスの世界、あるいは人を育てる仕事において見直されているからである。授業研究の現場で、たえず教育実践のリアリティやアクチュアリティに迫ろうとしてきた吉本均の教授学は、「教室の人間学」へと発展し、授業を「見る―見られる」相互的表情関係、身に「ふれる―ふれられる」相互身体的関係、「語る―語られる」相互主体的関係、「呼びかける―学びとる」呼応的関係、「問いかける―選びとる」ドラマ的関係、といった五つの相互作用の位相からとらえる。「表情する身体」を生きている子どもたちと出会い、「まなざしで身体に語りかける」日常を教師もまた生きていることを豊かにとらえ励ます教授学キーワードや関係論的視点は、同じように「人が人とかかわりあう」職場である看護や福祉の世界にも通じている。この意味で、吉本均の著作は、学校教育を越えた世界から、再評価される必要がある。
第五に、吉本均による教授学の人間学的構想にいたる学問的な歩みは、組織やイデオロギーといった「上から」の発想ではなくて、たえず人間のあり方そのものの現実にきびしく「向かい合う」学問的姿勢とそこから深まる人間観に支えられたものである。教育とは、「明日を生きる喜び」を一人ひとりに教えることであり、一人ひとりの「可能性への愛と要求」のドラマを実現していく仕事である。そうした仕事のためには、できるだけ文献にあたることと現場実践上の問題にふれることとを結びつける学問の方法論が必要である。いわば、レファレンス(理論研究)とフィールドワーク(実践研究)との統一を心がけなくてはいけない。専門職にとって、実践経験は大切なものであるが、なぜそのように実践するのかという理論的説明を欠けば、専門職の本質的な意味での進歩はない。教職の専門性が問われる時代にあって、あらためて学問的な方法論の原点に立ち返り、そこから学び続けなくてはならないからである。
以上のような五つの観点において、本「著作選集」は、たんに追憶のために刊行するのではなく、これから求められる教育方法学の研究と教育実践の前進のために刊行するものである。
吉本均の「著作選集」を編集するにあたって、その単著、編著、訳書、論文等の膨大な著作群から、何をどのように選択し配列するかは重たい課題である。先生の教えを受けたものたちが集まって「著作選集」の刊行へ向けて、何度も論議を積み重ねてきた。結局のところ、単著を基本としつつ必要に応じてその他の著作から補うようにして、全体の構成が、吉本均の「教授学と学習集団づくり」の理論的発展が読みとれるように選択配列し、以下のように五巻を構成した。
第一巻 授業と学習集団
第二巻 集団思考と学力形成
第三巻 学習集団の指導技術
第四巻 授業の演出と指導案づくり
第五巻 現代教授学の課題と授業研究
第一巻から第五巻へ向けて、吉本教授学の思想史的あるいは問題史的な発展を基本としているが、各巻の主題に応じて必ずしも歴史的順序で配列されているわけではない。歴史的なものと原理的なもの、理論的なものと実践的なものの緊張と統一のうちに、みずからの教授学をたえず更新して現場実践に通用する学習集団づくりの理論形成をはかってきたのが吉本均における「教育の思考形式」だからである。それぞれの巻の位置づけや特質、現代的な意義や引き受けるべき課題については、各巻の編者による解説を付してある。また、吉本均の「主要著作と略年譜」を第五巻の巻末に掲載したので、あわせて参照してほしい。
学習集団づくりによる授業研究は、現場の教師を授業研究者、よい実践を、ともにちからをあわせてつくりだす研究のパートナーと考えてきた。教育方法学は実践のため、教師のために役立たなければならない。また授業や学校づくりに多くの人々が関与する時代にあって、本「著作選集」が、教師はもとより、教育実践に関心を寄せる多くの人々によって読まれ、ちからをあわせて次の時代の教育方法学を築き上げる礎となることを希望する。
文末になりましたが、本「著作選集」の刊行にさいしては、吉本均の最初の単著である『授業と集団の理論』以来、ご本人のお言葉を借りれば「先生の戦友として」一貫してご支援をいただいている明治図書相談役の江部満氏、さらに出版事情の厳しいおりにご助言等をいただいた樋口雅子編集部長に感謝申し上げます。
二〇〇六年六月
吉本均著作選集刊行委員会・広島大学教育方法学研究室 /中野 和光 /深澤 広明
-
 明治図書
明治図書