- まえがき
- Ⅰ 国語教材研究への文体論的アプローチ
- ―文学教材における〈自由間接話法〉の諸相
- 1 〈自由間接話法〉をなぜ問題にするのか―いわゆる「三人称教材」の問題
- 2 知覚・意識のレベルから捉えた〈自由間接話法〉の諸相―「情景」概念の再検討
- 3 情景・心情の読み取り指導の問題点―国語科の授業を呪縛するもの
- 4 〈自由間接話法〉における「時制(テンス)」と「時間副詞」
- 5 授業のなかの〈自由間接話法〉
- Ⅱ 国語教材における〈話法〉の問題
- ―「『出口』論争」と〈自由間接話法〉
- 1 はじめに―「『出口』論争」への視角
- 2 宇佐美寛氏の「『出口』実践」批判―「宇佐美・西郷論争」への前哨(その一)
- 3 池田久美子氏の「『出口』実践」批判―「宇佐美・西郷論争」への前哨(その二)
- 4 「斎藤実践」の構造―「指示物」と「意味」
- 5 「宇佐美・西郷」論争―「言語理論」対「文芸学」
- 6 「視点論」の問題―〈語り〉の軽視
- 7 〈話法〉論から見た〈出口文〉―〈自由間接話法〉
- 8 現代日本語文法論による〈出口文〉の分析
- Ⅲ 「冬景色」論争の問題圏
- 1 はじめに
- 2 文学の芸術的自立性・特殊性から文学の言語的自立性・特殊性へ
- 3 西郷文芸学における「語り手」「語り」の軽視
- 4 「冬景色」の〈語り〉の構造
- 5 「冬景色」論争における〈情景論〉と西郷文芸学
- Ⅳ 〈示すこと〉と〈語ること〉
- 1 はじめに
- 2 時間表現における〈示すこと〉と〈語ること〉
- 3「直接話法」及び〈自由間接話法〉―〈示すこと〉と〈語ること〉の間
- 4 国語科教育における〈示すこと〉と〈語ること〉の問題―「ニュース番組」の形式を取り入れた説明文指導
- Ⅴ 国語教育への教育関係論的視点
- ―「読者論」の諸問題
- 1 はじめに
- 2 関口「読者論」の問題点―「ダブルバインド」としての教育関係
- 3 「かくれたカリキュラム」
- 4 文学教育における美的価値・道徳的価値・客観的真理
- 巻末
- 【注】 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
- 【付録】 「山の子ども」全文・「冬景色」複写
- あとがき
まえがき
本書は、この六年間余り、私が、国語教育にかかわりながら、考えてきたことに基づいて書かれている。
ここでは、表題にあるように、戦後の国語教育論争史に名を残す二つの論争「『出口』論争」と「『冬景色』論争」を主に取り上げ、私なりの観点から、この論争の展開・意味合いを考察したものである。
そもそも、きっかけは、本書でも触れているが、小学校低学年の教室で、「吹き出し」をつかった文学教材の授業を見、子どもたちが吹き出しに書き入れていることばに私自身、違和感を感じ、素朴な疑問をもったことに端を発している。ここから、文学教材を扱う上での、混乱を招く問題の背景として、語り手と、その語りのあり方、あるいは、語り手がどのような話法を用いて登場人物のことばや気持ちを書いているかということへの現場における関心の希薄さがあるのではないか、さらには、文学理論における「ナラトロジー」の考え方が文学教材研究には逸することができないのではないかと考えるようになった。
実際、様々な文学理論あるいは言語理論がこれまで積極的に国語教育・文学教育の授業実践に取り入れられ、多くの成果を上げてきたことは疑い得ない。しかし、従来の「視点論」「人称論」等から〈語り〉=ナレーションの問題や話法構造―特に、〈自由間接話法〉の解明は不十分だったのではないか。本書では、こうした課題意識に立ち、先の二つの論争において、なにがどのように問われ、論じられていたかを考えていきたいと思う。これは、たんに今日、文学偏重として縮小されつつある文学教育のみの問題ではないことも銘記しておきたい。音声言語における伝達・ナレーション、コミュニケーション能力としての「語る力」とも密接に連関しているテーマでもある。
解釈学を経由し、読者論あるいは読者反応批評が、近年の個性尊重、個に応じた教育の主張のもとで、国語教育の大きな潮流となっているが、たとえば、スタンレー・フィシュなどの、そのラディカルな読者論の展開は、科学的真理や客観性までも相対化し、言語学や文法理論の体系をもひとつの相対的な解釈・読みの帰結ととらえるに至っている(『このクラスにテクストはありますか』みすず書房 一九九二年)。なるほど、たしかに、あらゆる「知」が歴史的・社会的状況のなかに文脈化され、相対化されれば、〈読み〉の客観性、正しい〈読み〉にこれまで覆い尽くされてきた個の〈読み〉、読書のもたらす多様な経験世界を解放する有力な契機ともなりえるだろう。だが、しかし、すべての知が視点拘束的かつ相対的であるとして、解釈の相対性を主張することは、つねに真理への問いと探究心を断念する、いわゆる相対主義、怠惰な遠近法主義へと陥る危険と背中合わせであることを忘れてはならない。このことはまた、議論のはてしない相対性に倦んだ結果として、「文学は腹で読むのだ」「文学は理屈じゃない」式の反知性主義・反教養主義的な印象批評的独断および非学習論的教育を振り回す論調とも密接に重なりあっているといえるのである。
本書のⅤ章では、「主観読み」と「客観読み」に分けることで、関係項を関係に先立たせる〈読み〉の捉え方の問題点を、〈読み〉における方法意識のあり方に論点をおいて、私は考察した。しかし、まだ、十分展開したとはいえない。今後とも、読者主体とテクスト(読書対象)の関係項をすでに内に取り込んでいる関係ないし場面としての「読書行為」のあり方に焦点を据えながら〈読み〉の問題を考えていこうと思っている。






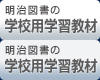


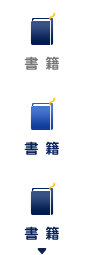
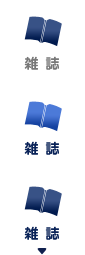



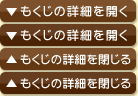

中村氏はまず、北原保雄氏の文法論に従って、次の二種類の連用修飾用法を区別する。
(1)情態修飾。「ありがたく頂戴して、帰った」「懐かしく拝見しました」「楽しく遊んだ」〔127ページ〕という文における「ありがたく」「懐かしく」「楽しく」の修飾のしかたである。この場合、「ありがたく」「懐かしく」「楽しく」は「あくまでも動作主の主観を表しており、表現主体のそれではない」〔127ページ〕とのことである。
(2)注釈修飾。「珍しく、一週間ぶりに雨が降った」「彼はそれを確かに 右手ではなく、左手に持っていた」〔127ページ〕という文における「珍しく」「確かに」の修飾のしかたである。この場合、「表現主体が『珍しく』あるいは『確かに』という思いを表す表現部を、表現主体の主観的な判断・評価に基づく『注釈』と捉え、『注釈修飾成分』あるいはたんに『注釈修飾』と呼」〔127ページ〕ぶとのことである。
以上のような区別を設けた上で、中村氏は次のように問題を提起した。〈出口文〉に用いられている「『やっと』という副詞は、注釈修飾なのか、情態副詞なのかが問題となるだろう。言い換えれば、副詞『やっと』は『表現主体の主観』なのか、『動作主の主観』なのかである」〔128ページ〕。
この問題について中村氏は、次のように宇佐美寛氏と西郷竹彦氏の説を比較した上で自説を述べている。
-----------<引用はじめ>-----------
……宇佐美氏の立場では、「やっと」は「話主の心理」「話主の心情」(「表現主体の主観」)を表すところの「注釈修飾」にあたることになろう。一方、西郷氏の立場からは、「あきおとみよ子」の気持ち(「動作主の主観」)を表す情態修飾と見ることができる。
この〈出口文〉の場合、副詞「やっと」は、はたしてどちらなのか。北原氏の文法論からすれば、「やっと」は明らかに情態修飾である。「やっと」は、「表現主体の主観」ではなく、登場人物「あきおとみよ子」という「動作主の主観」を表しており、宇佐美氏の言う「話主の心理」「話主の心情」ではない。〔129ページ〕
-----------<引用おわり>-----------
ここで、「北原氏の文法論からすれば、『やっと』は明らかに情態修飾である」と中村氏は断定しているが、果たしてそうであろうか。
例えば、先の「珍しく、一週間ぶりに雨が降った」という文の「珍しく」を「やっと」に置換してできた文「やっと、一週間ぶりに雨が降った」において、「やっと」が「雨」の主観ではなく表現主体(語り手)の主観を表現しているのは明らかである。
また、例えば「赤ちゃんがやっと立ち上がった。」という文において、「やっと」は動作主「赤ちゃん」の主観を表現していると言えるだろうか。さらに、「野良猫たちはやっとゴミあさりをしなくなった。」「昨夜からの大雨も今朝になってやっとおさまった。」「今月の仕送りがやっと届いた。」ではどうか。明らかに、これらの例文で使用されている副詞「やっと」は、「赤ちゃん」「野良猫たち」「大雨」「仕送り」ではなく表現主体(話主、語り手)の主観を表しているのである。
中村氏が、〈出口文〉における副詞「やっと」が「動作主の主観」を表しているといると主張するならば、「やっと、一週間ぶりに雨が降った」や「赤ちゃんがやっと立ち上がった」のような文に使用されている副詞「やっと」との違いを説明した上でなければならない。しかし、そのような論証はいっさいないまま、《〈出口文〉における副詞「やっと」は「宇佐美氏の言う『話主の心理』『話主の心情』ではない」》と決め付けている。
以上のように、中村氏による説明は不十分である。