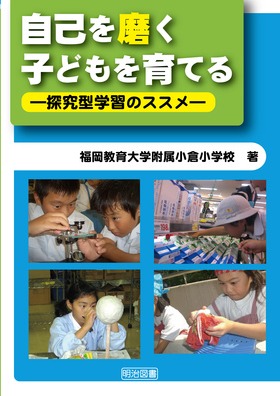- �͂��߂�
- �T�@���_��
- [�P]�@���������߂���q�ǂ����C���t��
- (1)�@����������Ă����q�ǂ����`���Ȃ��q�ǂ��`
- (2)�@���������߂����Ă��鋳�t��
- (3)�@���������߂����Ă���w�K
- [�Q]�@�Ȃ��C�T���^�w�K��
- (1)�@���������߂���T���^�w�K�Ƃ�
- (2)�@�T���^�w�K�����߂���w�i
- [�R]�@�u�P���v�̈Ӗ���₢����
- (1)�@�w�K�̎�̎҂͂���Ȃ̂�
- (2)�@�u�P���v�Ƃ�
- [�S]�@�T���^�w�K���f�U�C������
- (1)�@�T������u���v���ᖡ����`�u���S���v�Ɓu���͖��v�`
- (2)�@�q�ǂ��̕ϗe�̎p����̓I�Ɏv���`��
- (3)�@�T���̃X�g�[���[������
- (4)�@�q�ǂ��̖��������x����
- �U�@���H��
- [�P]�@����ȁi�u�������Ɓv�j�ɂ�������Ƃ̎���
- [�Q]�@����ȁi�u�ǂނ��Ɓv�����I�ȕ��́j�ɂ�������Ƃ̎���
- [�R]�@�Љ�Ȃɂ�������Ƃ̎���
- [�S]�@�Z���Ȃɂ�������Ƃ̎���
- [�T]�@���Ȃɂ�������Ƃ̎���
- [�U]�@�����Ȃɂ�������Ƃ̎���
- [�V]�@���y�Ȃɂ�������Ƃ̎���
- [�W]�@�}��H��Ȃɂ�������Ƃ̎���
- [�X]�@�ƒ�Ȃɂ�������Ƃ̎���
- [10]�@�̈�ȁi��B�^���\���є��^���j�ɂ�������Ƃ̎���
- [11]�@�����ɂ�������Ƃ̎���
- [12]�@���ʊ����i�w�������j�ɂ�������Ƃ̎���
- [13]�@�����I�Ȋw�K�̎��Ԃɂ�������Ƃ̎���
- [14]�@�O���ꊈ���ɂ�������Ƃ̎���
- �����Ɂ@�U���̋���ƒT���^�w�K
�͂��߂�
�@�킪���������w�������q���w�Z�́C����23�N�ɑn��100���N���}���邱�ƂɂȂ�܂����B���܁C�����C�������q���w�Z�̍Z�����ɂ́C��������^���ꂩ��̈�ق���C���x�݂̎q�ǂ������̌��C�ɗV�Ԑ��������������Ă��܂��B�Z���e������l�X�ȋ����������āC��d�ɂ��w���Ȃ������ƂȂ��Ă����܂œ͂��Ă���q�ǂ������̊����́C���̈��̓��e�܂Œ��������邱�Ƃ͂ł��܂��C���̋����́C���ɂ͍������܂��q�ǂ����������₩�ł���C�w�Z�����J�ł��邱�Ƃ̊�т̐��ł���܂��B����́C100�N�O���獡���܂ŕ������q���w�Z�ŕ�����Ă��������ł����邱�Ƃł��傤�B
�@�������q���w�Z�́C���a21�N�ɓ��g���j�E���Z���ɂ���Ē��ꂽ�u�U���̋���v�̗��O���C�����܂�60�]�N�ɂ킽���Ď��H���ĎQ��܂����B����ɐ������X�́C��l�̑n���Ă���ꂽ���̗��O�̂��Ƃł̎��H�ƌ����̓`���܂��Ȃ���C����100�N�Ɍ����ĐV���ȗ��j���\�z���Ă䂩�˂Ȃ�܂���B���j�́C�l�X�Ȋw�Z�s���C���邢�͌������\��̑傫�ȍs���ɂ���Ă̂ݍ\�z�������̂ł͂���܂���B���X�C����̋���c�ׂ̒��ɂ����C���j�͂����Ă䂭���̂ƔF�����Ă���܂��B�{���́C���������c�ׂ̐ςݏd�˂̏�ɂł��������Ă������X�̎��H�ƌ����̌����ł��B
�@�{���́C����20�N�P���̒�������R�c��\�ɂ����Ď����ꂽ�V���ȃL�[���[�h�u�K���v�u���p�v�u�T���v���C�{�Z������U���_�ƗZ���������u�T���^�w�K�v�������̒��ɐ��������̂ł��B����́C�擱�I�E�����I�Ȏ��g�݂����{���C���������𐄐i���C���̋��琭��̐��i�Ɋ�^����Ƃ���������w�@�l�����w�Z�Ƃ��Ă̖��������o�������̂ł�����܂��B�{����������{�̋��猻��ɏ����ł���^���邱�Ƃ��ł���C��ς��ꂵ�������܂��B
�@�Ȃ��C�{���̏㈲�Ɋ�����Ȃ閲������܂��B����́C�{�������݂̓��{�̋���݂̂Ȃ炸�C25�N��C50�N��̖����̓��{�̋��甭�W�Ɍ�������̓��ݐƂȂ�C�Ɗ���Ă��邱�Ƃł��B���݁C���������w�́C�����̊O���l���w����q�������������ւ����C�܂������w�Ƃ̍��ۊw�p�𗬂Ȃǂ������ɂȂ���Ă���܂����C�{����ʂ��āC���E�e�n�̋��猻��ɓ��{�̐V��������݂̍���ɂ��Ă̒m������邱�Ƃ��ł���Ȃ�C������܂��傫�Ȋ�тƂ���Ƃ���ł��B���ꂼ��̎���₻�ꂼ��̍��ɂ���āC�Љ�I�╶���I�C����V�X�e����w�Z���x�CLegal Basis of Education�i���珔�@�K�j��Course of Study�i�w�K�w���v�́j���C���̋���c�ׂ��x����g�g�݂͈قȂ��Ă���܂����C�����q�̐������肢�C���̊����ɗ�܂���Ď���̐E���ւ̊��͂Ă����p�́C���E�����ׂĂ̋����ɋ��ʂ�����̂Ɗm�M�������܂��B���͖{�Z�Z���Ƃ��āC�{���Ɍf�����e�[�}�u���Ȃ��q�ǂ�����Ă�v�́C���݂̓��{�����݂̂Ȃ炸�C����⍑�����z���āC���E�̂����鋳���ɂ����ċ��L���邱�Ƃ��ł��C�������ɂ킽���Đ[�߂Ă䂭�ɒl����e�[�}�ł���ƍl���Ă��܂��B
�@2007�N�̃��j�Z�t�̒����ɂ��C���E�Ŋw������}����12���̎q�ǂ����C�헐��n���̂��߂ɏ�������ɏA�w���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�A�t���J�̃T�n���ȓ�̒n��ł́C���̐��͕���30���ɂ܂ŒB����Ƃ����Ă��܂��B���̂��ƂɎv�����͂���Ƃ��C�q�ǂ������̌��₩�Ȋ������Ȃ���C�q�ǂ������̊w�K����p���������C���̐��ʂ��������ď㈲�ł��邱�ƂɊ��ӂ̔O������ƂƂ��ɁC��w�̌��r���d�˂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��������܂��B
�@�Ō�ɂȂ�܂����C�{���̊��s�ɂ�����C���x���Ƃ��w��������܂������������w�̏��搶���Ɩ{�Z�u�U���̉�v�̏���y�ɁC�܂��{���̔��s�����������������܂��������}���ҏW�����̔����q���C�����Ď��ǂ��̕��������w�������q���w�Z�ɍݐЂ���483���̎q�ǂ������Ɋ��ӂ̈ӂ�����܂��B
�@�ǎ҂̊F�l�̊��݂̂Ȃ������]�����肢�������܂��B
�@�@����22�N�Q���@�@�@������w�@�l���������w�������q���w�Z�Z���@�^�ѓc�@�j��
-
 �����}��
�����}��