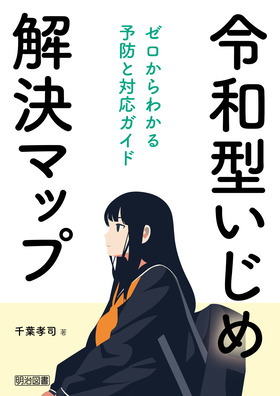- はじめに
- 序章 令和型いじめの根
- 教育の場から教育というサービスを受ける場へ
- 寛容さを失い攻撃する社会
- 他者視点の喪失
- オリンピック選手への批判から見えてくるもの
- 最適化された空間からストレスフルな閉鎖空間へ
- いじめが成立する3要素
- その子にとっての主人公でいられる教室へ
- 第1章 WANTとSTORYで対応する
- いじめはWANTから発生する
- 子どもが納得できるSTORYをつくる
- 2つのSTORY
- 第2章 令和型いじめ解決マップ
- 学級内の基本的欲求
- 崩れるいじめの4層構造
- 頻繁に入れ替わる被害者と加害者
- 被害者バージョン
- 加害者バージョン
- 第2ステージから第1ステージへの後退リスク要因
- 第3章 解決のSTORYを子どもとつくる
- 点ではなく線で考える
- 全員被害者のいじめのケース
- 3種類のゴールを考える
- 子どもたちのWANTを考える
- 選択肢を与えてSTORYをつくる
- 第4章 保護者のWANTに対応する
- 消費者としての保護者のWANT
- 子どもと一体化した保護者の例
- 保護者の感情に焦点をあてる
- 説明の手順
- 保護者の望む役回りは変えない
- 第5章 令和型いじめ対応の勘所
- 告白して断られて傷ついた,いじめだというケース
- 賢者からの質問カードで意欲的に考えさせる
- 表情カードで多角的に考えさせる
- 第6章 令和型いじめ予防の勘所
- アクセルばかりを教えてブレーキを教えない学校
- 子どものWANTにはないSOSを出す自分
- SOSを出す状況を受け入れさせる
- SOSカードの実践 助けを求める練習
- リスク回避から生まれるリスク
- ルールとマナーを使い分ける
- マナーの良いクラスというイメージを持たせる
- 自由の相互承認に基づいたルールを
- 勉強を教えたことがいじめにつながる時代
- 第7章 学級の荒れから生まれるいじめ
- 公式のルールと非公式のルール
- 公式のルール<非公式のルール状態での指導
- 人間関係のチェックポイント
- 第8章 令和の子どもたちに伝えたいこと
- 長い話を聞けない子どもたち
- いじめとは境界線の侵入
- 前にやられたから,仕返しだという子どもたちに
- 被害者にも原因があるという子どもたちに
- 多様性は認めるけれどかかわらないという子どもたちに
- 命を軽視する子どもたちに
- 第9章 令和型いじめ予防授業
- 遊んでいただけ
- これでいいの?
- 僕は悪くない!
- おわりに
はじめに
交通事故があったとします。被害者はもちろん,加害者も,自己現場の周囲で暮らす人々も,誰一人として幸せになる人はいません。そのときだけの問題ではなく,その後の人生にも暗く重い影を射すことでしょう。
これは,いじめも全く同じです。被害者も加害者もクラスの子どもたちも,保護者,教職員,地域の人も……。誰一人として幸せになることはありません。
今日も日本のどこかで,いじめ防止のために,様々な教育活動が行われています。子どもは教師の思いを受け止め,「いじめはしません」と口にします。ところが,いじめは起きます。
それは,わかることとできることは別だからです。
教師が,その子が二度といじめをすることのないように寄り添いながら,できるようになるまで導いたとします。
それでも,いじめは起きます。人は自分一人では決してやらないようなことでも,集団になるとやってしまうことがあるからです。
さらに,これまでのいじめ指導と令和の子どもたちとの相性の悪さも看過できない部分です。
教室は,交通事故多発地帯にたとえることができます。この場の地理や交通量や交通状況に精通することが,交通事故を防ぐことにつながります。
この「令和型いじめ解決マップ」が,教室のトラブル防止につながればと願っています。
2025年3月 /千葉 孝司
-
 明治図書
明治図書