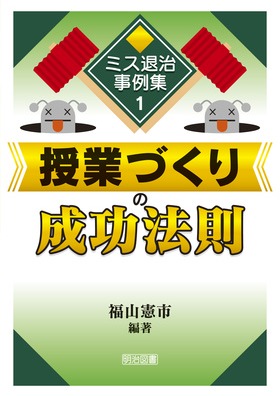- はじめに
- 子どもが変わる こんなミスを減らそう成功への道 36
- 1 誕生日チェックミス退治
- 2 朝の子どもの様子をチェック
- 3 机をそろえるときの目印
- 4 起立,着席の段階的指導
- 5 視覚に訴え,忘れ物を減らす方法
- 6 朝に忘れ物を言いに来る
- 7 ものを用意して,子どもの学習を保障する
- 8 通せんぼテスト
- 9 特別支援学級との交流学習での困った場面
- 10 長期休業中の課題処理《一人勉強コンテスト》
- 11 百人一首・余韻・聞く力
- 12 ふわふわ言葉とチクチク言葉
- 13 友達からのうれしい言葉
- 14 ことわざで《ハンカチ》指導
- 15 トイレのスリッパがそろうきっかけの詩
- 16 給食エプロンの持ち帰りミス退治
- 17 給食の配膳スピードが変わる
- 18 楽しい会食にしよう
- 19 くつ箱のくつがビシッとそろう
- 20 画像提示で,きちんとくつがそろう
- 21 1年生にも響く上ぐつ指導
- 22 集会で上ぐつがバラバラにならない方法
- 23 全員に《落とし物》を確認させる
- 24 片付けの悪い子も大変身
- 25 机の中に《引き出し》づくり
- 26 《机の中が大混乱》をなくす3点チェック
- 27 席替えの後のミス退治
- 28 お昼休みのドッジボールのミス退治
- 29 砂いじりしている子どもたちへの対応
- 30 空白の時間のないプログラムづくり
- 31 帰りの会に《当番タイム》
- 32 衣替えの日に《心がえ》をさせないミス退治
- 33 意外にできない《1日5善》
- 34 式に臨む心構えをつくる話
- 35 目標に向かって絆を深める
- 36 くつをそろえる,あと数人
- 教師が変わる こんなミスを減らそう成功への道 48
- 1 教師修業のための「かきくけこ」
- 2 新学期前の《書き出し》
- 3 医療ミスから学ぶ確認ミス
- 4 楽しみながらみんなに顔を覚えてもらおう大作戦!!
- 5 間違えたことを受け入れる
- 6 人の話を聞くこと
- 7 教師は《隙間の時間》を意識せよ
- 8 いきなりジャンケン
- 9 スキンシップを保障する
- 10 教室の心的温度を上げる
- 11 みんなのための《しあわせカウンター》
- 12 クラスキャラクターを活用して伝える
- 13 有名人のイラストでコメントをしよう
- 14 掃除を意欲的にさせる言葉かけ
- 15 見える仕事分担表で,てきぱき楽しい掃除
- 16 デジタルカメラ写真でお手本づくり
- 17 見通しを持てる日課は《取っちゃえ時間割》
- 18 簡単な1日のスケジュールを示す
- 19 子どもの日記から《自分のミス》を反省する
- 20 子どもたち全員と1日1回話していますか
- 21 放課後の地道な記録
- 22 定期的に《再点検》しないミス
- 23 教師の《言葉》の落とし穴
- 24 「また後で」を言ってはダメ
- 25 「もう一声」を忘れずに
- 26 「ちゃんと」「きちんと」「しっかりと」って?
- 27 どこに何があるかを伝えないミス退治
- 28 教師の机まわりが汚いミス退治
- 29 プリント配布時の誤字修正
- 30 テスト返却のミス退治
- 31 書字が苦手な子どもへのNG
- 32 子どもたちのけがを減らす方法
- 33 子どものけがに対する心構え
- 34 机間指導で《全体》を見る
- 35 職員室の座席決め
- 36 プロジェクターを黒板に映そう
- 37 《学級お助け隊》を組織しよう
- 38 学級文庫に漫画をセット
- 39 子どもたちが自ら動く学級システムづくりをせよ
- 40 飾りにしない目標づくり
- 41 通学路を歩く
- 42 二次障害につなげないために①
- 43 二次障害につなげないために②
- 44 人間が学習するときの3つのタイプを意識せよ
- 45 いじめを出さないためには
- 46 ミス退治の応用技術《市販問題集》を分析する
- 47 叱り方・ほめ方の鉄則事項
- 48 花心・根心・草心そして素心
- おわりに
はじめに
人は誰でも《ミス》をする。《ミス》をしない人はいない。
学校現場では,毎日《ミス》の連続だ。
子どもたちが《忘れ物》をする。これも《ミス》の一つだ。
《給食エプロンを袋にきちんと入れない》これもまた《ミス》だ。
《トイレのスリッパが,ぐちゃぐちゃ》……これなんて,どこの学校でもある《ミス》かもしれない。
教師だって,たくさんの《ミス》をする。
教室に持っていく道具を忘れてしまった。
黒板に書く漢字の書き順を間違えた。
子どものけがの様子を保護者に伝えるのを忘れていた。などなど,書けばきりがないくらい《ミス》がある。
これらの《ミス》をそのままにしておいてはいけない。
ミスを共有する必要がある。
ミスを共有し合えば,可能な限り《ミスを少なくする》ことができる。
ミスが少なくなれば,授業づくり・学級づくりがうまくいく。成功へ道が開けるのである。
ところで,ミスを共有するためには,ミスを出し合う仲間集団が必要だ。
「今日,こんなミスをしてしまいました。」
「今日,こんな方法でミスを減らすことができました。」
「この時に気をつけるミスは何ですか?」
そんな報告・質問をし合う場がいる。
そこで誕生したのが《ミス退治部会》である。
有田和正先生の実践を世に広めようという有田ネット(古川光弘先生主宰)の一つとして生まれた。現在,会員110名の部会である。
本著は,ミス退治部会の仲間たちが,今までの教師生活の中から《授業づくり》のためのミス退治事例を出し合ったものである。
こんなミスがあった時,どうすればいいかのヒントになれば幸せである。
2010年1月(箱根駅伝を見ながら) ミス退治部会主宰 /福山 憲市
-
 明治図書
明治図書