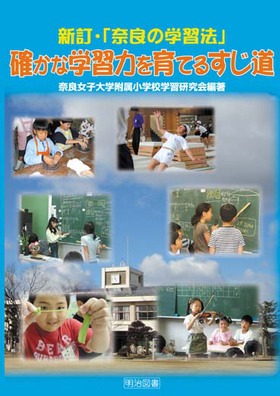- 刊行にあたって
- 本校の教育
- 第1章 「学習力が育つすじ道」改訂の経過
- 第1節 「各種能力指導系統表」の改訂とその経緯
- 第2節 改編のねらいと共通理解したこと
- ○新「各種能力の指導系統表」作成にあたって――改訂への共通理解に向けて――
- ■コラム■子ども記 伸びたい子どもたち
- 第2章 確かな学びの創出に向けた実践
- 第1節 「学習力の基盤」の育ち
- ○「学習力の基盤」とそのすじ道
- ○「学習力の基盤」が育つワンポイント
- ■コラム■教師の日記 休み時間の音楽室
- 第2節 「なかよし」学習の育ち
- ○子どもが創る「低学年なかよし集会」
- ○「グループなかよし」で育つ子ども
- ◆「なかよし」のすじ道
- ■コラム■教師の日記 教えない体育のめざすものは
- 第3節 「けいこ」学習の育ち
- ○物語を読もう「大造じいさんとガン」――(5年) 椋 鳩十 作――
- ○自らのよさに気づき伸びる子ども――「スーホの白い馬」(2年)――
- ◆言語的生活領域のすじ道
- ○社会的な見方や考え方が育つ,5年生の「エネルギー・環境」学習
- ○社会的生活領域の学習に必要な資料を読解する力が育つ
- ◆社会的生活領域のすじ道
- ○自分たちで進める「教科書算数」の学習
- ○学習力を育てる算数的学習法
- ◆数理的生活領域のすじ道
- ○理科における独自一相互一独自学習の発展的連続性について――「身近な酸アルカリを調べる」(6年)の実践から――
- ○個の観察記録をつなげて昆虫の生活を追究する理科学習(3年生)
- ◆理科的生活領域のすじ道
- ○音楽を身体で感じよう
- ◆音楽的生活領域のすじ道
- ○子どもが自分の力で切り拓く造形学習
- ◆造形的生活領域のすじ道
- ○生活の中に気づく力を育てる「食べものたんけん」(「めんの旅」3年)
- ○自らの生活をみつめる食の学習――けいこ(家庭)との連携――
- ◆家庭生活的領域のすじ道
- ○一人ひとりの子どもが生きる自律的な体育学習
- ○複合的な学習環境の中で自己の課題を追究する体育学習
- ○子どもの生活に結びつく保健学習
- ◆体育的生活領域のすじ道
- ■コラム■子ども記 数量感覚の必要性は子どもの生活の中から
- ■ホームページで自分の研究をまとめよう■
- 第3章 「しごと」学習の理論と展開
- ○奈良の学習法における「しごと」学習
- ○「しごと」学習の具体的展開
- 「学習力が育つすじ道」の研究に寄せて――育つこと・育てること―― /嶋野 道弘(文教大学)
- 読者の方々に――この本の3つの魅力―― /森脇 健夫(三重大学)
- 「学習力が育つすじ道」は教育の極楽浄土へと至る正道 /奈須 正裕(上智大学)
- あとがき──「学習法の革新」──
- 『学習研究』誌 購読のおすすめ
刊行にあたって
1990年代半ばから急速に進展したIT革命は,従来の工業社会を知能社会へと移行させる世界的変化を生じさせている。すなわち,筋肉労働から頭脳労働へ,あるいは重化学工業からソフトウエア産業へという過去に例のない移行が行われている。また,IT革命はグローバル化をも促した。グローバル化の世界では,国境を容易に越える強大な資本や超国家企業が最大の勝者になり,敗者は容易に国境を越えることができない先進国の国内企業や中流階級になると言われている。日本では,賃金は抑制され,「一億総中流意識」の崩壊と格差拡大の時代が到来すると言われている。
このような世界と日本の変化に伴い,それに適合させる教育が必要になる。日本の教育は,工業社会型教育から知能社会型教育へと,適切な先見性をもって移行できるであろうか。過去の大転換期の例をみても,紆余曲折を経て移行しているのが普通であり,容易に達成できないであろうとみるのが自然である。
しかし「奈良の学習法」は,大正時代から始まり,昭和に入り,第二次世界大戦の敗戦を経て,平成の今日に至っているも,その本質は変わりなく,高い評価を得ている。戦前・戦後の大転換期にも変わらぬその本質とは何であろうか。それは,児童が自ら学ぶことにあり,その教育システムを完璧に近いかたちで構築したからであろう。換言すれば,「奈良の学習法」は教育の普遍性を具現化した教育システムの代表的一例とみることができる。明日がどのようなかたちで変化するかが不明・不確実な時代には,先見性よりも普遍性がより必要とされる。したがって,時代は「奈良の学習法」を必要としているに違いない。
本校は国立大学法人奈良女子大学附属小学校という極めて恵まれた組織である。だからといって,「奈良の学習法」を簡単に構築でき,それを継承発展できたわけではない。初期の「奈良の学習法」の構築に際しては木下竹次他の教職員の偉大な功績が特に輝いて見えるが,発展継承できたのはその後の教職員の並々ならぬ努力と研鑽の賜物である。
この度上梓できた,「新訂・『奈良の学習法』確かな学習力を育てるすじ道」は,その成果の1つである。これが大変革期の日本の小学校教育やそれに携わる皆様方に少しでもお役に立つことができればと願っている。本書を読まれる皆様方の忌憚のないご意見やご批正を賜れば幸甚である。
奈良女子大学附属小学校 校長 /諸岡 英雄
-
 明治図書
明治図書