- 序章 「書く人」は「読む人」よりも偉い
- ―国語教師はなぜ「書く人」になろうとしないのか―
- 1 朗読の手本は見せるが、文章の手本は見せない教師
- 2 「読む人」であることに満足する教師
- 3 他の「書く」教師を冷笑する教師
- 4 私の言うとおりにすれば、必ず「書く人」になれる?
- 第1章 他人の褌で相撲をとる(その1)
- 1 情報としての「書き方」
- 2 「力」を「量」に還元する
- 3 書き方を借用する
- 4 文体はすべて借用の結果である
- 第2章 他人の褌で相撲をとる(その2)
- 1 言葉の捜し方を借用する
- 2 言葉の「メンクイ」
- 3 言葉は思考に先行する
- 4 模倣における個性と主体性
- 5 優れた箇所だけを模倣することは可能か
- [休憩時間1] 嘘を読む愉しみ
- 1 作文に嘘を書いてはいけない?
- 2 再び、嘘の話
- 3 多分、嘘の話
- 4 ついでに、本当のことも読む愉しみ
- 第3章 思考の転用(その1)
- ―本を読んで賢くなるとはどういうことか―
- 1 「考え方」を収集する
- 2 収集の一例―われわれの日常でもっとも頻繁に現れる議論のタイプ―
- 3 その転用
- 4 補一・定義からの議論
- 5 補二・類似からの議論
- 6 補三・譬えによる議論
- 7 補四・比較による議論
- 8 補五・因果関係からの議論
- 第4章 思考の転用(その2)
- ―反論法の収集と蓄積―
- 1 再び類似からの議論について
- 2 類似からの議論に反論するには
- 3 二項間の差異の指摘
- 4 練習問題一―山羊や羊と友人―
- 5 練習問題二―陶器と書物―
- 6 練習問題三―ピアノと文章―
- [休憩時間2] 揚げ足を取る愉しみ
- 1 足を揚げる方が悪い
- 2 揚げ足取りの実例
- 3 「揚げ足取り」を読む
- 4 揚げ足取りに磨きをかける
- 第5章 思考の転用(その3)
- ―思考の束への組み込み―
- 1 考え方一―それが書かれたことの意味―
- 2 考え方二―それが劇になったことの意味―
- 3 考え方三―それが説明されたことの意味―
- 4 転用―それが出版されたことの意味―
- 5 補・収集例から―矛盾する評価を切り口とする方法―
- 第6章 思考の転用(その4)
- ―弁証法の応用―
- 1 考え方―無条件的な忠誠の効用―
- 2 転用一―教科書しか教えないことの効用―
- 3 転用二―立場を変えられないことの効用―
- [休憩時間3] 屁理屈を読む愉しみ
- 1 屁のような屁理屈
- 2 中級―スメルジャコフの屁理屈―
- 3 上級―ショーペンハウエルの屁理屈―
- 第7章 思考の転用(その5)
- ―本を読めば読書も否定できる―
- 1 読書でなければならない理由はない
- 2 「文学」ゆえに貴からず
- 3 補・読書をすると思考力が鈍る
- あとがきにかえて―地獄での揚げ足取り―
序 章 「書く人」は「読む人」よりも偉い―国語教師はなぜ「書く人」になろうとしないのか―(冒頭)
1 朗読の手本は見せるが、文章の手本は見せない教師
章題がやや俗なので、少しはアカデミックな香りのする話題から始めたい。まず取り上げるのは、著者も書名も不明な一冊の古い書物である。これは現存するラテン語最古のレトリックの教科書で、献呈された相手の名前だけがかろうじてわかっていることから、『ヘレンニウスに宛てた修辞学』(前八五年頃)と呼ばれてきた(1)。学術的には、この『ヘレンニウスに宛てた修辞学』(以下、『ヘレンニウス』と略す)は、ほとんどヘレニズムのレトリックの引き写しで、独創性に欠け、「レトリックの理論には何ら貢献しなかった(2)」と評価されている程度の代物にすぎない。が、この何の取り柄もない教科書が、その中の、ある時代錯誤的な主張によって、本章の枕を見事に務めてくれるのだ。
レトリック教育の初期の頃、ソフィスト(σοφιστη.V、ソピステース)と呼ばれたレトリックの教師たちは、自分の弁論をモデルとして生徒に与え、それを視写と暗唱によって正確に真似させ、再生させるという方法をとっていた。これは、彼らの生活スタイルからすれば、ある意味でやむをえない方法であった。学校を固定したイソクラテス(前四三六-三三八)を例外として、ギリシャ各地を転々としながら、「集中講義」によって教育を行っていた彼らには、書記資料による補助もままならない当時としては、自分の弁論をそっくりに模倣させるということ以外に有効な教育上の手立てがなかったのである。
しかし、ヘレニズム時代に入って、当然のことながら、レトリックの教師(修辞学者)たちの方針は一変した。レトリックの理論は独自のものを出すにしても、それを説明するための例文(すなわち模倣のモデル)は、著名な弁論家や詩人のものを利用するようになってきたのである。これは、教育方法としては、常識的で妥当な線に落ち着いたと言えるであろう。が、『ヘレンニウス』の著者は、これに真っ向から反対する。模倣のためのモデルは、やはり自分の(直接の)教師とすべきであると言うのだ。彼は、『ヘレンニウス』第四巻の序文で、なぜ教師が模倣のためのモデルを提供しなければならないかを長々と説明した後、次のような大見得を切る。
もし、紫衣(purpura)か、あるいは何か他の商品を売っている商人がこう言ったとしたらどうだろう。「私の品物を買ってください。もっとも、今あなたに見せているこの見本は、他の人から借りてきたものですが。」……レトリックの教師たちは、自分が授けようと申し出たまさにそのものを借用しようとするのは馬鹿げた行為だと思わないのだろうか(3)。
大変な鼻息であるが、夫子自身はどうなのか。『ヘレンニウス』の注釈者であるハリー・キャプランによれば、この著者は、(そうとわからないように形を大幅に変えて)他の作家から無数の例文の引用をしているという(4)。この「言行不一致」について厳しく追及はすまい。彼は、ここで、レトリックの教師としての理想を語ったのである。そして、理想というものの本質として、それは容易に現実化できなかったというだけだ。問題は、『ヘレンニウス』の著者はそうした理想を抱いたが、彼の同時代人は、そしてもちろん現代の作文教師は、もはやそんなことは考えもしないということである。














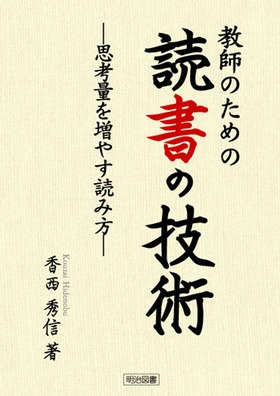


明治図書発行の絶版書もすべて読みたい、と思っています。