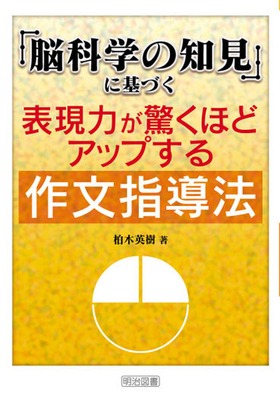- まえがき
- 主な脳科学用語の説明
- Ⅰ 「脳科学の知見」を作文の授業に生かす
- 1 作文は「記憶」「長期記憶」を生かして書くもの
- 2 「脳科学の知見」を作文に生かすとは?
- 3 「脳科学の知見」をこう作文に生かす
- (1) 物まね細胞「ミラーニューロン(ミラーシステム)」はこう生かす
- (2) 短期記憶(作業記憶=ワーキングメモリー)の知見は、こう生かす
- (3) 「長期記憶の知見」はこう生かす
- (4) 「間を開けて四回の原則」はこう生かす
- (5) 「脳内神経伝達物質」を分泌させることで作文指導に生かす
- (6) 「おおざっぱな脳」の性質はこう生かす
- (7) 「入出力のループ」はこう生かす
- (8) 「無意識なこと」に対して、「やる気」を起こさせるにはこうする
- (9) 授業の中で印象づけて記憶に残すにはこうする
- Ⅱ 「脳科学の知見」を生かした誰もが驚くほど書けるようになる作文指導法
- 1 「良い作文とは、一つのことに絞って書いた作文だと分かる」作文の授業(三年生以上適用可・モデル文にルビを打てば二年生でも適用可)
- 2 「短い間のことが長く書けるようになる」作文の授業(全学年適用可)
- 3 「『はてな』がどんどん書けるようになる」作文の授業(二年生以上可)
- (1) 「はてな作文」の導入授業はこうする
- (2) 「はてな作文」の変身(「はてな作文」+「調べ作文」)
- (3) 「はてな作文」さらなる変身
- (4) 「はてな作文」+「引用文の書き方」を教える
- (5) 「二つの辞典」で言葉は引け!
- 4 「書き出しがガラッと変わる『書き出し』」の授業
- 5 「描写力が一気に激変する」作文の授業(「会話+様子」文の授業)
- (1) 一会話様子文の授業
- (2) 二会話様子文の授業
- (3) 「会話連続型」の指導ポイント
- (4) 「三会話様子文」の授業
- 6 「段落の書き方が一変する段落の書き方」の授業
- 7 比喩が書けるようになる「比喩の作文」の授業(含む。隠喩、擬人法)
- 8 対比で変わる「体言止め作文」の授業
- Ⅲ 表現力が驚くほどアップする「思考の流れ」で書く作文の授業・詩の授業
- 1 作文二つのレベル
- 2 作文レベル二の授業~ポイント作文の授業(三年生後半可、四年生以上)
- 3 レベル三の作文授業(分析日記)(五年以上可)
- 4 基本型による誰でも書ける詩の指導法。(平野いく氏の修正追試─三年生以上可)
- (1) お母さんの詩(詩の導入)
- (2) お父さんの詩
- (3) その他の家族の詩
- Ⅳ 書けない子が書けるようになる誰にも教えたくない秘技
- 日記・作文の書けない子が変わる、誰にも教えたくない秘技
- (1) 「何を書いているのか、文が全く読みにくい子・促音が書けない子」へのとっておきの方法
- (2) 句点・読点が正しく打てない子へのとっておきの方法
- (3) 「読点ゼロ」の子が読める作文に変わるとっておきの方法
- (4) 日記・作文に漢字が使えない子が一気に漢字を使うようになるとっておきの方法(秘技)
- (5) 「だらだら文からスッキリ文に直す」とっておきの方法
- あとがき
- 引用文献・参考文献
まえがき
日記・作文指導に、教師二年目から毎年、コツコツ取り組んできた。
三〇年以上指導して、ようやく、
子どもの表現力が驚くほどアップする「劇的な指導法」が生まれてきた。
それを端的に言うと、次のことが満たされることであった。
前提 毎日のように日記を書いていること。
指導一 「脳科学の知見」に基づく「モデル」等を利用した授業を行うこと。
指導二 授業後は、「日記指導」で、その定着を図ること。
本著は、この三点を「脳科学の知見」に基づき、具体的に書いたものである。
毎年四月。子どもたちの「作文表現力」の実態に愕然としてきた。それは、低・高を問わない。
実態一 一つのことが書けない。
例えば、遊びのことを書いたと思ったら、買い物のことを書いている。中には、朝から晩までのことを書いている。
実態二 一つのことが詳しく書けない。
(例)「芳雄君とサッカーをした。楽しかった」等と一・二行でサッカーの内容を書き、サッカーの様子が詳しく書けない。
実態三 読み手を引きつける文が書けない。(これは、書き出し方を知らないからである)
(例)「今日は」「僕は」などと決まり切った書き出しをしている。
実態四 一文を長く書いて何を書いているか分からない。
(例)「一樹君と会って、話をして、それから、お菓子を食べて、ゲームを一樹君の部屋でしたので、とてもよかった」
この例文のように、「だらだら文」で書き、一文が短く書けない。
実態五 体言止め(名詞止め)、リフレーン等の「レトリック」を使った文章が書けない。
この他、「平仮名ばかりの文になっている」「原稿用紙が正しく使えない」等々と「できないづくしで」ある。
なぜこれほどまで「作文表現力」が劣るのか。私は、最大の理由はこうだと考えるに至った。
教師が作文の書き方の指導法を知らないために、指導していないか、指導をしても、確かな指導をしていないからである。
別の言い方をすれば、一部の教師を除いて、「作文の教え方を知らないからである」と。
本著は、これらの実態を克服すべく、「誰もが達意の文が書けるようになる作文指導の秘訣」を紹介したものでもある。
読者諸氏に少しでも役立てば、望外の喜びである。
二〇〇六年二月 /柏木 英樹
-
 明治図書
明治図書