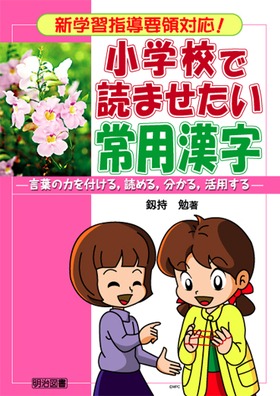- はじめに
- 第1章 小学校で読ませたい常用漢字
- [1] なぜ,常用漢字を読ませるのか
- [2] 言葉の力を付けるということ
- ○読めるようにしたい熟語
- [3] 読める,分かる,活用するの意味
- [4] 常用漢字939字をどう理解するか
- ○学年別漢字配当表以外の常用漢字939字
- [5] 小学校で常用漢字を読むための優先順位の考え方
- 第2章 小学校で読ませたい常用漢字の実際
- [1] 学年別配当漢字と常用漢字との熟語づくりの基本的な考え方
- (1) 振り仮名付きで学ぶ漢字を意識する
- ○振り仮名付き熟語の一覧表
- (2) 日常生活に合わせて分類することで理解する
- ○学校生活・教科・家庭生活
- (3) 地名や都市名などの生活との一体化で理解する
- ○名称・地方名・県名・都市名
- [2] 常用漢字939字を使用して小学校で活用できる熟語
- ○常用漢字の熟語づくり
- [3] 常用漢字相互の熟語
- ○常用漢字相互の熟語の使い方等
- [4] 日常生活の中で常用漢字を読むこと
- 【付録:1】常用漢字の熟語づくり
- 【付録:2】小学校学習指導要領 国語
はじめに
新学習指導要領が告示され,小学校国語においては,児童の言語の力の一層の定着度が求められている。その中で漢字の指導については,必要に応じて振り仮名を付けるなど,児童の学習負担に配慮することを視野に入れて,早い段階から児童に読む機会を多くもたせ,語句の力を身に付ける必要性が示されている。また,日常生活において児童の目に触れることの多い常用漢字についても,確実に読めること,分かること,活用できることを重視した指導の充実の重要性が指摘されている。
小学校の第5学年での社会科で学ぶ都道府県の位置と名称などについては,「新潟」の「潟」,「滋賀」の「滋」,「佐賀」の「佐」などは常用漢字としてあるが,児童は読めるだけでなく,活用が図れる必要性がある。また,日頃,学校生活の中で活用している語句に関しても配慮したい。「鉛筆」の「鉛」,「文房具」の「房」,「原稿用紙」の「稿」などの必需品や,「距離」の「距」,「鑑賞」の「鑑」,「芋掘り」の「芋」など,学校行事などでも活用している語句などでは,熟語が読めるようになって当然なのである。
そのためには,常用漢字をどのように読めるようにするのか,優先順位をどのように考えて実践していけばよいか,学校生活・家庭生活,そして県名・都市名など,活用されている常用漢字を日常生活の中で使えることを重視し,身に付くようにしなければならない。
本書では,児童が読書,新聞,広告等でも目にすることが多い学年別漢字配当表以外の常用漢字939字についても,小学生が確実に習得すべき語句を分析して教師が教室の中に持ち込むことで,語句の力を身に付けていくことを明確にしている。常用漢字について,小学校で少しでも活用が図れるようなレベルまで高めて,中学校で一層の定着が図れるように,言語の力を育成するために役立てていただきたい。
平成20年6月 著者 /釼持 勉
-
 明治図書
明治図書