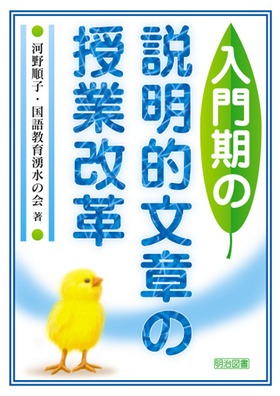- 序 /中洌 正堯
- はじめに /河野 順子
- 理論編
- 一 入門期の説明的文章の授業改革の視点
- (1) なぜ説明的文章教材を学ぶのか
- (2) 説明的文章教材の学びを成立させる学習者論
- (3) 説明的文章教材の学びを成立させる教材論
- (4) 説明的文章教材の学びを成立させる目標論
- (5) 入門期の説明的文章指導の現状
- ① 学習者観
- ② 目標観
- ③ 方法
- (6) 入門期の説明的文章の授業改革の視点
- 二 入門期の説明的文章教材の学習指導の臨床的研究から明らかになった子どもの「世界・論理を捉える技能」の形成の実
- (1) 「〈対話〉による構成活動」の年間計画
- (2) 「〈対話〉による構成活動」の実際1 「とりと なかよし」
- ① 子どもの視点からの「とりと なかよし」の教材研究
- ② 「世界・論理を捉える技能」が形成されるための授業デザイン
- ③ 直子の「世界・論理を捉える技能」の形成の実際
- (3) 「〈対話〉による構成活動」の実際2 「どうぶつの 赤ちゃん」
- ① 子どもの視点からの「どうぶつの 赤ちゃん」の教材研究
- ② 「世界・論理を捉える技能」が形成されるための授業デザイン
- ③ 久実の「世界・論理を捉える技能」の形成の実際
- (4) 足場づくりとしての教師の役割に着目した子どもの「論理・構造を捉える技能」の形成―「じどう車くらべ」
- ① 「じどう車くらべ」で育てる「世界・論理を捉える技能」
- ② 導入における既有知識の掘り起こしのデザイン
- ――身近な「もの」と比べる――
- ③ 「仕事」と「作り」を捉える技能を育成するための第二時・第三時の授業デザイン
- ④ 子どもの側から「仕事」と「作り」を捉える技能を形成するための第四時の授業デザイン
- ⑤ 身体的、実感的な「世界・論理を捉える技能」を形成するための授業デザイン
- ⑥ 子どもの側から「世界・論理を捉える技能」を形成するための教師の役割
- 実践編
- 一 「いろいろな くちばし」
- 1 「いろいろな くちばし」の教材研究
- 2 授業提案 子どもの思考を大切に授業をデザインするということ
- 3 アイディア編1 子どもたちが実感しながら読み取るためのアイディア
- ――比較しながら読む活動を通して――
- 4 アイディア編2 筆者の工夫に気付く
- ――読み手を意識した述べ方の工夫――
- 5 行為を通して、子どもの側からの「世界・論理を捉える技能」形成を目指した授業
- 二 「じどう車くらべ」
- 1 「じどう車くらべ」の教材研究と先行実践
- 2 授業提案 ものの見方を広げる説明的文章の授業の工夫
- ――筆者との対話を通して――
- 3 アイディア編1 身近なものを写真で見て比べてみよう
- 4 アイディア編2 推論しながら「仕事」と「作り」を関係づける
- 5 「筆者との対話クイズ」を中核とした「世界・論理を捉える技能」形成を目指した授業
- 三 「どうぶつの 赤ちゃん」
- 1 「どうぶつの 赤ちゃん」の教材研究と先行実践
- 2 授業提案1 対話を核に実感しながら読み深め、空白の部分を綴る
- ――入門期・最後の説明文「どうぶつの 赤ちゃん」の実践――
- 3 授業提案2 自分史を手がかりに『比べて』読み取る説明的文章の授業
- ――対話型読解の授業をめざして――
- 4 アイディア編1 学習者の共通体験を創出するメディアの活用
- ――写真を使って体験の差をうめる「どうぶつの 赤ちゃん」の導入――
- 5 アイディア編2 写真から情報を読み取る力を育てる導入の工夫
- 6 アイディア編3 自分の見方・考え方や思いを本文に結びつけて読んでいく工夫
- 7 自己、筆者、友だちや先生との対話を中核にした「世界・論理を捉える技能」形成を目指した授業
- おわりに
序
「入門期の説明的文章の授業改革」について、ここに、気鋭の研究会による清新な提案がなされたことを喜ぶ。
説明的文章の授業を、小学校から高等学校までの長いスパンで捉えると、「入門期」は、小学校一年全体と考えてよいであろう。小学校一年の前には幼児期があり、つづいて低学年、その後の中学年へと展開する。河野順子氏らの「入門期」の実践と理論は、幼児の「思考や情動、行為の客観化、標準化」に関する認知心理学の知見をふまえ、メタ認知が本格化していく中学年を見すえた学びの基礎・基本の構築を目ざすものである。
「なぜ、説明的文章教材を学ぶのか」について、河野順子氏は従来から「子どもたちが自ら生きている世界との関わりを通して、自分はどう世界と関わっていくのかという自分なりの見方、考え方、述べ方をもって生き抜いていける子どもに育ってほしいと願」い、今も説明的文章にその高い可能性を見いだしている。
ここに言う「世界」を、本書では、「自然、人間、生活、社会、歴史、宇宙などの現実を指す」としている。説明的文章のテキストは、その筆者が世界に対する自身の見方、考え方、述べ方を展開したものである。そこには、学びの対象とすべき「世界・論理に関する概念的知識」と「世界・論理を捉える技能」とがある。「世界・論理」となっているが、「世界」、「論理」(「表現・論理・構造」とするばあいもある)それぞれである。本書では、「知識」「技能」をくだいて次のように述べている。
知識―ある見方・考え方(認識)で世界を切り取ったときの内容とその方法についての知識
技能―どのような見方・考え方で世界を切り取り、それをいかに効果的に表現していくかということに関する技能
この知識と技能の形成は、子どもたちにとって、生活に生きて働く力、社会を生き抜いていく言葉の力となるものでなくてはならない。PISA型読解力が提起し、私たちが心すべきいちばんの問題はここにある。河野順子氏の求めた授業は、PISAに先行するものであったが、実践・研究の仲間を得、時宜を得て、改めて「授業改革」を提案するものである。
子どもたちは、
1 説明的文章との出会いを通して、
2 既有知識、既有経験を想起し、
3 テキストをめぐる他者(教師・子どもたち等)との〈対話〉活動によって、
4 テキストの「知識」「技能」とともに既有知識、既有経験を再構成していく。
この1~4の授業はそれぞれにデザインされ、2と3、3と4は順序不同に繰り返される。そのデザインと授業過程のあざやかな事例は、理論編にも実践編にも数々紹介されている。
かつて「生活に落とす」(芦田恵之助)とか、「生活経験・既習事項の想起」(石山脩平)などの実践や提言もあったが、授業の重要事項としてデザインされ、「再構成」に及ぶ徹底した位置づけはなされてこなかった。河野順子氏には、「子どもの内面や揺らぎや葛藤を生じさせるような学習指導」という観点がある。子どもたちの既有知識や既有経験とテキストの世界・論理のずれこそが、「知識」「技能」形成の重要な切り込み口となると考えているからであろう。その学習指導上の基本的な方法として採用されたのが、「表象化活動を取り入れた〈対話〉による構成活動」である。
「表象化活動」は、テキストの「知識」「技能」を身体的、実感的に立ち上がらせる活動であり、「構成活動」は、既有知識を用いて、主体的に情報を選択、変換、結合、補充、統合したり、既有知識を修正したりする活動(認知心理学の知見)である。
河野順子氏の実践に基づく理論と呼応し、先の1~4のデザインと授業過程を整理し、実践の体系に向かいつつあるのが、橋本須美子氏のそれである。実践から積み上げられる知見にも注目したい。
兵庫教育大学名誉教授 /中洌 正堯
-
 明治図書
明治図書