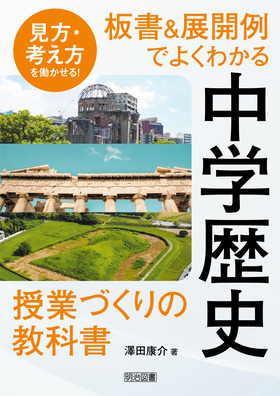- はじめに
- 1章 見方・考え方を働かせる!中学歴史授業デザイン
- 1 見方・考え方を働かせて探究的な学びを実現
- 2 板書構成について
- 3 本書の読み方
- 2章 見方・考え方を働かせる!中学歴史授業づくりの教科書 板書&展開プラン
- 1 【人類の出現と文明】
- 1 サル・ヒト…どっち?
- 2 文明が起こったのはどんな場所?
- 3 7000体の兵馬俑が出てきた!
- 2 【日本の成り立ち】
- 1 どっちが縄文人?!どっちが弥生人?!
- 2 ひどい争いの時代をおさめた女王
- 3 古墳をつくったのは何のため?
- 3 【律令国家の形成】
- 1 紙幣と聖徳太子
- 2 日本と海外で似た作品が?!
- 3 絵巻の事件は一体?!
- 4 【貴族社会の発展】
- 1 奈良時代にチーズ?
- 2 東大寺の大仏と中国の大仏
- 3 平安時代は無事で穏やか?
- 4 貴族も辛いよ
- 5 【武家政治の始まり】
- 1 武士になったのは誰?
- 2 『耳なし芳一』から見える平清盛の政治
- 3 頼朝が鎌倉を選んだ理由
- 4 140年続いた鎌倉幕府
- 5 浄土真宗が広まったのはどうして?
- 6 【武家政治の変化】
- 1 元が日本にやってきた!
- 2 武士を味方につけたのは誰?
- 3 『一寸法師』と下剋上
- 4 金閣のよさと銀閣のよさ
- 7 【結び付く世界】
- 1 どうしてこんなにキリスト教信者が増えたの?
- 2 南蛮貿易と日本地図
- 8 【天下統一への動き】
- 1 信長は良い人?悪い人?
- 2 秀吉は良い人?悪い人?
- 3 桃山文化とわび・さび
- 9 【幕藩体制の確立と江戸幕府のしくみ】
- 1 江戸時代は平和?
- 2 鎖国中なのに貿易?!
- 3 田沼意次だけ仲間外れ?!①
- 4 田沼意次だけ仲間外れ?!②
- 5 どうやってゴッホは浮世絵を知ったの?
- 10 【近代世界の確立】
- 1 絶対王政を行っていた国王に何があったの?!
- 2 これぞ革命?!
- 3 産業革命と児童労働
- 11 【幕藩政治の終わり】
- 1 ペリーは何しに日本へ?
- 2 倒幕の動き
- 3 大変な世の中なのに,「ええじゃないか」?!
- 12 【新政府と明治維新】
- 1 人々は徴兵令に進んで参加したの?
- 2 明治天皇が大変身?!
- 3 福沢諭吉が一万円札に選ばれた理由とは?!
- 4 「演歌」と政治
- 13 【揺れ動く東アジアと2つの戦争】
- 1 不平等条約の改正の行方
- 2 「日清」戦争なのに「朝鮮」?
- 3 義和団事件と出兵数
- 4 怒りを生んだ日露戦争
- 14 【近代産業と明治時代の文化】
- 1 産業革命の「光」
- 2 産業革命の「かげ」
- 3 外国人が描いたもの?日本人が描いたもの?
- 15 【第一次世界大戦と世界の動き】
- 1 第一次世界大戦は「天の助け」?
- 2 連合国側なのにデモが起きたのはどうして?
- 3 お金の価値ってこんなに下がるの?!
- 16 【大正デモクラシーと文化の大衆化】
- 1 米騒動と国民の怒り
- 2 明治?大正?どっちでSHOW!
- 17 【世界恐慌と繰り返す戦争】
- 1 世界恐慌で様子が一変?!
- 2 植民地の少ない国は世界恐慌をどうやって乗り越えた?!
- 3 日本の進む道は?
- 18 【第二次世界大戦と日本のゆくえ】
- 1 パリでヒトラーが写真撮影?
- 2 太平洋戦争のはじまり
- 3 第二次世界大戦中に生きた人々
- 4 第二次世界大戦の終結
- 19 【「新しい日本」へ再出発】
- 1 名前ランキングからみえる国民の願い
- 2 Go Home Quickly?
- 3 朝鮮戦争と警察予備隊
- 4 独立回復!国民の意見は?
- 20 【日本の復興と新たな課題】
- 1 国家予算の3分の1をかけたオリンピック
- 2 チキンラーメンと高度経済成長
- おわりに
- 参考文献一覧
はじめに
社会の変化はめまぐるしく,生成AIの登場により教育のあり方も大きく変わろうとしています。ChatGPTは既存の情報から大量のアウトプットを出すことが得意であるため,教科書の掲載内容についても質問さえすれば,事実をいとも簡単に説明してくれます。私もChatGPTを活用しますし,本書でも授業での活用例を紹介しています。しかし,ChatGPTを通して単に個別知識を調べただけでは,深い意味理解を促すことや,社会とのつながりは見出せないと考えます。授業を通して,自分で知識を獲得したり,友達の発言から「はっ」とする瞬間があるからこそ,子どもたちは深い意味理解に到達するのではないでしょうか。その前提として,子どもたちが楽しいと思える授業を行うことが大切です。そして,いわゆる公開授業のときだけ,とっておきの授業をするのではなく,日常的に楽しい授業を積み重ねていくことが大切だと考えます。
中学校社会科の大家である安井俊夫氏は,「日常」の授業に関わり,次のように述べています。
教科書の「事実」を中心に授業を構成することが求められているとしても,それに軽重をつけ,考えさせるべきヤマ場を設定して,授業を起伏のあるものにする工夫も必要である。あるいは,「事実」を並べるにしても,ストーリー性をもたせるような順序で並べれば「知識羅列型」の授業を少しは脱却できる。
中学校社会科では,毎時間かなり大量の「事実」を扱うことを要求されます。そのため,「日常」の授業では,それらの「事実」を中心に授業を構成せざるを得ません。本書も「日常」の授業を示すものですので,この制約内にあります。私自身も,中学校社会科の授業づくりをしていく中で,どのように「事実」を扱うか悪戦苦闘しています。しかし,事実ばかりを伝えることに終始していては,楽しい授業を準備し,子どもに力をつけることはできません。安井氏が述べるように授業のヤマ場をデザインし,子どもが「えっ?!」「どうして?!」と思うような場面をつくることで,子どもたちが主体的に知識を獲得することや活用することにつながるのだと考えます。日常的にこうした授業を積み重ねていくことで,本当の意味で子どもたちが力をつけられるのではないでしょうか。
中学校歴史的分野の学習では,時代の文化の特徴について学ぶ単元があります。以前,文化の学習について,子どもたちにインタビューをしたところ「覚えることがたくさんある」「暗記することが多くてつまらない」「どの時代にも文化があるのはわかるが,違いがよくわからない」など,否定的な回答が多くありました。文化について学ぶ際,単に「~の絵画が描かれた」「~という建物が建てられた」などの事実を伝えただけでは,子どもは知識を獲得することはできるかもしれませんが,追究する場面も生まれないので,単なる暗記を強いることになりかねません。
しかし,絵画を切り口に子どもたちに驚きを与えることもできると考えます。子どもたちの中には「洋画=海外」「外国人を描く=絵画」といったイメージをもっている子もいます。明治時代の文化について学ぶ時間では,横山大観(①)とルノワール(②)の作品を提示しました。「日本人が描いたのはどっち?」と問うと,生徒たちは迷わず横山大観の作品を選びます。その上で,黒田清輝『読書』(③)を提示します。黒田清輝はパリで印象派的な視覚を学んだため,『読書』は黒田清輝が描いたものだと確認すると,生徒から「えっ?」という声が生まれました。こうして生まれた問いは,子どもたちの追究のエネルギーにもなっていきます。資料提示や発問の仕方を工夫することにより,子どもたちの学びも大きく変わります。(図省略)
本書では,授業の導入からまとめまでの学習過程について,板書をもとにしながら紹介しています。本書の小学校シリーズの著者である朝倉一民氏も述べているように,授業について方法論的な「型」を生み出すべきではないと考えます。しかし,本書を手に取っていただいた先生方にわかりやすく,明日の実践に生きるような内容構成にしたいと考え,単元としての問題解決ではなく,一単位時間の問題解決ができるような授業も多く紹介しています。もちろん私自身も,日々試行錯誤しながら授業をしています。上手くいかなかった点,もっとこうしたらよいという点については,ぜひ工夫・改善しながら授業に臨んでいただければと思います。日常の授業の充実に向けて,授業の手引きにしていただければ,これ以上嬉しいことはありません。
/澤田 康介
-
 明治図書
明治図書