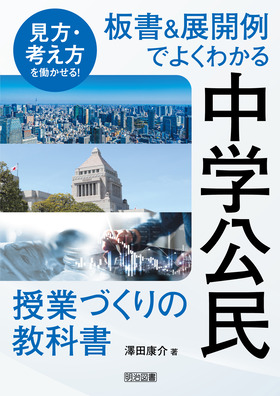- はじめに
- 1章 見方・考え方を働かせる!中学公民授業デザイン
- 1 見方・考え方を働かせて探究的な学びを実現
- 2 板書構成について
- 3 本書の読み方
- 2章 見方・考え方を働かせる!中学公民授業づくりの教科書 板書&展開プラン
- 1 【現代社会と私たちと文明】
- 1 授業開き ~戦争は止められるのか?~
- 2 AIは幸せをつくり出す?
- 3 法律で文化を守るのはどうして?
- 2 【よりよい社会とルール】
- 1 子どもにスマホを持たせるべき?! ~対立と合意~
- 2 どうする?!避難所運営! ~効率と公正~
- 3 【基本的人権と日本国憲法】
- 1 憲法って何のためにあるの?
- 2 天皇と国民の違いって?
- 3 アイヌ民族とこれからの社会 ~平等権~
- 4 身の回りにも差別がある? ~平等権~
- 5 自由権があるのに,自由じゃない?! ~自由権~
- 6 逮捕するぞと言われたら,あなたはどうする?! ~自由権~
- 7 パンツは何枚? ~社会権~
- 8 この働き方,大丈夫? ~社会権~
- 9 自由権があるのに,免許や資格があるのはなぜ? ~公共の福祉~
- 10 単元の学びから見える基本的人権
- 4 【私たちと平和主義】
- 1 原爆ドームが世界遺産になったのはどうして?
- 2 平和主義があるのに,自衛隊があるのはどうして?
- 3 平和な社会を築くために
- 5 【現代の民主政治と日本の政治】
- 1 民主政治はよい政治?
- 2 国会は信頼されていない?
- 3 たくさんの政党があるのはどうして?
- 6 【三権分立と国の政治の仕組み】
- 1 国会議員はうらやましい?
- 2 先生は総理大臣になれる?
- 3 トラブルが起きたらどうする?! ~民事裁判~
- 4 みんな同じ給料?! ~三権分立~
- 5 幸福度の高い北欧の国々
- 7 【地方自治と住民の政治参加】
- 1 牛乳で乾杯条例?! ~地方自治~
- 2 除雪をしているのは誰?
- 3 除雪費用を増やせないのはどうして?
- 4 単元の学びから見える地方自治のあり方
- 8 【消費生活と市場経済】
- 1 悪質商法にあったときには
- 2 こんなに?!販売価格と原価の差
- 9 【生産と労働】
- 1 利益を上げる企業がどうしてCSR?!
- 2 Karoshiと働く人の権利
- 3 どっちがいい?! ~年功序列と能力給~
- 10 【市場のしくみと金融】
- 1 せっかく育てたキャベツを廃棄処分?!
- 2 「金融」って何だろう?
- 3 円安・円高って?
- 11 【財政の役割と国民の福祉】
- 1 税金は嫌いだけど……,税金は必要?
- 2 税金の種類は何種類?
- 3 1297161500000000円! ~日本の財政の課題~
- 4 人生のリスクにどう対応する?! ~社会保障~
- 5 ホームレスの原因と社会保障制度
- 12 【これからの日本経済】
- 1 割り箸を使うことがエコなの?!
- 2 自分たちのまちをよりよくするには?
- 13 【国際社会の仕組みと平和の実現】
- 1 世界はあと90秒で終わる?!
- 2 国際平和の実現に向けた取り組み
- 3 戦車にも「UN」のマーク?
- 4 69年も支援を続ける理由とは?!
- 14 【これからの国際社会と私たち】
- 1 1日210円で生活してと言われたら
- 2 回転寿司店の社長が海賊を0に!
- 3 持続可能な未来を築くために私たちができること
- おわりに
- 参考文献一覧
はじめに
社会の変化はめまぐるしく,生成AIの登場により教育のあり方も大きく変わろうとしています。ChatGPTは既存の情報から大量のアウトプットを出すことが得意であるため,教科書の掲載内容についても質問さえすれば,事実をいとも簡単に説明してくれます。私もChatGPTを活用しますし,本書でも授業での活用例を紹介しています。しかし,ChatGPTを通して単に個別知識を調べただけでは,深い意味理解を促すことや,社会とのつながりは見出せないと考えます。授業を通して,自分で知識を獲得したり,友達の発言から「はっ」とする瞬間があるからこそ,子どもたちは深い意味理解に到達するのではないでしょうか。その前提として,子どもたちが楽しいと思える授業を行うことが大切です。そして,いわゆる公開授業のときだけ,とっておきの授業をするのではなく,日常的に楽しい授業を積み重ねていくことが大切だと考えます。
中学校社会科の大家である安井俊夫氏は,「日常」の授業に関わり,次のように述べています。
教科書の「事実」を中心に授業を構成することが求められているとしても,それに軽重をつけ,考えさせるべきヤマ場を設定して,授業を起伏のあるものにする工夫も必要である。あるいは,「事実」を並べるにしても,ストーリー性をもたせるような順序で並べれば「知識羅列型」の授業を少しは脱却できる。
中学校社会科では,毎時間かなり大量の「事実」を扱うことを要求されます。そのため,「日常」の授業では,それらの「事実」を中心に授業を構成せざるを得ません。本書も「日常」の授業を示すものですので,この制約内にあります。私自身も,中学校社会科の授業づくりをしていく中で,どのように「事実」を扱うか悪戦苦闘しています。しかし,事実ばかりを伝えることに終始していては,楽しい授業を準備し,子どもに力をつけることはできません。安井氏が述べるように授業のヤマ場をデザインし,子どもが「えっ?!」「どうして?!」と思うような場面をつくることで,子どもたちが主体的に知識を獲得することや活用することにつながるのだと考えます。日常的にこうした授業を積み重ねていくことで,本当の意味で子どもたちが力をつけられるのではないでしょうか。
中学校公民的分野の学習では,日本国憲法に関する単元があります。子どもたちに「日本国憲法という言葉を聞いたことある人?」と問うと,クラスの9割が手を挙げます。しかし,「日本国憲法ってなに?」と問うと,答えられる子どもはそうはいません。政治に関わることがらは,子どもにとっては馴染みが薄いため,興味・関心が弱くなりがちです。また,抽象的な内容も多いことから理解が難しくなってしまう場合があります。しかし,日常生活と関わりのある具体的な事例をできるだけ扱い,もの・ひと・ことがどのように動き,関わり合っているかを明らかにすることで,子どもたちも自分に引き付けて考えるきっかけになると考えます。
例えば,平等権に関する学習では,授業の導入場面で盲導犬に関するCM(AC JAPAN 日本盲導犬協会 CM「きみと一緒だから。」)を視聴します。動画の終盤でストップをかけ,CMの最後に流れる言葉を空欄にして提示します。空欄に入る言葉は「行けないところがある」です。盲導犬と一緒だからこそ生活しやすくなる人がいるにもかかわらず,なぜ入店を拒否する店もあるのか考えるきっかけへとつなげていきます。盲導犬を街で見たことがある子どもも多いと思いますが,こうした何気ない日常の中にも,基本的人権とつながりがある場面が潜んでいることに気付かせていくことができます。(図省略)
本書では,授業の導入から終末までの学習過程について,板書をもとにしながら紹介しています。本書の小学校シリーズの著者である朝倉一民氏も述べているように,授業について方法論的な「型」を生み出すべきではないと考えます。しかし,本書を手に取っていただいた先生方にわかりやすく,明日の実践に生きるような内容構成にしたいと考え,単元としての問題解決ではなく,一単位時間の問題解決ができるような授業も多く紹介しています。もちろん私自身も,日々試行錯誤しながら授業をしています。上手くいかなかった点,もっとこうしたらよいという点については,ぜひ工夫・改善しながら授業に臨んでいただければと思います。日常の授業の充実に向けて,授業の手引きにしていただければ,これ以上嬉しいことはありません。
/澤田 康介
-
 明治図書
明治図書