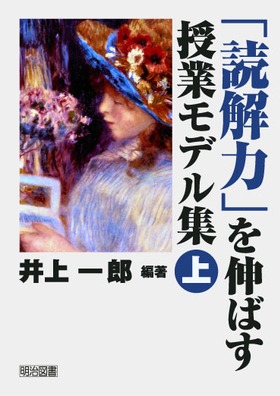- ���^�@���@��Y
- ��{�}����I�ڂ�
- �^��c�@�[�q
- ��@�Ǐ������Ɗ�{�}��
- ��@���H�u���ɗ��{��I��ŏЉ�悤�v
- �P�@�P�����E�Ώێ����^�@�Q�@���ށ^�@�R�@�Ǐ������^�@�S�@�P���̎w���ڕW�^�@�T�@�P���̕]���K���^�@�U�@�P���ρ^�@�V�@�P���̎��Ɖߒ��^�@�W�@���H�̋L�^�Ɖ��
- ���Ԃ̖ڕW�����߂ēǂ���
- �^��T�@����
- ��@�ڕW�����߂Ė{��ǂ�
- ��@���H�u�w���b���l�x�ɂȂ�邩�ȁv
- �Ƒ��œǏ����y����
- �^��c�@�]��
- ��@�Ƒ��œǏ����y����
- ��@���H�u�Ƒ��ƓǏ��������L�����悤�v
- �Ȃ肽�����ɓǂޖ{
- �^�����@�m�L
- ��@�Ȃ肽�����ɓǂޖ{�����p�����Ǐ�����
- ��@���H�u�Ȋw�ǂݕ���ǂ�ŁA���t�V�ъG�{�����낤�v
- �{�̃I���G���e�[�����O
- �^��q
- ��@�I���G���e�[�����O����{�̐��E�ɓ���
- ��@���H�u���������悤�u�b�N�A�C�����h���v
- ���M�ҏЉ�
��
�@�@�@�P
�@�ŋ߁A�Ǐ������̏d�v���������F�������悤�ɂȂ����B�w�Z�⋳���A����ɂ́A�����}���ٓ������p���đ����̎�g���s����悤�ɂȂ�A���̐��ʂ��グ�Ă���B�����A���߂����Ȃ��ۑ�����m�ɂȂ��Ă��Ă���B����́A�Ǐ������͍s����̂ɁA�Ǐ��͂����߂邱�ƂɘA�����Ȃ��ʂ�����Ƃ������Ƃł���B�{�����グ�邱�Ƃ��̂��̂�A�y�����ǂނ��Ƃ̒Nj��ɂƂǂ܂�A�����̓Ǐ��������q�ǂ��X�̐S�̖L������l����́A�����͓ǂނ��Ƃ̗͂̈琬�ɘA�����Ă��Ȃ��Ƃ����X����������̂ł���B�O���w�Ǐ��͂�����x��E�����i�����}���A��Z�Z��N��j�ł́A���̂悤�ȌX������肷��`�ŁA����Ȃ̒P���ł����ɓǏ��͂�t���邩�A�]���K���m�ɂ��Ȃ���A��̍�i�ɂ����Đ��ǂ��邱�ƂƑ��ǂ��銈�����ǂ̂悤�ɓ����I�Ɉ����悢�̂��A��Z�̃A�C�f�B�A��ĂƂƂ��Ɏ��H���������̂ł������B�������A���������Ƃ܂��܂�����������͂�L�`�̓Ǐ��͂ƌ��ѕt���Ă��Ȃ��Ƃ����X���͕��@����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����̂ł���B
�@���̂悤�Ȓ��������ɑ�����N���邩�̂悤�ɁA�����⍑�۔�r�̒������ʂ�������A�ǂނ��Ƃ̗͂ɉۑ肪���邱�Ƃm�ɂ����̂ł������B�����ł̋���ے����{�����i��Z�Z��N�x�E��Z�Z�O�N�x�j�̌��ʂ⍑�۔�r�����i�n�d�b�c�ɂ��o�h�r�`�����j�̌��ʂȂǂ�����ł���B�Ȃ��ł��A�������n���̃e�L�X�g�ɂ��Ă̓lj�͂����ƂȂ��Ă���B
�@�����́A�����Ƃ��čs���邪�̂ɁA�ۑ�ݒ��Ǐ��v��𗧂Ă��肷��v���Z�X�͏ȗ�����A���ǂ���u�lj��v�̃v���Z�X�ɏœ_�����Ă�ꂽ�B���ɁA�o�h�r�`�����ł́A�uREADING�@LITERACY�@�ǂނ��Ƃ̗́v�́A�u�lj�́v�Ƃ������{��^����ꂽ���A����́A���{�ōs���Ă����{�����Ȃ���悤�ȓlj��Ƃ͑S��������L�`�̊T�O�ł���B�o�h�r�`�����ɂ�����u�lj�́v�́A���̂悤�ɒ�`�t�����Ă���B
�@�q�o�h�r�`�����ɂ�����lj�͂̒�`�r
�@�@����̖ڕW��B�����A����̒m���Ɖ\���B�����A���ʓI�ɎЉ�ɎQ�����邽�߂ɁA�����ꂽ�e�L�X�g�𗝉����A���p���A�n�l����\�́B
�@�����́A�u�lj�́v�̊T�O���L���̂�A�@���l�ȃe�L�X�g�ɑΉ�����A�A�Ǐ��s�ׂ̉ߒ��A�܂�A�u���̎��o���A�e�L�X�g�̉��߁A�n�l�ƕ]���v�Ƃ������v���Z�X�Ɋ�Â����\�͂̒������s���Ă���B�n�l�E�]���ł́A�e�L�X�g���\�����܂��A�����̍l���m�ɋL�q���邱�ƁA����ɂ́A���e�ւ̍D��������^���E���Ȃǂ͕ۗ����A���̕��͂⎑���̑Ó�����]������Ƃ����N���e�B�J���E���[�f�B���O�܂ł�₤���̂ł������B�����́A�O���ŏq�ׂ��u�Ǐ��́v�A���Ȃ킿�A�Ǐ��s�ח͂ƓǏ������͂���ɓǏ��s�ׂ̃v���Z�X�ɉ����ēǏ��l����܂Ƃ܂����Ǐ�������g�ݍ��킹��Ƃ����l�����Ƃ����v���Ă���B
�@�@�P�@�ۑ�ݒ��
�@�@�Q�@�Ǐ��v���
�@�@�R�@�Ǐ��s�ח�
�@�@�S�@�Ǐ�������
�@�@�T�@�Ǐ������́i��i�n���́j
�@�@�U�@�R�~���j�P�[�V�����́i�p�t�H�[�}���X�́j
�@�@�V�@�L�^�E�]����
�@�����A�u�lj�́v�̋c�_�́A�����̃v���Z�X�̓��A�Ǐ��s�ח͂��ŏd�_�ɂ������̂ł��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�lj�͂̉ۑ�́A��̍�i��Ǐ�����s�ߒ��Ƃ��Ắq���̃v���Z�X�r�ƁA�����̓Ǐ������ɘA�����A�𗬂Ȃǂ��s������ɑ傫�ȁq���̃v���Z�X�r�̊̒��Ɉʒu�t������ƂƂ��ɁA�����̒��j�̔\�͂Ƃ��ď\���ɒ蒅���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���B
�@���ہA����������o�h�r�`�����ɂ���Ď����ꂽ�ۑ�́A�]���̍���Ȃɂ�����ǂނ��Ƃ̊w�K���Č���������̂ɏ\���Ȍ��ʂ��������Ƃ������悤�B�������ʂ��獡��̍���Ȃ̂�������T�ς��Ă����ƁA���̂悤�ɂȂ낤���B
(1)�@�A���I�ȕ������\�����镶�͂ɉ����A�`���[�g��\�A�����A�|�X�^�[�ȂǑ��l�ȃe�L�X�g��ǂސ}�Ǘ͂̈琬�̕K�v��������B
(2)�@���p�I�E�����I�Ȑ�����ʂɂ����錾�ꊈ���̑̌��ɘA�����A�Ǐ�������L���ɂ���L���Ȏ����Ƃ��ēǂފ������ʒu�t������K�v��������B
(3)�@�ǂނ��Ƃ́A��i�̓��e���Ȃ�������A�L�ۂ݂ɂ����肷�邱�Ƃł͂Ȃ��A�ǎ҂̖ړI�ɂ���č�i�����߂����p����͂̈琬�̕K�v��������B
(4)�@�ǂނ��Ƃ́A�ǎ҂����Ȃ̍l�������߂���A�܂Ƃ܂������z��ӌ����\�z������A���̍�i�⌻���Ɗ֘A�t���ĕ]�����邱�ƂŊ�������悤�Ɋw�K�������\������K�v������B
(5)�@�ǂނ��Ƃ́A�ǂޖړI���m�肷�邱�Ƃ���n�܂�A�\����͌����ďȗ��\�Ȋ����ł͂Ȃ��\�A�u�{���v��ǂ݁A�K�v�ɉ����ĕ��������ȋy�ѕM�҂Ɗ֘A�t�����߂��邱�ƁA���ȕ\���Ƃ��Ă܂Ƃ܂������ǂ���E�����s������A���z�⏑�]�y�їl�X�ȕ�ӌ��Ȃǎ��ȉۑ�ɉ�����u��i�v�̍\�z�A�����Č��������̉��P�A�Ƃ�������A�̊����ɂ����Ċ�������\�͂��琬����u�Ǐ��s�ׂ̃v���Z�X�v���y���ޔ\�͂ł��邱�Ƃm�Ɉӎ����A�����̔\�͂��琬����K�v������B
(6)�@����Ȃ݂̂Ȃ炸�A����ے��̗l�X�ȋ��Ȃ⊈����ʂ��Ĉ琬����K�v������B
�@���̂悤�ȉۑ�ɉ����邽�߂ɂ́A�L�`�́u�lj�́v���琬����q���̃v���Z�X�r�ƁA�����̓Ǐ������ɘA�����A�𗬂Ȃǂ��s���q���̃v���Z�X�r�̊̒��ɓǏ��������ʒu�t���A���̊������ǂ̂悤�ȖړI�������Ă���̂����m�Ɉӎ����邱�Ƃ��d�v���낤�B
�@�@�@�Q
�@�����ŁA���l�ȓǏ�������ʂ��āA���q�ׂ��悤�ȍL�`�́u�lj�́v���ǂ̂悤�ɐL���悢�̂��A���_�ʋy�ю��H�ʂ��猤�����A�O���̃V���[�Y�Ƃ��Ċ��s���邱�Ƃɂ����B���_�҂Ƃ��āw�u�lj�́v��L���Ǐ������\�J���L���������Ǝ��ƍ��\�x�A���H�҂Ƃ��āw�u�lj�́v��L�����ƃ��f���W�x�㊪�E���������s�����B�\���́A���̂悤�ł���B
�@�w�u�lj�́v��L���Ǐ������\�J���L���������Ǝ��ƍ��\�x
�@�@�T�@���{�̎q�ǂ��́u�lj�́v�\�������Ȃ̂�
�@�@�U�@�w�Z�S�̂Ŏ�g�ޓǏ������\�����璅�肷�邩
�@�@�V�@�Ǐ������̓�̃C���[�W�\���R�Ǐ��Ɖۑ�Ǐ�
�@�@�W�@�Ǐ������̃V�X�e�����Ǝ��Ɖ��v
�@�@�X�@���z�E�]���̂��߂̌��t��g�ɕt���悤
�@�w�u�lj�́v��L�����ƃ��f���W�x�㊪
�@�@��
�@�@��{�}����I�ڂ�
�@�@���Ԃ̖ڕW�����߂ēǂ���
�@�@�Ƒ��œǏ����y����
�@�@�Ȃ肽�����ɓǂޖ{
�@�@�{�̃I���G���e�[�����O
�@�w�u�lj�́v��L�����ƃ��f���W�x����
�@�@��
�@�@�I�m�}�g�y���W�߂悤
�@�@���X�Ɉ��ǎ҃J�[�h�𑗂낤
�@�@�{�̎O�����X�g����
�@�@�����̎��̏W����낤
�@�@�Ǐ��G�����̐��E�ւ悤����
�@�@�L�����N�^�[�J�[�h������ėV�ڂ�
�@�w�u�lj�́v��L���Ǐ������\�J���L���������Ǝ��ƍ��\�x�ł́A����ے����{������o�h�r�`���������炩�ɂ����ۑ�ɂ��ďڍׂɌ������A����̉��P�_���q�ׂ��B�w�u�lj�́v��L�����ƃ��f���W�x�㊪�E�����ɂ͎��H��Ă����߂��B���H��ẮA�Ǐ�������L���ɂ�����@��A�ړI�������ēǂ�ҏW�����肷����@�A���z�͂����߂���@�A���l�ȃe�L�X�g�������@�A�ȂǑ���ɂ킽��B���H�ɓ������ẮA���̂悤�Ȃ��Ƃɗ��ӂ����B
�@�@�w���ڕW��]���K���m�ɂ����P����
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ͓��R�Ȃ̂����A�]���̎��H��Ăł́A�ڕW��]���K�������m�Ɏ�����Ă��Ȃ����Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���H��Ă̓��e�����̂܂ܐ������悤�ȏꍇ�ɂ��A�������Q�l�ɐV�������H���l����ꍇ�ɂ��A�{���ł̎��H��Ă����f���Ɏw���ڕW��]���K�����l���Ă��炢�����B
�A�@���Ɖߒ��ɂ�����܂Ƃ܂������ꊈ���Ƃ��Ă̓Ǐ������̖��m�Ȉʒu�t��
�@���ǂ��邾���łȂ��܂Ƃ܂������ꊈ�����s������^�p�\�͂��d�v�Ȃ̂ŁA�Ǐ��������d�_��������A�J��Ԃ����肵�Ē蒅����悤�ɐ}���Ă���B
�B�@���Ȋw�K���d�������Ǐ�����
�@�Ǐ��́A����ǂނƂ�����̐��Ȃ��ɂ͐������Ȃ��B�Ǐ��͂�t����ƌ����Ȃ���A���t�哱�œǂނ��Ƃ����v������K�����̏ꂾ���̓Ǐ������ɏI��邱�ƂɂȂ�B���t�Ǝq�ǂ����b�������ɂ���Ă܂Ƃ߂����Ƃ�l�������Ƃ��m�F����悤�ɂ���B
�C�@�w�Z�}���ق̊��p
�@�w�Z�}���ق�����}���ق����p����悤�ȉۑ���\�z����悤�ɂ��A�Ǐ�������L���ɂ���B
�D�@�w�K�̗���ɉ����ĕK�v�Ȋw�K�����̊��p
�@�w�K���������p���Ď��Ȋw�K�𑣂��ƂƂ��ɁA�����̋L�^���Ǐ��𑱂��邱�Ƃ��x����悤�ɂ���B���H����ł́A�����̎����̗��ӓ_��g�������������B���Ɖߒ��̊w�K������S�Ď��グ��̂ł͂Ȃ��A�厖�Ȋw�K�𒆐S�ɂ��ēǂ݂₷������B
�@�����̎��H�ƂƂ��ɁA�O���Ŏw�E���Ă��������z�E�]����b�̑I����w�u�lj�́v��L���Ǐ������\�J���L���������Ǝ��ƍ��\�x�ōs���Ă���B�e�L�X�g�Ɋ�Â��Ď����̗����l���m�ɋL�q������A���͂⎑����]������N���e�B�J���E���[�f�B���O�����߂�ꂽ�̂ɂ������邽�߂ɁA�u����E�͍�E����v�Ƃ��������z�E�]����b��蒅�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl�����邩��ł���B�����̍l����]�������߂��Ă��A������L�q����\����������Ȃ���Ώ����悤���Ȃ��̂ł���A���̂悤�Ȏw�����]���ڂ݂��邱�Ƃ��Ȃ��A���z��]�������߂Ă������Ƃւ̖���N�Ƃ����������̂ł���B���́A��X�̊��z����앶�̃R���N�[���̐R���ψ������Ă���B�����ŁA�����R���ɏオ���Ă����D�ꂽ�q�ǂ��̊��z����ΏۂɁA���w�Z���獂�Z�܂ł̌n���ׂ����A���z�E�]����b�́A�c�O�Ȃ��炻��قǍL����Ȃ������B���w�Z���w�N���炢�܂ł͍L���邪�A��������悤�ɂȂ�̂ł���B
�@�I��ɓ������ẮA�ތꎫ�T�⍑�ꎫ�T�Ȃǂ��Q�l�ɑI�肵���O�Z�O�Z�����ՂɁA���ۂ̎q�ǂ��̊��z��b�ׂ���A��i�Ȃǂɕt���Ă���т̕]����b�ׂ��肵���B�����ɂ��āA���t�ɂ����Ɣ���@��p���đI�肵���B��w�N�E���w�N�E���w�N�E���w�Z�̎l�i�K�ɕ����Čn�������A���v���Z�Z���I�肵���B�����Ŏ��ۂɎg�p�ł���悤�Ɂu�w�N�ʔz�������v�ɔz���������z�E�]����b�̃��[�N�V�[�g���쐬���Ă���B�]���A���̂悤�Ȃ��Ƃɉ����錤���́A�S���Ȃ������ƌ����Ă悢�B���z�E�]����b�̌����́A���߂�n�l�E�]�����s���u�lj�́v�����I�ɐL�����Ƃɍv��������̂Ɗ��҂����B
�@�w�u�lj�́v��L�����ƃ��f���W�x�㊪�E�����̊��s�́A�k��B���ꋳ��J���t�@�����X�̉�����A�O���ɑ����āu�撣���āv���H�Ɏ��g���ʂƂ��Č����������̂ł���B�q�ǂ������̊�Ԏp������̂��y���݂ɁA���H�҈ȏ�̂��Ƃ�]�܂����t�����𑗂낤�Ƃ�����������ɂ��A�{���ɑ������Ƃ��Ǝv���B�����ԁA�Ǐ������𒆐S�Ɍ����Ɏ�g��ł������ƂŁA�O���Ɠ��l�ɁA���������̎��H�������ƂȂ������̂Ǝ�������B
�@�Ō�ɂȂ������A���s�ɓ������ẮA�����}���̐ΒˉÓT���A���{�K�q���ɂ����b�ɂȂ����B�\���͊Ȍ������A�[���ӈӂƂƂ��ɂ����ɋL���Ă��������B
�@�@��Z�Z�ܔN�㌎�@�@�@�����Ȋw�ȋ��Ȓ������@�^���@��Y
-
 �����}��
�����}��