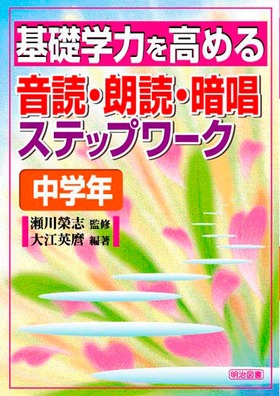- 序章 音読・朗読・暗唱の徹底で基礎学力を向上 中京女子大学名誉教授 /瀬川 榮志
- 美しい日本語との出会いを――言語感覚を高める音読・朗読・暗唱のスペシャルワークの特色 /大江 英麿
- Ⅰ 正しく読む 音読の基礎学習
- 正しく読む(1) リズムにのって
- 春が来た(高野 辰之)
- 正しく読む(2) 心をこめて父母を読む
- わすれない五月(大江 ひでまろ)
- 正しく読む(3) 口をしっかりあけて
- イヌが歩く(まど・みちお)
- 正しく読む(4) 「だ」の音をはっきりと発音する
- だるま(まど・みちお)
- 正しく読む(5) 小さな声で読む
- じめん(まど・みちお)
- 正しく読む(6) ひびくように読む
- きりん(まど・みちお)
- 正しく読む(7) 練習「早口言葉」
- 早口言葉
- 正しく読む(8) 「『おんど』ってなあに?」
- いろは おんど(阪田 寛夫)
- 正しく読む(9) 楽しい読み声
- おにが やい やい(阪田 寛夫)
- 正しく読む(10) よびかける
- おなかのへるうた(阪田 寛夫)
- 正しく読む(11) 「しりとりうた」を読む
- 年めぐり(阪田 寛夫)
- 正しく読む(12) くり返しの言葉を読む
- きました(阪田 寛夫)
- 正しく読む(13) 尺をとる
- 尺取虫(竹久 夢二)
- 正しく読む(14) 今きたこの道
- あの町この町(野口 雨情)
- 正しく読む(15) 歌を読む
- 赤い鳥小鳥(北原 白秋)
- 正しく読む(16) 口を大きくあけて
- 月
- 正しく読む(17) 音読記号を使って
- 赤いろうそく(新美 南吉)
- 正しく読む(18) 音のまとまりに気をつけて読む
- 春よ来い(相馬 御風)
- 正しく読む(19) 『校歌』を正しく読もう
- Ⅱ 深く読む 朗読の基本学習
- 深く読む(1) あれはなんだ
- つけもののおもし(まど・みちお)
- 深く読む(2) わかるかな
- びりのきもち(阪田 寛夫)
- 深く読む(3) ニンゲンって なんだろ
- ニンゲン(阪田 寛夫)
- 深く読む(4) こんな体験 すてき!
- すき すき すき(阪田 寛夫)
- 深く読む(5) おもしろい題ですね
- あたまの さんすう(阪田 寛夫)
- 深く読む(6) 祭りのふんいきをもりあげよう
- 夏まつり(大江 ひでまろ)
- 深く読む(7) 物語の圧巻を
- 手ぶくろを買いに(新美 南吉)
- 深く読む(8) 主人公の心をつかむ
- おじいさんのランプ(新美 南吉)
- 深く読む(9) 文語調に親しむ
- 故郷(高野 辰之)
- 深く読む(10) ずんずん積もる
- 雪(文部省唱歌)
- 深く読む(11) 雪はどんなふうにふるのかな
- ゆきがふる(まど・みちお)
- 深く読む(12) みんなで読もう
- ウミ(文部省唱歌)
- 深く読む(13) 感じを表して
- 砂山(北原 白秋)
- 荒海や佐渡に横たふ天の河(松尾 芭蕉)
- 深く読む(14) 様子を思いうかべて
- 菜の花や月は東に日は西に(与謝 蕪村)
- 春の海終日のたりのたり哉(与謝 蕪村)
- 深く読む(15) 昔の歌を読む
- 銀も金も玉も何せむに(山上 憶良)
- 子等を思ふ歌(山上 憶良)
- 深く読む(16) 漢詩を力強く読もう
- 偶成(朱憙)
- 勧学(陶潜)
- Ⅲ 豊かに読む 暗唱の統合学習
- 豊かに読む(1)「おうい、雲よ~」
- 雲(山村 暮鳥)
- 雲(山村 暮鳥)
- 豊かに読む(2) 体も使って暗唱しよう
- ケンパであそぼう(阪田 寛夫)
- 豊かに読む(3) 大きな声でよびかけるように暗唱しよう
- 夕日がせなかをおしてくる(阪田 寛夫)
- 豊かに読む(4) リズムを工夫して楽しく暗唱しよう
- あめのひの おきょう(阪田 寛夫)
- 豊かに読む(5) 声の強弱を工夫して読む
- おとうさんの あしおと(阪田 寛夫)
- 豊かに読む(6) 音の重なりを生かして読む
- 風の又三郎(宮沢 賢治)
- 豊かに読む(7) 間を工夫して暗唱しよう
- ごんぎつね(新美 南吉)
- 豊かに読む(8) 「ほんとうに人間はいいものかしら」
- 手ぶくろを買いに(新美 南吉)
- 豊かに読む(9) 昔からの『ことわざ』を味わって読もう
- 負けるが勝ち
- 芸は身を助ける
- 豊かに読む(10) 昔からの『ことわざ』を味わって読もう
- 情は人の為ならず
- 笑う門には福来たる
- 豊かに読む(11) 短歌に親しむ
- ふるさとの山に向ひて言うことなし(石川 啄木)
- ふるさとの訛なつかし(石川 啄木)
- 豊かに読む(12) 短歌に親しむ
- 霞み立つ 長き春日を子どもらと(良寛)
- 白雲の うつるところに小波の(与謝野 晶子)
- 豊かに読む(13) 俳句に親しむ
- 雪とけて 村一っぱいの 子どもかな(小林 一茶)
- やせ蛙 負けるな一茶 これにあり(小林 一茶)
- 豊かに読む(14) 俳句に親しむ
- 梅一輪 一輪ほどの 暖かさ(服部 嵐雪)
- 閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声(松尾 芭蕉)
- 豊かに読む(15) 言葉と心を声にのせて
- ことばは心(せがわ えいし)
- Ⅳ 付録 ワーク枠
序章音読・朗読・暗唱の徹底で基礎学力を向上
中京女子大学 名誉教授 /瀬川 榮志
「正しく美しい日本語で優れた日本人の育成~よき言語生活者を育てる日本語教育」……このキーワードは、二十一世紀に世界の中の日本人として国際社会に生きていく児童・生徒を育てる学校教育の重要課題です。
しかし、大人と子供の言葉遣いの実情には危惧感を抱くことがあります。「言葉の乱れは心の乱れ、心の乱れは行動の乱れ、行動の乱れは社会の乱れ、社会の乱れは国家の衰亡につながる」~のではなかろうか。
正しい発声・発音ができない子。語彙が貧弱で自分の思いや考えを的確に話せない子。国語の教科書の文章を明瞭な音声で正確に読めない子。読みが浅く文学作品などの高い価値や深い感動を豊かに表現できない子もいます。この子供たちを温かく支援し、的確に指導して「正しく美しい日本語」を、学校・家庭・社会生活で場面や相手あるいは目的に応じて適切に駆使・運用できるようにしたいものです。
音読・朗読・暗唱を積極的に取り入れると国語学力が確実に向上します。学力の低下が議論されていますが、この重要な問題を解決する具体策は、音読・朗読・暗唱の指導の強化であると確信しています。
また、この指導を徹底することによって言葉のひびき合い、余韻余情のある日本語、季節の変化を巧みに描き心のひだを微妙に表現できる日本語。視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚などの五感を駆使して、正誤・適否・美醜・主題・行動~感覚などの五感を磨き語感を豊かにして、日本語独特のよさを学ぶこともできます。このことは、現在の我が国の教育に求められている「心の教育」に連動します。
音読・朗読・暗唱の指導をより一層効果的にし、一人一人の子供の国語学力を高めるためには次の事項を押さえることが大切です。
一、生きて働く国語力として確実に定着させるために学習者の能力の発達段階に即して「基礎的技能」→「基本的能力」→「統合発信力」の螺旋的系統によって指導する。
二、学習体系も螺旋的系統に即して「基礎学習」→「基本学習」→「統合学習」とし、その方法も、生きて働く国語力をつけるために、段階的にレベルアップする言語行動としてシステム化する。
三、教材の選択の開発に当たっては、「基礎・基本・統合発信力」の系統に即すると共に、学習のシステム化に適切な作品・名文・名句・名作・俚諺・漢詩・古典等々を開発したり精選したりする。
四、指導に当たっては、系統的・段階的に言語行動を編成する。断片・偶発的に指導しても効果は上がらない。また、音読する→朗読する→暗唱する~という全身表現の行動学習に徹することである。
五、音読・朗読・暗唱力の向上の決め手は、繰り返し学習の徹底である。継続的に反復練習することに尽きると言っても過言ではない。それも単なるドリルではなく、「易から難へのステップ」を踏む学習法である。
六、学習の効果を上げるために、絶対評価と指導の一体化を図る。特に、自己評価や相互評価で学習者の興味・関心・意欲を高めるようにする。音読・朗読・暗唱力は、的確な評価ができるものである。
七、音読・朗読・暗唱を通して感動したことや、理解・表現の方法を友達と双方向的に情報交換をする。あるいは児童集会や施設の訪問などでも「伝え合う力」が育ち人間関係力が培われる。
八、日本の伝統文化・言語文化・文学等についての知識や教養を身に付ける素地を養うことができる。朗読・暗唱・朗読力を練磨し継続する努力・精進・昂揚によって生涯充実した生き方ができる。
このように、音読・朗読・暗唱は国語力の基礎力の習得から文化の習得や、人間関係力さらには人間力獲得の生涯教育にいたるものであり、幅が広く奥の深いものであると確信しています。
『基礎学力を高める音読・朗読・暗唱ステップワーク』は、以上のような国語教育の理念・理論や、指導の原理・原則に基づき具体的なワーク学習つまり、行動学習を通して国語力が定着できるように楽しく企画構成したものです。本書の三巻は、『「国語学力向上アクションプラン」シリーズ』の一環として企画したものです。基盤となる実践書としては『基礎的技能・基本能力・統合発信力ワーク』全七巻(明治図書)を発刊しています。それに『ゆとり教育から学力向上へ「国語学力・絶対評価で鍛える」一年~六年』全六巻(明治図書)も評価重視の視点から根底に据えました。
学力向上行動計画の本企画は、低学年の企画編集を岩谷武利先生(北九州市小倉国語の会)、中学年の企画編集を大江英麿先生(山形穐世紀の国語教育を創る会)、高学年を山本直子先生(埼玉穐世紀の国語教育を創る会)にお願いしました。
各研究会においては、低・中・高学年の能力や特色に応じた編集に工夫を凝らしており、国語科教育の理念・理論や国語科指導の原理原則に基づいた行動学習が展開できるようにシステム化されています。
本書が、新世紀に生き抜く子供たち一人一人の生きる力の支えとなる「生きて働く日本語力」の獲得に連動することを心から願っているものです。
山本直子先生をはじめ同会員の武市幸子先生、草村久美子先生、藤田恵子先生には編集調整等の総括を意図的・計画的に進めていただきました。この実践研究力を備えたスタッフの先生方は、これまでに『楽しく学ぶ「話し方・聞き方」ワーク』〈一年~六年 全六巻〉『「学び方技能が育つ総合的な学習」ワーク』〈三・四年用 五・六年用 全二巻〉(明治図書)を刊行した実績があります。
本企画においても「声を出せ!」(全小国研協力)や「音読集」(まど・みちお監修)についての教材分析ならびに行動学習の実践などの事前研究を積み重ね、情報交換を密にして「基礎学力を高める音読・朗読・暗唱ステップワーク」を完成しました。次は、「伝え合う力を育てる『対話法』の指導~ステップワーク」作成に挑戦しています。今後さらに研究体制を確立して「ワーク学習」つまり「行動学習」で「基礎・基本・統合発信力」を獲得する方法の開発を推進することを期待しています。
「国語学力向上アクションプラン」の価値あるシリーズを企画してくださった明治図書出版企画開発室長代表、江部満様には、本書(三巻)の企画から発刊まで心温まるご支援いただき感謝しております。
学力向上は我が国の重要課題であり、この解決には国語力を高めることの具体策が求められます。国語教育において、何のために、何を、いつ、どこで、どのように指導すればよいのか。また、学習者主体・言語行動主体の国語教育を理論的に体系化し、どのように具現化すればよいかを追求して、このシリーズを充実していきたいと考えています。
まどみちお、阪田寛夫両先生には作品掲載にあたって、特別にご諒解を得た。心からお礼を申し上げたい。
(21世紀の国語教育を創る会 代表)
-
 明治図書
明治図書