- ������
- �喴�c�s���@�^�ց@�D�F
- �͂��߂�
- �^�y��@�K�F�E���c�@����
- CHAPTER�P�@���_�ҁ@�r�c�f���^�d�r�c�Ƃ�
- �^�y��@�K�F
- 1�@���E�̖r�c�f���\�N��l���c���Ȃ��Љ���߂�����
- 2�@�r�c�f���̒B���Ɏ�����d�r�c�\�����\�ȎЉ�̑n�����琬���邽�߂�
- 3�@�喴�c�̒n��n���������l�Â���\���l�X�R�X�N�[���̂܂��Ƒ喴�c�łr�c�f��
- �����@�喴�c�s�ɂ�����r�c�f���^�d�r�c��10�N�̕���(1)
- CHAPTER�Q�@���Â���ҁ@�r�c�f���^�d�r�c�𐄐i���邽�߂�
- 1�@����ψ���̎�g�i�s���������r�c�f���^�d�r�c�̑��l�ȓW�J�j
- �i�P�j�����\�ȑ喴�c��
- �i�Q�j�u�����ނ��v����u���l�X�R�X�N�[���E�d�r�c�̂܂��@�����ނ��v�̑n��
- �i�R�j�����̑喴�c�ւ̓W�]
- �����@�喴�c�s�ɂ�����r�c�f���^�d�r�c��10�N�̕���(2)
- 2�@�w�Z�̎�g�i�����\�ȎЉ�̑n������ފw�Z�o�c�j
- �i�P�j���l�X�R�X�N�[���S���҂̍Z�������ւ̈ʒu�t��
- �i�Q�j�r�c�f���^�d�r�c�̔N�Ԏw���v��
- �i�R�j�q���̊w�т��A���E���W����X�g�[���[�}�b�v�i�P���v��j
- �i�S�j�n��Ƃ̌𗬂ɂ�����S�̃p�^�[��
- �i�T�j�q���̊w�т̏[���Ɍ������̌��I�����ɂ���
- �i�U�j���l�ρC�s���̕ϊv�����҂���w�тÂ���
- �i�V�j���l�X�R�X�N�[���Ƃ��Ă̊e�w�Z�ɂ������g
- �i�W�j�r�c�f���ɂ��Ă̊w��
- �i�X�j�u���l�X�R�X�N�[���̓��v�̎�g
- �i10�j�s���̃��l�X�R�X�N�[���Ƃ̌�
- �i11�j�S���̃��l�X�R�X�N�[���Ƃ̌�
- �i12�j�C�O�̊w�Z�Ƃ̌�
- CHAPTER�R�@���H�ҁ@�w�Z�ɂ�����r�c�f���^�d�r�c�̎��Ǝ���
- ����1�@�����ɂȂ���܂��@�g�쏬���v���W�F�N�g
- �喴�c�s���g�쏬�w�Z�E��T�w�N
- ����2�@�݂�Ȃ��Ȃ��钆�F�Z���ڎw���ā|�q�ǂ������ψ������|
- �喴�c�s�����F���w�Z�E��T�w�N
- ����3�@�{���B�u�q�ǂ��{�����e�B�A�K�C�h�v
- �喴�c�s���j�n���w�Z�E��U�w�N
- ����4�@�t�����[�^�E���v���W�F�N�g
- �喴�c�s���吳���w�Z�E��T�w�N
- ����5�@�T�Z������v���W�F�N�g
- �喴�c�s��������w�Z�C�ʐ쏬�w�Z�C�g�쏬�w�Z�C�������w�Z�C���F���w�Z
- ����6�@�L���C��O�r�`�������喴�c�C�m����v���W�F�N�g
- �喴�c�s���݂ȂƏ��w�Z�C�V�̏��w�Z�C�j�n���w�Z�C�V�̌����w�Z
- ����7�@�l���^�̂܂��Â���v���W�F�N�g
- �喴�c�s���{�����w�Z�E��R�w�N
- ����8�@�h�ЁE���Ѓv���W�F�N�g
- �喴�c�s���k���w�Z�E��P�w�N
- ����9�@�𗬋y�ы����w�K�v���W�F�N�g
- �喴�c�s���喴�c���ʎx���w�Z�E���w���C���w���C������
- ����1�`4�E7�`9
- �i�P�j�{�Z�̂d�r�c�̓���
- �i�Q�j���ނɂ���
- �i�R�j�{���H�Ŗڎw���r�c�f��
- �i�S�j�P���̎w���v��
- �i�T�j�w�K�����̎��ہi�����I�Ȋ����j
- �i�U�j�����̕ϗe�^���k�̕ϗe�^�������k�̕ϗe
- �i�V�j����Ȃ���H�̏[���Ɍ�����
- �����@�X�g�[���[�}�b�v�^�d�r�c�̐}
- ����5
- �i�P�j�T�Z�������Ŏ��g�ނd�r�c�̈Ӌ`
- �i�Q�j�{���H�Ŗڎw���r�c�f��
- �i�R�j�e�w�Z�̎��H���e
- �i�S�j�T�Z�����E��T�~�b�g
- �i�T�j����Ȃ���H�̏[���Ɍ�����
- ����6
- �i�P�j�喴�c�ɂ�����C�m����̈Ӌ`
- �i�Q�j�S�Z�����i����喴�c�s�C�m����̍\��
- �i�R�j�{���H�Ŗڎw���r�c�f��
- �i�S�j���H��T�@��R�w�N�u�L���C�E��������@�C�̐������I�v
- �i�T�j�w�K�����̎��ہi�����I�Ȋ����j
- �i�U�j���H��U�@��U�w�N�u�C�Ɛl�Ƃ�ʂ��Č������喴�c�̂܂��v
- �i�V�j�w�K�����̎��ہi�����I�Ȋ����j
- �i�W�j�喴�c�s�C�m���琄�i�Z�S�Z�ɂ�����w�т̌�
- �i�X�j�����̕ϗe�Ƃ���Ȃ���H�̏[���Ɍ�����
- �����@�C�m���琄�i�Z�̑S�̌v��E�N�Ԍv��
������
�@�@�@�喴�c�s���@�^�ց@�D�F
�@�䂪�܂��喴�c�͑吳�U�i1917�j�N�Ɏs�����{�s���C����29�i2017�j�N��100���N���}���܂����B�{�s100�N�̗��j�́C�䂪���̋ߑ㉻�Ɛ�㕜��������������O�r�Y�z�ƂƂ��ɔ��W���Ă܂���܂����B�������C���̎O�r�Y�z���C���̃G�l���M�[����̓]����荇������]�V�Ȃ�����C���ɕ����X�i1997�j�N�ɕR���܂����B
�@���̂悤�Ȓ��C�O�r�Y�z���c�����ߑ㉻�Y�ƈ�Y�ł���u�{���B�v�u�O�r�Y�z��p�S���~�Ձv�u�O�r�`�v�́C����27�i2015�j�N�Ɂu�������{�̎Y�Ɗv����Y�@���S�E���|�C���D�C�ΒY�Y�Ɓv�̍\�����Y�Ƃ��āC���E������Y�ɓo�^����C�n��̕��E�̕�ɂȂ�܂����B�����̕��X���{�s��K��C���E������Y�����w����C���{�̗��j�E�Y�Ƃɂ��Ċw��ł��������Ă��܂��B�܂��C�w�Z�ł̐��E��Y��ʂ������j�⋽�y�w�K���̏[���ɑ傫����^���Ă���Ƃ���ł��B
�@���āC�{�s�̌����̑S���E���E���ʎx���w�Z���C����24�i2012�j�N�Ɉ�ĂɃ��l�X�R�X�N�[���ɉ������Ĉȗ��C����ψ���E�w�Z�E�W�@�ցE���c�̂��A�g��}��Ȃ���C�s�������Ăd�r�c�i�����\�ȊJ���̂��߂̋���j�𐄐i���Ă���܂��B����ɁC�u�r�c�f�������s�s�v�Ƃ��āC�{�s�̉ۑ�܂��Ăr�c�f���i�����\�ȊJ���ڕW�j�ɂ����g��ł���܂��B
�@���́C�s���Ƃ��āu��҂����������ē����܂��Â���v�u�q��Đ���ɖ��͓I�Ȃ܂��Â���v�u���S���Č��C�ɕ�点��܂��Â���v�����̂R�̂܂��Â���Ɏ��g��ł��܂��B
�@���̎����Ɍ����āC�q�������������̖���ڕW�Ɍ������Ĉӗ~�I�Ɋw�сC�����\�ȎЉ�̑n���ƂȂ�悤�ɋ��炪�[�����Ă���܂���ڎw���C�܂��C�e�w�Z�����l�ȋ��犈����W�J���邱�Ƃ��ł���悤�C�w�Z��������[�������Ă���Ƃ���ł��B
�@�����S���q���������C�l�X�ȑ̌���ʂ��ĖL���Ȑl�Ԑ��⊴�������ł������Ƃ��C�喴�c�̎���100�N��n���Ă����b�ɂȂ���̂ƐM���Ă��܂��B
�@�{���́C�d�r�c��r�c�f���ɂ��Ă̗��_��C�喴�c�s����ψ����e�w�Z���C���l�X�R�X�N�[���Ƃ��Ăd�r�c�𐄐i����10�N�Ԃ̎�g������I�Ȋw�Z�̎��H�C�s�������͂��ߊW���c�̂Ƌ������Ď��g���e�J�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B�{�����C���ꂩ��̎����\�Ȃ܂��Â���̓W�]�������Ă��������ƂƂ��āC����ɁC�w�Z����ɂ����ẮC�r�c�f���B���Ɍ������d�r�c�̎�g�̏[���Ɍ������ꏕ�ƂȂ�C�V�������H�Ƃ��Ċ�������܂����Ƃ�����Ă���܂��B














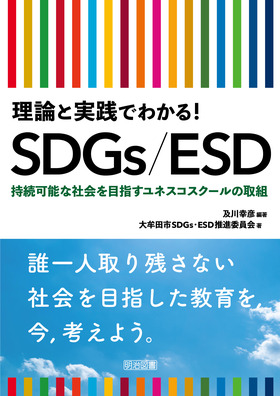



SDGs�̌������Ƃ����邽�߂ł��B
�{�Z�͑����I�Ȋw�K�̌������ė��N�x�s���܂����A���͎Z���̎��Ƃ�SDGs�����g�ޏ�ł̍��{�I�Ȏ����\�̖͂ʂ�����Ƃ��s���܂��B
���̏�ŁASDGs�̎��H�Ⴞ���ł͂Ȃ��A���_�������Ă������������ƂŁA�e�w�Z��������\�ʓI�ŏ㊊�肷��悤�Ȍ����ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��������Ă���悤�Ɏv���܂����B
�@�~�������A�w�K�]�����d�v�����������A�]����ɂ��Ă��ڂ����m�肽�������ł��B�܂��A�Ίێ��̂����u�n��v���ʂ��������ɂ��Ă��L�q������Ɗ������ł��B���Ҋy���݂ɂ��Ă��܂��B