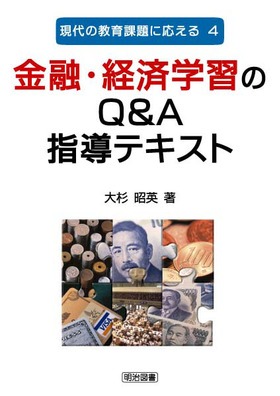- まえがき
- Ⅰ章 金融・経済学習の見取り図
- Q1 何のために金融・経済を学ぶのか
- Q2 経済学習は学習指導要領のどこに位置付くのか
- Q3 経済学習の体系図を描くとどのようになるだろうか
- Ⅱ章 経済的に考えるとは
- Q1 私たちは日常生活の中でどのような経済活動を行っているか
- Q2 何をどのように考えることが「経済的に考える」ことになるのだろうか―経済の基本問題―
- Q3 企業はどのような経済的選択を行っているのだろうか
- Q4 家計はどのような経済的選択を行っているのだろうか
- Q5 政府はどのような経済的選択を行っているのだろうか
- Ⅲ章 市場経済って何?
- Q1 価格が変化するのはなぜか
- Q2 需要が増えたり減ったりするのはなぜか
- Q3 市場経済の「市場」とはどこにあるのだろうか
- Q4 市場にはどのようなものがあるか
- Q5 私たちは何を基準に商品を購入するのか
- Q6 私たちはどのようにして収入を得ているか
- Q7 年功序列型賃金と能力給はどう違うのか
- Q8 企業とはどのようなものだろうか
- Q9 企業は社会にとってどのような役割を担っているのか
- Q10 私たちは企業(会社)をつくることができるだろうか
- Ⅳ章 政府はどのような経済活動を行っているか
- Q1 国や地方公共団体はどのような経済的な役割を担っているか
- Q2 政府が行う経済活動の元手はなぜ税金なのか
- Q3 政府はどのような経済政策を行っているか
- Q4 私たちの使っている1万円札は本当に1万円の価値があるか
- Ⅴ章 経済活動を国単位でまとめると何が分かるだろうか
- Q1 私たちの経済は成長しているのだろうか
- Q2 景気が良い時期と悪い時期がなぜ繰り返し起こるのだろうか
- Q3 インフレーションって何?
- Q4 デフレーションって何?
- Q5 お金とは何か
- Q6 金融とは何か
- Q7 金融機関はどのような働きをしているのか
- Ⅵ章 国と国との関係を経済的な繋がりで考えるとどうなるか
- Q1 日本と諸外国との経済的な繋がりを見るにはどうすればよいだろうか
- Q2 なぜ国と国は貿易を行うのか
- Q3 自由で活発な貿易が展開されるために国際社会ではどのような工夫が行われているか
- Q4 互いに異なる通貨を使う国が貿易を円滑に行うためにどのような工夫が行われているか
- Q5 日本の貿易をめぐる現代世界の状況はどのようになっているか
- Ⅶ章 我々の社会で解決が求められている経済的な諸問題は何か
- Q1 消費者被害の問題(消費者保護)をどう考えればよいだろうか
- Q2 労働問題をどう考えればよいか
- Q3 少子高齢社会における社会保障をどのように考えればよいか
- Q4 失業問題をどう考えればよいか
- Q5 産業の空洞化をどう考えればよいか
- Q6 赤字国債をどう考えればよいか
- Q7 南北問題をどう考えればよいか
- Q8 経済摩擦をどう考えればよいか
- Ⅷ章 金融・経済学習の Q&A指導テキスト(本書)の使い方
- Q1 この指導テキストを使ってどのように授業を行うか
- Q2 この指導テキストを使って金融・経済学習のための年間指導計画をどのようにつくればよいか
まえがき
高校生のころ,定期試験の期間中になるとなぜか今まで見向きもしなかった小説を無性に読みたくなって困ってしまうことがありました。読者の皆さんもよく似た経験があるのではないでしょうか。私の場合,夕食後から就寝時間までの3時間を試験勉強と小説のどちらに使うのか迷いながら,結局小説を読んでしまい,試験結果を返してもらうたびに後悔するという繰り返しでした。
一見(?),優柔不断な人間だと思われたのではないでしょうか。ところがこの優柔不断さを経済的に分析してみると結構いい教材になるのです。なお分析のためには,ここでは次のような経済の基本的な考え方が分析枠組みとして必要となります。
「欲求は無限だが資源は有限であり,この希少な資源をいかに配分するかという選択が経済の基本問題である」
それでは,これを用いて先の私の経験を分析してみましょう。限られた「資源」とは試験期間中の夕食後の「3時間」であり,「欲求」とは「試験勉強をすること」と,「小説を読むこと」になります。両方の「欲求」を満たすためには3時間という「時間」(資源)では少ないので,どちらかの「欲求」を満たすことしかできません。そこで「選択」の必要が生じてきます。これはまさに希少な資源の配分にかかわる「選択」を行うという経済問題になっているわけです。
私たちは日常生活においてこのような「選択」を数多く行っています。私の高校時代のように後で後悔しないために合理的な意思決定力を育てることが必要であり,そのためにも希少な資源の配分にかかわる「選択」を客観的に科学する経済の勉強が大切になるのです。
今日,こうした合理的な意思決定力を育てる「経済教育」に対する期待はますます高まっています。中央教育審議会「審議経過報告」(平成18年2月)においても「子どもたちが社会の変化に主体的に対応できるようにするためには,……法や経済などに関する教育の充実が求められている。」と述べられ,その後の審議過程で具体的改善事項の例として「社会経済システムの高度化・複雑化への対応のため,法,経済などに関する内容の充実,課題追究的な学習を一層重視」することが示されているところです。
本書は,このような社会的な要請に少しでも応えることができるように,金融・経済学習の具体的な展開を想定した指導テキストを提案したいと考えました。特に,児童生徒が経済の問題を科学するためには追究すべきテーマと教師の発問が重要な役割を果たすと考え,「学習テーマ」「発問」「資料」をセットで示すことはできないかと検討しました。そして本書を,①Q(クウェスチョン),②本文,③「授業化するための発問例」の三つで構成することにしました。①には授業における学習テーマを示す役割を,②には学習すべき内容や資料を示す役割を,③には教師の発問を示す役割を与えることにしたのです。
さらに,金融・経済の問題を科学する年間指導計画を疑問形の学習テーマで作成したものを最後に示すことにしました。このような形で年間指導計画を提示することで,授業者は,児童生徒に何を追究させるのか,あるいは何を分からせればよいのか,何をできるようにすればよいのかが明確になるし,児童生徒も同じく,何を追究し,何が分かれば,あるいはできればよいかが明確になると考えたからです。
本書の冒頭のQは「何のために金融・経済を学ぶのか」という問いからはじまっています。それでは読者のみなさんと一緒に経済問題を科学したいと思います。
最後になりましたが,執筆の機縁を与えていただいた編集部の安藤征宏氏,本書の校正でお世話になった土井辰雄氏にお礼を申し上げます。
2007年1月 /大杉 昭英
-
 明治図書
明治図書