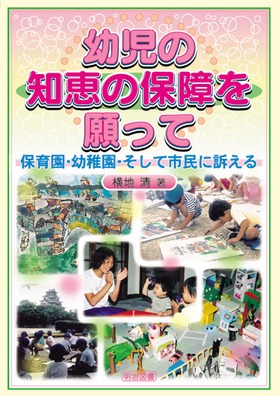- ���@�G
- �͂��߂�
- �T���@�l�ނ̒m�b�C�搶�̒m�b�C�c���̒m�b
- �P�@�c���̒m�b�������Ȃ���
- �Q�@�l�ނ̒m�b�@�\�\�����̍ʓ��E����E����\�\
- �R�@�搶�̒m�b�@�\�\�V���E�C�O��������̗c�t���̐搶��������Ɂ\�\
- �S�@�T�Ύ��̖͗l�̒m�b
- �T�@�T�Ύ��̎ʐ��̒m�b
- �U�@���w�Z�T�N���͉^���\���Ŗ͗l��`��
- �U���@�P�Ύ�����T�Ύ��܂ł̒m�b�̔��W
- �P�@���ۈ牀�̍�i�W����
- (1)�@���ۈ牀�ł̌�����̐i�s
- (2)�@�c���̔��W
- �Q�@����ۈ牀�̕ۈ�W����
- (1)�@����ۈ牀�ł̌�����̐i�s
- (2)�@�c���̔��W
- �V���@�m�b��U������搶��
- �P�@�m�I�ȕ���̋���ے�
- �Q�@�����c�t��
- �R�@�ЂƂݗc�t��
- �S�@���ۈ牀
- �T�@����ۈ牀
- �U�@����C���w�C�G�摢�`�̋���ے��̒@����
�͂��߂�
�@���̖{�͕ۈ牀�C�c�t���̐搶���͂��Ƃ��C�c������Ă�ی�ҁC�X�ɗc������ɊS�̂���s���̕��X�ɁC�c������̐i�ߕ������ۓI�ɒm���Ē������߂Ɏ��M�����B
�@�O�Ύ�����̗c���ɂ͏[�������ۈ炪�K�v�ł���B�����ɏ[������������K�v�ł���B���̋���̐i�ߕ��́C���w�Z�ȍ~�̊w�Z�ŗ\�z����鋳��Ƃ́C�������莖��Ⴄ�B�ނ���C���w�Z�ȍ~�̋��炪�C�܂��Ƃ��ȗc������Ɋw�ԕK�v��������ł���B
�@�O�ێ�����̎q���́C����݂Ȃ������ɑ����ʂ̒m�������߂Ă���B���̒m�b��̑S�̂̊�����ʂ��Ċl���������̂ł���B�ۈ牀��c�t���̐搶���́C�q�����C���������߂Ă��邩��c�����C�V�т⊈�����H�v���āC�q���Ɏ��Y���C�����Ɣw�������C�m�b�̑̓���}��K�v������B����ɂ́C�搶���̌J��Ԃ�������K�v�ƂȂ�B�������Ă����C�搶���́C�q���̒m�b�̗v���������o���C����ɉ����C���肳�����Ďq���̒m�b��U�������W�����邱�Ƃ��o����B
�@�c����c�t�ƌ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̖{�ł��C�T�Ύ��̖͗l��C�L����Ⓑ��̊ዾ���̎ʐ����Љ�邪�C�����̍�i�͌����ł���B�������̓ǂ݂͊��ɂR�Ύ��Ɏn�܂�C���莆�������͂S�Ύ��̑�D���Ȋ����ł���B45�x��]��90�x��]�̉~�͗l�ЂƂƂ��Ă��C�S�Ύ��C�T�Ύ��̎q���͎��R�ɑn�삵�C�����͗l���Q�x�ƕ`���͂��Ȃ��B���ł�10�܂ł̐��̕������C�ËL�ł͂Ȃ��V�т̒��ő̓�����B�����܂ŗ���ɂ́C�O�Ύ�����̑����̋���̎��H���K�v�ƂȂ�B�c���͗c�t�ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���̖{�ł́C�c���̒m�b�̔��W�̕ۏ������āC���L�̂R���ɕ����Ď��M�����B����̕����L�x�Ȏ����Ō�邱�Ƃɂ����B
�@�T���ł͗c���̒m�b�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����q�ׂ��B�U���ł͂O�Ύ�����T�Ύ��܂ł̗c���̒m�b�́C�N���ǂ��āC�ǂ̂悤�ɔ��W���邩���q�ׂ��B�V���ł͗c���̒m�b�̗v���ɉ����C���肵�ėc���̒m�b��U������搶���̌����͂ǂ̂悤�ɐi�߂��邩���q�ׂ��B
�@����1995�N�ȗ��C�c������w����Ƃ��C���Ɂw��Ǝq�����ԁu�c������̕S�ȁv�x�i�O�ȓ��C1971���j�C�w�c�t���E�ۈ牀�u�ۈ�S�ȁv�x�i�����}���C1981���j�̑啔�̕S�Ȃ��Q���C���ɂ��C���̑��C�����̗c������̐}�����������Ă����B�������C�O�Ύ�����̕ۈ炪�d�v�������悤�ɂȂ��Ă��������C����ƑΉ����āC�O�Ύ�����̋�����܂��d�v�ł���C���̏d�v�ȋ���̎��ۂ���邽�߂ɖ{�������M�����B
�@�����g�C���ł��C�ۈ牀�C�c�t���ɒʂ��C�����̌�����C���w���̍��h��������w�����Ă���B���̖{�́C���������w���̌o�߂�w�i�Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂ł���B���M�ɍۂ��āC���s�s���݂́u���ۈ牀�v�C�����q�s���݂́u������C��j�C��O�ۈ牀�v�C�L���s���݂́u�ЂƂݗc�t���v�C����s���݂́u����ݗc�t���v�C���s���݂́u�����c�t���v�ȂǑ����̉��̂����b�ɂȂ����B�����̕ۈ牀�C�c�t���ɂ������ӂ������B�܂��C���̖{�̏o�ł����コ��C�ҏW���̑��ł����b�ɂȂ����C�����}���ҏW���̍]�������C��ؓ��q���ɂ���������q�ׂĂ��������B
�@�@2004�N�S���@�@�@�^���n�@���@�L
-
 �����}��
�����}��