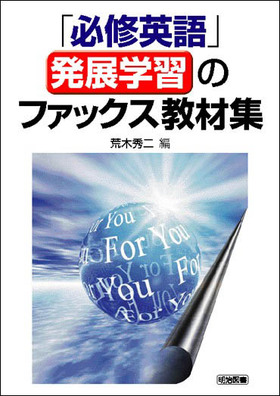- �͂��߂�
- ��P�́@�u�m���Ȋw�́v����ސV�����p��Ȃ̎w��
- §�P�@�u�ɉ������w���v��ʂ��āu�m���Ȋw�́v��
- §�Q�@�u�ɉ������w���v�ɐ��������ފJ���̃|�C���g
- �P�@���w�Z�p��Ȃɂ�����u��b�I�E��{�I�ȓ��e�v
- �Q�@�K�C�p��̓��e
- �R�@�w���ƕ]���̈�̉�
- �S�@�u�K�n�x�ʎw���v���{��̔z������
- �T�@�u��[�I�Ȋw�K�v�Ɓu���W�I�Ȋw�K�v�̂��߂̏W�c�����Ǝw����̗��ӓ_
- ��Q�́@�u�R�~���j�P�[�V�����ւ̊S�E�ӗ~�E�ԓx�v�����߂锭�W����
- �m�R�~���j�P�[�V�����n
- �P�@�P�N�FDo you �` ? �Ƃ��̓������Ɋ���悤
- �Q�@�P�N�FAre you �`ing ?�i���ݐi�s�`�j�Ƃ��̓������Ɋ���悤
- �R�@�Q�N�F�����̏������iwill�j�̋^�╶�Ƃ��̓������Ɋ���悤
- �S�@�Q�N�FThere is �`.�̕\���Ɋ���悤
- �T�@�R�N�F�Ԃ̕\���Ɋ���悤
- �U�@�R�N�F�f�B�x�[�g��Objection!�u�ًc����v
- ��R�́@�u�\���̔\�́v�����߂锭�W����
- �m�b�����Ɓn
- �V�@�P�N�FQuestions to ALT
- �W�@�P�N�FDescribing a character �\���ȏ��̓o��l���ɂ��Ęb����
- �X�@�Q�N�F�S�[���f���E�B�[�N�ɂ������Ƃ�b����
- 10�@�Q�N�F���{�I�Ȃ��̂�������悤
- 11�@�R�N�F�ǂ{�̓��e�����|�[�g���悤
- 12�@�R�N�F�X�s�[�`�����悤
- �m�������Ɓn
- 13�@�P�N�F�F�B�Љ�i�X�s�[�`�j�̌��e������
- 14�@�P�N�F�P���̊G�����āC���̓��e��`���镶������
- 15�@�Q�N�F�x���̂ł����Ƃɂ��ē��L���ɏ���
- 16�@�Q�N�FALT�̓d�b���āC���̓��e��`����`����������
- 17�@�R�N�F�n��Љ�̃|�X�^�[�����
- 18�@�R�N�FALT�̘b���C�v�_���܂Ƃ߂�
- ��S�́@�u�����̔\�́v�����߂锭�W����
- �m�������Ɓn
- 19�@�P�N�F�܂Ƃ܂�̂�����e�̉p����āC��ȕ�������낤
- 20�@�P�N�F�p����āC����Ȃ�������`���Ă݂悤
- 21�@�Q�N�F�K�v�ȓ��e�𐳊m�ɕ�����낤
- 22�@�Q�N�F�Θb���āC�K�v�ȕ����ɏœ_�Ăď�����낤
- 23�@�R�N�F�����e�[�}�ɂ��ďq�ׂ���Q�̏��̈Ⴂ�𐳊m�ɕ�����낤
- 24�@�R�N�F�A�i�E���X�Ȃǎ������̏�Ŏ��ɂ���p����āC�K�v�ȏ�����낤
- �m�ǂނ��Ɓn
- 25�@�P�N�FReading Game�i�lj��j�\�Q�[����N�C�Y��ʂ��C�y���݂Ȃ���ǂ���
- 26�@�P�N�FReading the Story�i�lj��j�\�����ǂ݁C�G�𐳂������Ԃɕ��ׂĂ݂悤
- 27�@�Q�N�FShadowing�i���ǁj�\CD��e�[�v�Ɠ����X�s�[�h�œǂ�ł݂悤
- 28�@�Q�N�F�p���̊T�v���Ƃ炦��Reading�i�lj��j�\���{��̐ݖ�ɓ����āC�lj�͂�������
- 29�@�R�N�F�p���̊T�v���Ƃ炦��Reading�i�lj��j�\����̊T�v�����݁C�i����������Ă݂悤
- 30�@�R�N�F�O���̕��������m��Reading�i�lj��j�\�O���̗l�q�����m�邽�߂ɉp����ǂ���
- ��T�́@�u�����ƕ\���v�̔\�͂����߂锭�W����
- �m�������ƁE�b�����Ɓn
- 31�@�P�N�F�p��ł�����������C�p��Ŏӂ낤
- 32�@�P�N�F�p��œd�b�������悤
- 33�@�Q�N�F���肢�C�˗������悤
- 34�@�Q�N�F�U���C���҂���Ȃǂ̉�b�����悤
- 35�@�R�N�FAsking the Way�i���������˂�j
- 36�@�R�N�FAre you OK?�i�̒��������˂�j
- ��U�́@�u����╶���ɂ��Ă̒m���E�����v�����߂锭�W����
- �m����E�����Ɋւ��邱�Ɓn
- 37�@�P�N�F�A���t�@�x�b�g�ŕ\�������̗����ׂ悤�\���ۑ��̍����\�L
- 38�@�P�N�F�p��̕W���Ȃǂɗp���闪��̂��낢��
- 39�@�Q�N�F����ʂ�\���\���\�p����L�̕\�����ɂ���
- 40�@�Q�N�F�@�@���낢��ȕ����̎g�����Ɋ���悤�^�A�@�p��Ɠ��{��̃W�F�X�`���[��Δ䂵�Ă݂悤
- 41�@�R�N�F�@�@�p��̘A��⊵�p�\���Ɋ���悤�^�A�@��{�I�ȕ��^�╶�@�����Ɋ���悤
- 42�@�R�N�F���Ƃ킴�ɂ���p��Ɠ��{��̋��ʓ_�\���Ƃ킴�̔�r��ʂ��āC���̂̍l�����̋��ʓ_��T��
- �m�����Ɋւ��邱�Ɓn
- 43�@�P�N�FEnglish and New Englishes �\���E�ɂ͂��낢��ȉp�ꂪ����
- 44�@�P�N�FAmerican English and British English �\�ǂ����ē����p��Ȃ̂ɈႢ���ł��Ă��܂��̂��ȁH
- 45�@�Q�N�F���낢��ȃJ�[�h���p��ŏ����Ă݂܂��傤���\�p��ŏ�������V�N�����v���X����邩��
- 46�@�Q�N�F���Ƃ킴�E�����W�\���Ƃ킴�͐�l�̌��t�̍��Y
- 47�@�R�N�F���{�H���p��ŕ\�����Ă݂悤�\������o���Ă����Ɩ��ɗ�����
- 48�@�R�N�F���{�̕������p��ŕ\�����Ă݂悤�\���{�Ɠ��̂��̂��p��Ő�������Ɠ��e���킩��₷��
- 49�@�����F�p��̉����������Ă݂悤�\�����C�����̔����Ƀ`�������W�I
- 50�@�����F�p��̏������l���Ă݂܂��\���Ȃ��ɂƂ��āC�p��Ƃ́H
- �t�^�P�@��������
- �t�^�Q�@���i���ށE����j�̑S��
�͂��߂�
�@�w�Z���S�T�T�����̉��C���w�Z�N�ԑ����Ǝ���980���ԑ̐��ɂ��V����ے����X�^�[�g���āC�͂�R�N�ڂ��}���Ă���B
�@�O����Ȃɂ����ẮC�e�w�N�K�C�N��105�i�T�R�j���ԂƁC�P�N�ŔN30���ԁC�Q�`�R�N�ōő�70���Ԃ܂ŋ��e�����I�����Ǝ����̘g���ŁC���Ȃ̖ڕW�Ɍf����u���H�I�ȃR�~���j�P�[�V�����\�́v�̈琬�Ɍ����ėl�X�Ȏw�����W�J����Ă����B�����āC���̐V����ے��̃X�^�[�g�ɔ����ē������ꂽ���Ȏw���Ɋւ��u�W�c�ɏ��������]���v����u�ڕW�ɏ��������]���v�ւ̑�]���ւ̑Ή��ɔ����邱�ƂƂȂ�C���X�̎w���͌����C���Z�����̂��߂̓��\���ɗp����u�w�K�̋L�^�v�̕]��L���Ɏ���܂ŁC����܂ł̕]���E�]��̂�����̉��P�Ƃ��K�Ȏ��{�Ɍ����đ����̓w�͂��X�����Ă����Ƃ���ł���B���̎�|���āC���w�Z�O����Ȃɂ�����w���ƕ]���̈�̉��ɂ��Ă��C�����̎w����]�����̉��P�C���Ó����E����̍����]���K���̐ݒ�ȂǁC�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ肪�����c����Ă���Ƃ���ł���B
�@����ɁC�����Ȋw�Ȃ�����13�`17�N�x�̂T���N�ԂŎ��{����|�C�ʒB�����u�掵�������`�����珔�w�Z���E���萔���P�v��v���_�@�Ƃ��āC�S���̎����́C�w�Z�ɍL�܂����u���l���w���̕Ґ��v�������w�K�w���ɂ��Ă��C�ǂ̊w�Z�ɂ����Ă��C���X��̓I�ȑΉ��ɔ�����ۑ�ƂȂ��Ă���B�����̉��v�ɋ��ʂ��鍪�{���O�́C�Ƃ��Ɂu�ɉ���������v�̎����ł���C���̎��H�̏�ƂȂ�S���̊w�Z�C�����ɂ�������X�̎w���ɂ����āC���҂͖��ڂȊ֘A���ȂĎ��g�܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ����i��ттĂ�����ł���ƌ����悤�B
�@�u�ɉ���������v�ɂ��ẮC�啝�Ȋw�K���e�̍팸���V����ے��̎��{�ƂƂ��ɁC�������k�̊�b�w�͊m�ۂ̊ϓ_����C�v�X���̕K�v���ւ̔F�������܂��Ă��钆�ŁC�e���Ȃɂ�����w���̏[���E���P��}���ŁC�w�����e�C�Ƃ�킯�C����܂ł̎��H�̒��ł��C�K�������\���Ȑ��ʂ��オ���Ă���Ƃ͌����Ȃ������C�Ⴆ�C�u�ɉ����C�^�Ɉ�l��l�̐��k�̃j�[�Y�ɓK�������ނ̊J���v�Ȃǂ̖ʂňˑR�傫�ȉۑ���c���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�@�Ƃ���ŁC��N�W���C��������R�c��̋���ے�����́C�w�K�w���v�̂̐��i�i����j�ɂ��āC�u���ׂĂ̎������k�Ɏw�����ׂ����e�����������́v�Ƃ��āC������ׂ��Œ���̓��e�ł���Ǝw�E����ƂƂ��ɁC�u�������k�̎��Ԃɉ����C�w���v�̂Ɏ�����Ă��Ȃ����e�������邱�Ƃ��\�v�Ƃ̈ʒu�Â������āC�u�ɉ�����w���v�ւ̈�w�̎��g�݂𑣂������̈ꕔ����������B
�@�V�������w�Z�O����Ȋw�K�w���v�̂�����ƁC�I�����Ȃ𗚏C������ꍇ�ɂ́C�u���k�̓������ɉ����C���l�Ȋw�K�������W�J�ł���悤�C���e�ɂ��ẮC��Q�̓��e���̑��̓��e�Ŋe�w�Z����߂���̂ɂ��āC�ۑ�w�K�C�R�~���j�P�[�V�����\�͂̊�b��|����[�I�Ȋw�K�C���W�I�Ȋw�K�Ȃǂ̊w�K�������e�w�Z�ɂ����ēK�ɍH�v���Ď�舵�����̂Ƃ���B�v���Ƃ�������Ă���B�����}���ł́C��ɁC���c�a�l�ҁw�u�I���p��v��[�w�K�E�ۑ�w�K�^���W�w�K�̃t�@�b�N�X���ޏW�x�i�S�Q���j�̊��s�������Ƃ���ł��邪�C���̂��т̒����R����ے�����ɂ��u�w�ɉ�����w���x�̈�w�̏[����}�邽�߁C�K�C�^�I�����킸�C��[�I�Ȋw�K�C���W�I�Ȋw�K�̍H�v������w�K�v�ɂȂ��Ă���B�v�Ƃ̒���̉����ׂ��C�{���̔��s�Ɏ���������ł���B
�@�ҏW�ɓ������ẮC�܂��C�u�ڕW�ɏ��������]���v�̎�|�������u�w���ƕ]���̈�̉��v��}�邱�ƁC����ɂ��C�����̏�K�n�̒��x�ɉ��������l���w�K�̗L������ϋɓI�ɐ��������ƂȂǁC�ŋ߂ɂ�����w�K�w�����P�̂������Ƃ̊֘A���l�����C�����̃m�E�E�n�E���\�������ꂽ�w�����e�E�w�����@�̉��P��}�邱�Ƃ��ł���悤�ɓw�߂��B�Ⴆ�C�]����̕�[�E���W�w�K�i�w���j��z�肵�āC����ɂ���Ắu�z��B���x�i�_�j�v���������݂Ȃǂ��������B���������āC�{���̓��e�ɂ��ẮC�w�u�K�C�p��v�̕�[���ށx�Ɓw�u�K�C�p��v�̔��W���ށx�̂Q���ō\�����C�e���̕ҏW�ɂ��ẮC���̂悤�ȕ��j����{�Ƃ����B
�@���@��P�����C�u�K�C�p��v�̂����C�R�~���j�P�[�V�����\�͂̊�b��|�����߂̕�[�w�K�ɖ𗧂Ă�t�@�b�N�X���ނ𒆐S�ɁC��Q�����u�K�C�p��v�̂����C���k�̈ӗ~��B���ɉ����āC����ɐi��ł�荂�x�ȓ��e�Ɏ��g�܂��邽�߂̔��W�w�K�ɖ𗧂Ă�t�@�b�N�X���ނ𒆐S�ɍ\������B
�@���@�e���̍\���ɂ��ẮC�Ҏ҂̊����w���w�Z�p��Ȃ̓��B�x�]���|�ϓ_�ʕ]�����50�I�|�x�i�����}���j�̍l���������C���w�Z�w�K�w���v�̂ɂ�����u���e�v�̒�����{�Ƃ����B����ɂ��C���w�Z�p��Ȃɂ�����u�w���ƕ]���̈�̉��v�����R�ɐ}����悤�ɂ���B
�@�u�K�C���ȁv�Ƃ��Ẳp��̊w�K�́C�T�R���ԂƂ�������ꂽ���Ǝ����ɂ����̂ł��邪�C���̋M�d�Ȏ��Ƃ𒆐S�ɁC�N�Ԃ�ʂ��čl������l�X�Ȋw�K�̏��@����C���X�̐��k�Ƌ��t�̐G�ꍇ���̒�����n�o���Ă������Ƃ���ł���B��������C���k��l��l�̎���ɉ��������l�Ȏw���̓W�J��S�����Ă�����搶���̂��߂ɁC���L���ŖL���ȋ��ނ̒ƂȂ�悤�C���M�҈ꓯ�w�͂��X��������ł���B���ꂩ��̎w���ɑ傢�Ɋ��p����邱�Ƃ�����Ă���B
�@���M�Ȃ���C���X�̋����ł̎w�����H�̒�����M�d�ȋ��ޗ�����Ղ������M�w�̐搶���ɁC�܂��C�{���̊��E�ҏW�ɏI�n���Ȃ��w���E�������������������}���ҏW���̈������G���ɐS���犴�ӂ������B
�@�@2004�N11���@�@�@�Ҏҁ@�^�r�@�G��
-
 �����}��
�����}��