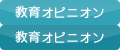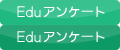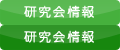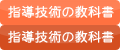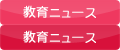- 国語科指導技術
- 国語
授業に深みを与えるためには?
これまでの国語授業
「教師としての読み」で読む
授業に深みを与えるのは、教師による「教師としての読み」ではなく「一人の読者としての読み」です。
「教師としての読み」とは、簡単にいえば、
- 何を指導すべきか
- 子ども達にどのように発問しようか
などを考えながら読むことです。
これはもちろん授業をつくるうえで重要であり、欠かせないものです。授業を機能させるために必要なものといえるでしょう。教師が子どもの目線に立って「子どもはどう読むだろうか」と考えて読むことになります。
一方、「一人の読者としての読み」とは、教師としての立場は一旦忘れ、
- 自分が最も心に残ることは何か
- 自分の経験と結びつくことはないか
などと教師が一人の人間として読むことです。
授業を深いものにしていくのは、こちらの方です。ここでは、教師は自分の経験や知識を総動員して「全力で」読むことになります。
国語科指導技術・ニューノーマル
「一人の読者」として読む
一般的に「読むこと」の教材研究というと、「教師としての読み」ばかりを指すのではないでしょうか。しかし、それ一辺倒では授業は深まりません。なぜなら、子どもの読みがしばしば「教師としての読み」を超えてくるからです。
例えば、「大造じいさんとガン」で「残雪とおとりのガンは違うと思う。大造じいさんはそれを分かっていると思う」などと発言してきたとき、例えば「スイミー」で「スイミーは大きな魚を追い出した後、また仲間と一緒に住むのかな」などと発言してきたとき、「教師としての読み」を深めているだけでは、これらの発言の価値に気付けず、対応できません。これらの発言は作品の本質を突いていますが、「教師としての読み」だけではたどり着けないところです。現に、セミナー等で「大造じいさんとガン」の講座をしていると、多くの先生方が、大造じいさんが残雪とおとりのガンを区別して扱っていることに気付いていないということが分かります。
「主体的・対話的で深い学び」が求められる今、授業に深みは欠かせません。
その深みを生み出すのは、教師による「一人の読者としての読み」です。
まずは、どのように指導するかということは置いておいて、「全力で」読むことをおすすめします。教師の読み以上に子ども達の読みが深まることは、ないのですから。
ここがポイント!
- 深い学びは、教師の「全力の読み」の先にある。
教材の特性を掴むには?
これまでの国語授業
授業者のセンスや読書量に基づいて教材分析をする
文学や説明文の教材には、一つ一つそれぞれ特性があります。
国語科の授業力は端的にいえば、「教材の特性を掴む力」ともいえます。この力がある先生は、何となく授業をしても本質を突いた授業ができてしまいます。一方、この力がない先生は、頑張って教材研究をしているのにズレた授業をしてしまいがちです。
例えば、「一つの花」は三人称客観視点で書かれた物語ですが、この物語を中心人物の変容を主に扱おうとすると無理が生じるでしょう。登場人物の心情などはあまり語られず、そもそも中心人物をゆみ子と考える人もいればお父さんと考える人もいるからです。そのような中で、中心人物の変容を扱うのは教材の特性を掴めていないと言わざるを得ません。
しかし、この「教材の特性を掴む力」は少し抽象的です。私の大学院時代の恩師である長崎伸仁先生は「教材研究をしていると、教材からこう扱ってくれという教材の声が聞こえてくるんだ」と仰っていました。私はそれを聞いて何度も教材を読みましたが、結局「教材の声」は聞こえてきませんでした(涙)。長崎先生はセンスがあるから教材の声が聞こえるのであって、私のようなセンスのない人間には教材の声は聞こえないのではないか、そう悲観することもありました。確かに、「教材の特性を掴む」には、その教師のセンスやこれまでの読書量などに左右される部分が大きいのも事実です。
それでは、私のようにセンスのない教師は永遠に「教材の声」を聞くことはできないのでしょうか。
たしかに、ただ漠然と教材を何度も読むだけでは厳しいでしょう。しかし、「視点」をもって教材を眺めることで、その教材の特性が見えてきます。
教材研究のセンスがある先生は、一文一文をかみしめ解釈しているだけではなく、「視点」をもって教材を眺め、教材の特性を掴んでいます。それをマネするのです。
例えば、白石範孝先生(明星大学)の「教材分析のための読みの観点(文学)」は、とても分かりやすく10個の視点にまとめられていて、おススメです。ただ読むのではなく、これらの視点を借りて教材を眺めるクセをつければ、自分なりに教材の特性を掴めるようになっていきます。初めはマネから入ってよいのです。
国語科指導技術・ニューノーマル
視点をもって教材を眺める
参考文献:白石範孝(2020)『白石範孝の「教材研究」』(東洋館出版社)
ここがポイント!
- 教材研究はまず、マネから始めよう。