- きょういくじん会議
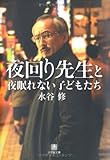
学校も夏休みに入って子どもたちも解放的な気分になる7月。夏は日も長く、夜に外を出歩く機会も増えてくることや、成人の約5.2倍という高い刑法犯少年の検挙人員、少年犯罪の凶悪化などの社会的背景から、7月は特に「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」とされています。社会的に弱い立場であること、精神的・肉体的に発達途中であることで被害者にも加害者にもなりやすい子どもたちを守るため、近年、子どもの非行を防ぐ試みが盛んに行われているようです。
成果をあげる「夜回り大学生」
7日の朝日新聞の記事によると、10代の少年非行率ワースト1の福岡県で、少年の非行防止に大学生が一役買う取り組みが行われているということです。夜歩きを説教する警察官と、それに反発する少年たちの会話を取り持つ「学生サポーター」として、家庭裁判所の調査官や教師を目指す学生たちが県警と一緒に夜間の街頭補導を行い、活躍しているとのこと。
学校の先生や警察官、両親など大人に言われると反抗してしまうことでも、年齢の近い大学生が声をかけ、話をすると納得できる、というのはその年代の心理としてはわかるような気がします。強がってはいても、日頃から自分のことを心配してくれ、話を聞いてくれる人が周りに少なく、内心は寂しい思いをしているのかもしれませんね。子どもたちがなぜ非行に走るのか? その原因の一つも、そのあたりにあるのかもしれません。
全国に広がる「非行防止教室」
文部科学省は、全国の学校で行われた「非行防止教室」の実践例を、「非行防止教室等プログラム事例集」としてホームページに掲載しています。小学校での「人のものや店のものをとらない」といった基本的なルールについて学ぶ取り組みや、中学校での「非行行為を断る勇気を育む取り組み」、「保護者を対象とした非行防止教室」など犯罪の種類や対象とする人に応じていろいろな方面からアプローチしているようです。
少年犯罪が多発する原因として、社会の規範意識の低下があると言われています。知らず知らずのうちに、悪いことは悪いことだとわざわざ教えこまなくてもわかるだろう、常識だ、と大人から見た常識を子どもに押し付けているところもあるのではないでしょうか? 基本的なことですが、何が悪いことで、何をしたら人が悲しむのかを子どもたちにしっかりと伝えていくことが、実は何よりも重要なのかもしれません。
まだまだ続く夏休み、楽しい行事もたくさんありますが、時間のあるときにゆっくりお子さんと話し合ってみるのもいいかもしれませんね。
