- きょういくじん会議
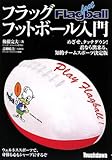
2011年度から施行される小中学生の「新・学習指導要領解説」にフラッグフットボールが正式に例示として掲載され、今後授業内外で取り組みが拡大されることになりました。
まだ世間では馴染みの薄いスポーツですが、簡単に言うとやさしい「アメリカンフットボール」。しかしその面白さは失われずに、別の魅力が増した新しいスポーツとの評判です。
アメリカンフットボールは日本でも人気のあるスポーツですが、そのプレーの激しさにより、多くの人にとっては観戦を楽しむだけであって自分が楽しむスポーツとは言えません。そこでさまざまな点を簡略化し、安全面における心配をできるだけ少なくし、老若男女が楽しめるスポーツとして考案されたのがフラッグフットボールです。
攻撃側のボールを持った選手が腰につけた「フラッグ」を、守備側が取ったり外したりした時点で「タックル」されたということになり、攻撃終了。基本的に接触プレイは禁止(反則)となっています。
しかし、なぜフラッグフットボールが教育界から注目されたのでしょうか? このスポーツの特徴をいくつか見てみましょう。
1.毎プレーごとに作戦時間がある
プレーが1回1回止まるので、失敗したら何が悪いかを話し、すぐに次のプレーに生かせるので、児童は考えることの大切さを学べます。しかも、作戦を書いたノートなどを自由に持ち込むことができるとか。事前の作戦作りに熱が入りそうですね。
2.ベースは鬼ごっこ
鬼ごっこのような単純な動きだけで、子どもたちが十分に楽しむことができます。動きが簡単であればあるほど作戦が物を言う?
3.交代が何回でもできる
だからこそ、みんなに活躍のチャンスがあります。攻撃は得意だけど守備は苦手…という子は、攻撃の時だけ出て大活躍してもらうのでもいいかもしれません。それが自信につながりますよね。
4.みんなに役割がある
このスポーツには、誰が何をするかの明確な役割分担が必要になるそうです。「走る」「受け取る」「守る」「投げる」などをそれぞれが担当し、チームワークのよいほうが勝つ。運動能力の高い子が一人よがりでプレイしても点にはなりません。
このように誰もが楽しむことができ、なおかつスターになれる可能性があるスポーツがフラッグフットボール。現在はアメフト関係者などが直接学校に赴いて指導を行うほか、教育関係者に対する講習会なども各地で行われているようです。
休み時間にドッジボールやサッカーに混じって、フラフトをする子どもたちを見る日も近そうですね。

