- はじめに
- 序章 通常の学級でできるくり上がり・くり下がりのあるたし算ひき算の支援
- 第1章 くり上がり・くり下がりのあるたし算ひき算習得トレーニングワーク
- ワーク1〜4 20までの かず
- ワーク5〜8 10を わけよう
- ワーク9〜12 たしざんを しよう
- ワーク13〜16 えを つかって たしざんを しよう1
- ワーク17〜20 えを つかって たしざんを しよう2
- ワーク21〜24 ことばを いいながら たしざんを しよう1
- ワーク25〜28 ことばを いいながら たしざんを しよう2
- ワーク29〜32 ひきざんを しよう
- ワーク33〜36 えを つかって ひきざんを しよう1
- ワーク37〜40 えを つかって ひきざんを しよう2
- ワーク41〜44 ことばを いいながら ひきざんを しよう1
- ワーク45〜48 ことばを いいながら ひきざんを しよう2
- 第2章 くり上がり・くり下がりのあるたし算ひき算習熟トレーニングワーク
- ワーク49〜52 おとなりさんで 10を さがそう
- ワーク53〜60 あんごう かいどく
- ワーク61〜64 クロス けいさん
- ワーク65〜68 +−を いれて しき かんせい(10まで)
- ワーク69〜72 かずを いれて しき かんせい
- ワーク73〜76 +−を いれて しき かんせい(20まで)
- *解答&解説
- おわりに
はじめに
本書は、算数が苦手な児童生徒に対して一斉授業のなかでスモールステップの教材を使い、つまずきの原因発見と支援のヒントを与えてくれます。発達障害がある/なしに関わらず、子どもたちに計算をわかりやすく解説し、完全に理解してもらうということは大変難しいことです。私たち大人の頭のなかではこうすればいいと説明できても子どもたち一人一人が理解できるように言葉で納得のいく説明に到達するのは至難の業です。「できた」ではなく「わかった」と本心から言える教え方が望まれます。
本書では、「どこでつまずいているのか」を特別支援教育の視点を取り入れて一人一人にぴったりの学習支援を見つけていきます。計算は、暗算と筆算があります。計算が難なくできるようになるためには、早い時期に数詞(「1つ、2つ、3つ」、「いち、に、さん」)、数字(1、2、3)、具体物との対応(りんごが3つ)ができることが求められます。数字が読める前に数詞を順番通りに言えるようになることが望ましいです。また、数字が数と量を示していることに気づくことも大切です。
次に数の概念の形成では、基数性(同時処理過程)と序数性(継次処理過程)があります。同時処理では直感的に4つより6つのほうが量的に多いことに気づく、継次処理では前から何番目、後ろから何番目というように順番がわかるなどを丁寧に教えていきます。数概念の発達を促しながら加減の意味がわかる子どもへと育てていきます。
20までの加減学習の課題は、くり上がり・くり下がりの計算の仕組みの理解、その計算手順の習得、そして最後に暗算でできるようになることです。一般に算数を指導するときに、たし算では視覚化、ひき算では言語化という方法で計算手順を教えることが多いようです。しかし、特別支援教育対象の様々な認知特性に偏りがある子どもの場合は、きめ細かく一人一人のストロングポイント、ウイークポイントを見極め、子どもの見る力、聴く力、記憶する力、集中する力などの特性に合わせていくことが真の理解につながります。2年生、3年生になっても計算にまだ指を使っている子どもの場合、指を禁止するのではなく、なぜ指が必要なのか、どのような支援がいるのかの視点が必要です。
本書は、中尾先生の特別支援教育のコツが詰まっている貴重なトレーニングワークです。
ぜひ普段の授業で、家庭で活用してください。子どもの「わかった!!」という笑顔が見たいです。
2018年6月 監修者 /竹田 契一















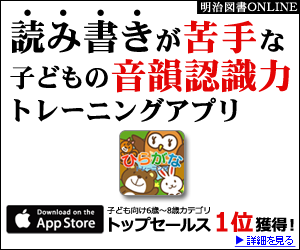
 PDF
PDF


UDデジタル教科書体などで作ってもらえるといいなと思います。
コメント一覧へ