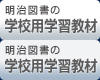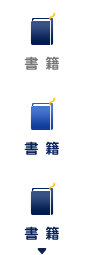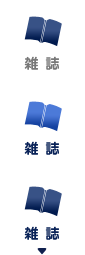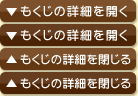はしがき
すべての子どもを賢くすこやかに育てることが、教育という仕事の目標でなければならない。そのことに正面から異議をとなえる人はおそらく一人もいないだろう。
しかし、建前はそうであっても現実はどうであろうか。現在の学校の現実はこの建前どおりになっているだろうか。一人の子どもも落後させることなしに毎回の授業は進められているのだろうか。いまの学校は、子どもたちを優等から劣等へと一直線に序列づけ、優等生をちやほやし、劣等生をおとしめる選別のための機関となり果てていないだろうか。
数年前の全国教育研究所連盟の調査によると、半数以上の子どもが学校の授業から取り残されているという。それはたしかに驚くべきことであったが、もっと驚くべきことは、教育界がこの調査結果に少しも驚かなかったことである。
もしこれが学校の給食のばあいだったらどうなっていただろうか。ある日のある学校の給食で半数以上の子どもが消化不良を起こしたとしたら、たぶん大騒ぎになっていただろう。ただちに調査が開始され、材料の仕入れ先から、料理人の健康状態まで徹底的に究明されるにちがいない。ところが子どもの精神的給食ともいうべき授業で消化不良を起こしても誰一人驚かないのはなぜだろうか。
それはいまの学校がすべての子どもを賢くするという目標を事実上放棄して、何パーセントかの子どもが落後するのは当然であり、その落後する子どもを選び出してそれを切り捨てることを学校の任務とさえ考えているからである。そのような現実のなかでもっとも冷い待遇を受けているのはいうまでもなく障害児である。
最近ようやく障害児教育の重要性がみとめられるようになったことは喜ばしいことであるが、その内実に立ち入ってみると必ずしも満足できる状態ではない。一個の人間としての障害児の権利がみとめられた、というより、普通学校の授業の邪魔になるからこれを別のクラス、別の学校に入れて隔離しようという考えが強いのである。
盲、聾、ちえおくれ、身体障害等の子どもは少なくないが、その一部分しか学校に行くことができないでいるし、また学校に通っている子どもも、適切な教育を受けているとは言い難い。本来ならば普通児にくらべて特に手厚い教育を受けなければならない子どもたちが、厄介者あつかいされている、というのがいつわりのない実情である。
このような実態を改めていくことは今後の教育の重要な課題であるが、このためにはまず障害児が十分に教育可能であることを事実によって証明して見せる必要がある。
そのことを何よりも鮮やかに立証してみせたのはヘレン・ケラーであり、彼女の教師アン・サリバン女史であった。
ヘレンがサリバンの手によってどのような教育を受け、どのように言語を獲得していき、人間らしい思考力と行動を身につけていったかを知ることは、まさにその証明となるはずである。
盲、聾、唖という三重の障害を背負ったヘレンが、どのような人間にまで成長したか、その結果だけを見れば、たしかに奇跡というほかに言いようのないことであるかも知れない。
ヘレン・ケラーは数回わが国を訪れ、大きな感動をまき起こしたが、どちらかというと奇跡を目撃したいという好奇心の対象となっただけで、着実な障害児教育の出発点とはならなかったようである。そのことは、本書のような貴重な記録が今日まで訳出されなかったことによっても、立証されているとも言えるだろう。
本書を詳しく読めば、ヘレン・ケラーが決して奇跡の人などではなく、すぐれた教育の結果であることが分かるだろう。
そこにはたしかに二つの恵まれた条件があった。
その一つは、ヘレンから光と音とを奪った幼時の熱病は、彼女のすぐれた脳には一指も触れることがなかったことである。
第二に、ヘレンの師サリバン女史が稀にみるすぐれた教育者であったことである。
その二つの条件がそろっていたことは一つの僥倖であったかも知れないが、それから先は、きわめて合理的な教育法の生み出した当然の結果であったというべきであろう。
そこでどのような教育が行なわれたかについて私たちはつぎの二つの記録を持っている。一つはヘレン・ケラー『わたしの生涯』(角川文庫)であり、もう一つはここに訳出された『ヘレン・ケラーはどう教育されたか――サリバン先生の記録――』である。
前者は教育を受けた側の記録であり、後者は教育を授けた側の記録である。このように、一つの教育の営みを両方の側から記録した例は珍しいことであるかも知れない。
この本によってサリバンという人がどのようにすぐれた教師であったかを知ることができるだろう。
絵画とか、音楽には天分というほかはないような特別な才能を持った人がいるが、教師にもそういう人がいる。
教室のなかで、子どもたちの表情や動作から、瞬間的に子どもたちの心の動きを洞察して、臨機応変の処置のとれる人がいる。そういう人はやはり生まれつきの天分をもった人というほかはない。サリバン女史はそのような天分を最高度に持ち合わせた人だったらしい。
ヘレンと会った最初の日に、一服する間もなく、サリバンは doll という字を教えようとするが、これなども普通の人にはできないことである。
また甘やかされていたヘレンをきびしく訓練するために家族から引きはなして、一軒家に住むことにする。これも二十歳を越したばかりの若い娘にはなかなかできないことである。
ヘレンが言葉を獲得していく過程が詳細に記録されているが、これも幼児の言語教育に大きな示唆を与えるものであろう。
とくにおもしろいのは、ネズミが出てきたときのエピソードである。サリバンはこの小さな偶然事をすぐさま教育の材料として利用してしまう。
この本は障害児の教育にたずさわっている人々にとって汲みつくすことのできない教訓を提供してくれることはもちろんであるが、もっと広く、普通児の教育にたずさわっている人々にも数々の示唆を与えてくれるだろう。
この二人の記録を併せ読んだ後ですべての人はつぎのように感ずるであろう。
「この人を見よ。
ここにすばらしい二人の人がいる」と。
一九七三年二月 /遠山 啓
-
 明治図書
明治図書