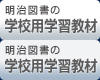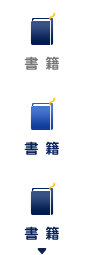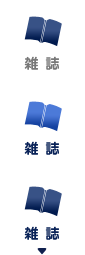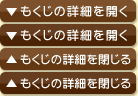- まえがき
- 第一章 国語科の領域の中身は何であったのか
- 一 問題状況
- 二 活字で印刷された身のまわりの読み物は、教科書だけだった
- 三 戦前(太平洋戦争中)の国定教科書の一例
- 第二章 国語についての知識よりも豊かな言語経験か
- 一 「五里霧中」状態での新しい方向の模索
- 二 全否定の上での、茫漠とした考え方
- 三 作業単元と教材単元の「渾然一体」の念願とその行方
- 四 国語科の領域はどのようにあるべきか
- 五 教科書の教材ジャンルの微妙な変化と「国語学力」問題
- 第三章 国語科教科書を言葉の教科書にする試みの無残な結果
- 一 その志や良し
- 二 教科書の言葉教材と児童生徒の言語生活の実際との格差
- 三 〔言語事項〕の存在意義
- 四 〔言語事項〕とは何か
- 第四章 国語科各領域の現在の問題
- 第一節 文学教材の読み方学習指導の問題文学教育の問題
- 一 教材としての文芸作品の変遷にどう対処するか
- 第二節 説明文の教材論と授業論の半世紀
- 一 国語科教科書の理科に関する事柄について述べた文章と理科の教科書の文章
- 二 国語科の説明文教材と理科との混同
- 三 実物観察「信仰」の弱点
- 四 読んで分かる理解、見て分かる理解
- 五 昨今の問題一つ
- 第三節 生活作文と学習作文――作文活動と文章の書き方(作文)学習は異なること――
- 一 作文活動と作文学習の違い
- 二 生活作文と対照的な学習作文の登場
- 三 「書くこと」(作文)の年間指導時間数の設定の意味
- 四 書くこと(作文)の学習指導が到達した現在
- 五 「先生、書くことがない」「どう書いたらよいか分からない」のは、当たり前のことだ
- 六 「書くこと」についての学習指導の具体例
- 七 再び評価の学習とは、何をどうすることか
- 八 「『うそっぽ』を書こう」という提言は無意味なことか
- 第五章 教材としての方言の運命
- 第一節 これからの方言の教材観と教材論の行方は
- 一 方言意識の希薄化の動向
- 二 標準語の文章が、スラスラと音読できない
- 三 国民学校時代の標準語教育
- 四 方言札という負の遺産
- 第二節 これからの方言の教材化のむずかしさ
- 一 現在の方言教材の動向とその行方
- 二 方言の良さの賛美は「逆差別」ではないのか
- 第六章 教材としての敬語のあり方
- 第一節 敬語は、うやまう気持ちを表す言い方なのか
- 一 敬語は、「至誠の心」を表すためのものか
- 二 敬語のきまりのゆれ敬語教材の「復活」の根拠の脆弱さ
- 第二節 これからの敬語の教材化のむずかしさ
- 一 袋小路に追い込まれた敬語教材
- 二 敬語表現から「敬意表現」へ
- 三 他人との心理的距離の調節をはかる敬語
- 第七章 「和語・漢語・外来語」という語彙指導の教材づくりは、何時まで続くのか
- 第一節 和語、漢語、外来語の教材観は、百年前の考え方なのだ
- 一 単語と語彙の意味は、同じなのか、違うのか
- 二 「〜話や文章の中の語彙について関心を持つこと」と言われても…
- 三 教科書教材の言語事項としての語彙の教材の現在
- 四 これからの語彙教材づくりの可能性は
- 第二節 語彙の知識をふやすことが、思考の深まりに連動するか
- 一 「区別」と「差別」の意味の違い
- 二 「あける」と「ひらく」の意味
- 三 窓を開(あ)ける、心を開(ひら)く
- 第八章 文法という役に立たない知識学習の残酷さ
- 第一節 なぜ実用の役に立たない文法知識の「体系」ができあがったのか
- 一 「おっしゃいました」は、なぜ一文節なのか
- 二 六十年後の「文節」
- 三 〔言語事項〕とは、文法事項のことか
- 第二節 理屈の知識よりも実用の役に立つ文法の必要性
- 一 本文「内容」と無関係な知識を問う文法問題
- 二 混迷を重ねる「文法」の先行き
- 三 文法知識は、読解の役に立つか、立たないか
- 第九章 話すこと・聞くことが学習指導になる道筋
- 第一節 話すこと・聞くことが、学習指導になる道筋
- 一 用語の不安定なままの半世紀
- 二 『コトバノオケイコ』とラジオの普及
- 三 「話すこと」「聞くこと」指導の一つの到達点
- 四 音声言語学習指導のこれからの問題点
- 五 文字言語の機能との対比における音声言語学習の必要性
- 第二節 音声言語の教材論において、肉声の長所・短所の両方に、なぜ「気配り」をしないのか
- 一 「話すこと・聞くこと」から「音声言語」へ
- 二 話し言葉指導の歴史は「点」で見るか「面」で見るか
- 三 「戦前」「戦後」の話し方指導の相違点
- 四 「話すこと」「聞くこと」指導はふるわなかった
- 五 音声言語を文字言語との関係で見る視点の必要性
- 六 「癒し」の肉声と悪魔の呪いの肉声
- 第三節 音声言語の本質的特徴の把握のむずかしさ
- 一 音声言語の特徴を明らかにする一つの教材づくり試論
- 二 「理性を越えて、人間の生理の最も奥深い層にまでじかに届くような」声とは
- 三 癒しの声と呪いの声
- 第四節 言葉とそれが指すもの「記号と意味」との種々の関係教材化の問題
- 一 「南セントレア市」は、なぜ実現しなかったか
- 二 言葉の意味の種々相を知る素材
- 三 名付け(名をつける)の問題か、実態の改善の問題か
- 四 適切な言葉による名付けのむずかしさ
- 第五節 言語事項の授業に「日のあたる」時は、何時来るのか
- 一 言葉の指導に手薄な国語科
- 二 言語事項の国語科での位置づけ
- 三 言語事項の授業の軌跡
- 四 文法、敬語、方言の学習指導の先行き
- 第十章 国語科授業展開上の問題点
- 第一節 百花繚乱か百鬼夜行か指導過程論の隆盛とその意味
- 一 授業参観では、先生を見るのか、学習者を見るのか
- 二 『国語の力』は、指導過程の方法論の書なのか
- 第二節 指導過程論と授業論
- 一 指導過程の方式の限界
- 二 基本的指導過程論は無意味なのか
- 三 百花繚乱か百鬼夜行か
- 第十一章 授業研究という考え方の成り立ち
- 一 よい教材と優れた指導過程は、よい授業を保障するか
- 二 「名人芸」の授業を行なう一人と「十人並み」の授業を行なう多くの人
- 三 指導過程と授業の展開との関係
- 第十二章 評価が授業のあり方と関わる道筋
- 一 評価の研究の細々とした道筋
- 二 評価が、広く深い「常識」になった日
- 三 相対的評価は「悪代官」だったのか
- 四 相対評価から絶対評価への転換の問題
- 第十三章 言葉の正しい使い方の教科か、認識力の育成の教科か
- 一 国語科は、偽装(camouflage)された「修身」か
- 二 「言語生活の向上」の消滅(昭和四十三・一九六八年版学習指導要領国語科編)
- 三 「西尾・時枝論争」の無意味について
- 四 「四面楚歌」の国語科の目標
- 第十四章 国語科教育の本質は、言葉の妥当な使い方の学習にあること
- 第一節 「言語文化」という概念の無意味について
- 一 「言語文化」の意味
- 二 垣内松三の言語文化の規定
- 三 西尾実の言語文化論の問題
- 四 言葉についての学習教材と授業を
- 第二節 国語科の領域の新しい形成への苦闘
- 一 生活単元学習の後退
- 二 「指導計画作成および学習指導の方針」の登場と引退と再登場
- 三 「継続学年」の、平成十年版における「復活」
- 第三節 戦後半世紀の国語科教育史は何を意味するか
- 一 「木に竹を接ぐ」改革
- 二 国語科教育が言語の教育になる可能性〔言語事項〕という「障害」を乗り越えられるか
- 三 総合的な学習が要請される「不幸な」状況
- あとがき
まえがき
小学校から大学まで、国語科教育は、個々人の修養学習、認識力の深化・拡大、人間形成のための教科であった。私は、現在の国語科教育上の問題は、私の小学校児童の時代から今日まで、どのような状況の中を過ごして来たかということとの関連で考察することを行なって来た。私の小学生時代は、今から半世紀も前のことである。そんな「はるかな過去」を追懐しても、《老人のたわごと》だとして一蹴されたこともある。しかし私は「昔はよかった」などと言うつもりはない。現在の国語科教育上の問題は、いかに過去の考え方を踏襲しているかということを私は折々につぶさに感じて来た。
一九四〇年代までのわが国の過半数の小学校には、活字印刷の文献は教科書しかなかったのだ。当時の、おびただしい数の「小作農」の家庭には、ラジオもなかったし、新聞、雑誌などの〈非実用品〉を購入する余裕はなかった。例えば『赤い鳥』などという「児童文化雑誌」は、存在していなかったに等しい。それは一部の限られた「人」の世界の物であった。教科書の意味は、現在のような「書物の一種」とは異なっていた。それをいまさら非難するつもりはない。ただ「できる児童」にとっての読み物は、その当時の「国語」「修身」の教科書だけであり、高学年になると「国史」「地理」の教科書があった。教養読本の趣を濃厚に帯びていた。言わば太平洋戦争中といえども、「運命的な状況」の中で文部省によって教科書は作られたし、私ども小学生だった者は、本気になって学んだ。
しかし現在の学校教育における国語科教育環境は、半世紀前までのそれとは、大きく変わっている。現在との関連の有無を知るためにも、「過去の推察」が必要なのである。現在の地点から見て「推察した過去」との対比によってしか、現在および将来の見通しは立たない。本書で特に考察したのは、一九六〇年代以降の国語科教育の問題である。明治六(一八七三)年以来、特に一九四〇年代の太平洋戦争中の国民科国語時代の国語科教育を如何に克服できるかに今後のあり方は係っている。ところが否定すべき因習を私達は、如何に引きずっているかについて考え込まざるを得ない。私が本書の各論を通して訴えたかったことは、国語科教育を本来の意味で、言葉の学習教科にしたいことである。それに尽きる。
国語科教育を言葉の学習教科にしようと私は今までも随所で提唱して来たが、しかるべき反応があったとは思えない。あえて言うと、「お前は、うすっぺらな言語ドリル学習でよいと言うつもりか」、「言語そのものは、児童生徒にとっての興味・関心を惹く教材にはなりにくいのだよ」と非難され、挙げ句の果てには、「『認識力の深化拡大、人間形成のため教科』ではないなどと言うと、権力側にとって〈思う壺〉だよ」とまで言われて来た。そのような批判、非難や忠告は当てはまらないことを、国語科教育の実態の一つ一つを通して考察し、それぞれの問題に提案を述べたのが本書である。
一九七三年の『説明的文章の指導過程論』(明治図書出版)の上梓以来、およそ四十年間、当初から問題として来たことで、最後まで残った問題について考察した。この度も識者の批正を得る機会に恵まれれば、幸い、これに越したことはない。
二〇〇七(平成十九)年五月十四日 /渋谷 孝
-
 明治図書
明治図書