- 特集 理科の基礎基本―楽しく学べるアイデア
- 新学期:あなたのクラスの“基礎基本”実態把握のヒント
- この植物シートを見て―いくつ発見できたらどのランク
- 植物なかま分けシートを利用して
- /
- この昆虫を見て―いくつ名称が言えたらどのランク
- ネーミング力を調査する
- /
- この実験計画―いくつ予想ができたらどのランク
- 科学的な予想の能力は数だけでは測れない
- /
- このモノづくり計画―いくつ用意するものがいえたらどのランク
- 3年「電気」「磁石」,4年「空気と水」
- /
- “基礎基本を意識”した学習計画づくりのアイデア
- ノートづくりで指導する基礎基本
- はじめは1つの実験からマネージメント
- /
- 育てたい資質・能力を具体的にして
- 3年「光の性質」・4年「水のすがた」
- /
- 5年「振り子の授業」の導入で学習計画をつくる
- 坂道実験はいかに?
- /
- まず教科書通りにやってみる
- 5年「ものの溶けかた」
- /
- “基礎基本”につながる地域教材・発展教材開発のアイデア
- 3年地域教材・発展教材開発のアイデア
- 植物のからだを調べよう
- /
- 4年地域教材・発展教材開発のアイデア
- なかよし初見日表「季節と生き物」
- /
- 5年地域教材・発展教材開発のアイデア
- 流れる水のはたらき・てこのはたらき
- /
- 6年地域教材・発展教材開発のアイデア
- 夏は「ジャガイモ」+冬は「流氷」で多面的考察力を育てる
- /
- 中学1分野地域教材・発展教材開発のアイデア
- 燃焼・電流・状態変化
- /
- 中学2分野地域教材・発展教材開発のアイデア
- 植物の体のつくりとはたらき
- /
- 基礎基本を楽しく学ぶアイデア:到達度評価にも使える指導のポイント―1分しゃべれる・400文字書けるなどの目安づくりのヒント―
- 3年「植物の育ち」基礎基本を楽しく学ぶアイデア
- 絵日記をもとにスピーチ、「紙芝居」にも
- /
- 4年「空気」基礎基本を楽しく学ぶアイデア
- 『自由試行』で子どもが熟中する授業
- /
- 5年「溶解」基礎基本を楽しく学ぶアイデア
- 教科書実験に準備物を増やしノートチェックする基礎基本
- /
- 6年「電磁石」基礎基本を楽しく学ぶアイデア
- 子どもたちに「好きにさせる」
- /
- 中学1分野「光」基礎基本を楽しく学ぶアイデア
- 凸レンズを手にして
- /
- 中学2分野「植物の観察」基礎基本を楽しく学ぶアイデア
- 総合的にとらえ,研究のプロセスを獲得させよう
- /
- “この発表”の基礎基本クリア度=あなたならどう評価する?
- この野外観察の報告=何があったら基礎基本クリア
- 子どもたちに評価基準を示す
- /
- この実験評価=何があったら基礎基本クリア
- 「もし」があれば基礎基本クリア
- /
- この自由研究=何があったら基礎基本クリア
- 問いを持って収集活動し,比較・関連づけをしているか
- /
- 小学校科学クラブのフレッシュネタ
- ペットッボトルの飛行リング
- /
- 中学校総合的学習で使えるフレッシュネタ
- ポートフォリオの言葉のつなぎ
- /
- 理科好きをつくる環境づくり
- 理科室に水槽やプランターを
- /
- 今月の本棚 わたしのお勧め本
- 『X―ファイルに潜むサイエンス』アン・サイモン著
- /
- 理科における実現状況の評価をどう進めるか―改革のポイントはここだ (第2回)
- 理科の内容のまとまりごとの評価規準と評価方法
- /
- 子どもは学習場面をどう考えているか (第2回)
- 小学生の考えが深まる理科学習場面
- /
- 自分の頭と体で考える到達度評価 (第2回)
- 生きる力とは何か?
- /
- 新理科教科書+発展学習 (第2回)
- 3年/葉っぱの迷路
- /
- 4年/「春のまとめ」の発展型発表
- /
- 5年/コイの卵とビデオと妊婦さんをプラスする
- /
- 6年/環境単元いつやるの?
- /
- 中学1分野/LEDでソーラー電卓を作ろう
- /
- 中学2分野/家庭で確かめる
- /
- 編集後記
- /
- 100円ショップで科学手品 (第2回)
- いろいろな電池に挑戦
- /
編集後記
○…新教科書が薄くなったことに関連して,骨だけになった…とか,いや,肝心の基礎基本さえ薄くなり,理科の学力が崩壊する…という危惧さえ広がっているー現在の理科を取り巻く状況は,こんな形ではないかと思います.
たしかに,どうしても押さえなければならない概念というものをはずしては,いくら楽しい学習だと言ってもなんにもならないこともまた確かでしょう.
ですから,基礎基本をしっかり,しかも楽しく学ぶことができる授業を展開できれば,こんな善いことはないわけです.
ですから,この問題はあるいは永遠の課題かも知れません.
が,しかし,それに向ってさまざまな工夫がなされていることもたしかではと思います.
本号はそんな工夫のポイントをご紹介いただければと願いました.
(樋口雅子)
-
 明治図書
明治図書















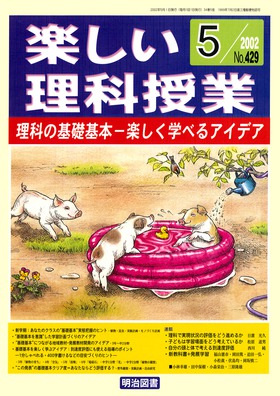
 PDF
PDF

