- 特集 1年間のまとめ「楽しい学習イベント」24
- 1年間のまとめ:最後の授業が盛り上がる“学習イベント”
- “エクセレント&エレガント”コンクール―こう実施する
- /
- めざせ理科学習名人―こう実施する
- /
- ノートコンテスト―こう実施する
- /
- 学習キーワード探し―こう実施する
- /
- 使い捨てカイロでゆで卵づくり体験―こう実施する
- /
- まちがい探しゲーム―こう実施する
- /
- 1年間のまとめ要素入り“学習クイズ”
- 3年
- /
- /
- 4年
- /
- /
- 5年
- /
- /
- 6年
- /
- /
- 中学1分野
- /
- /
- 中学2分野
- /
- 1年間のまとめ:印象に残る“オススメ実験”
- 3年
- /
- /
- 4年
- /
- /
- 5年
- /
- /
- 6年
- /
- /
- 中学1分野
- /
- /
- 中学2分野
- /
- 1年間のまとめ確認の“面白ミニテスト”
- 3年
- /
- /
- 4年
- /
- /
- 5年
- /
- /
- 6年
- /
- /
- 中学1分野
- /
- /
- 中学2分野
- /
- 小特集 読み聞かせ:ノーベル賞受賞者物語
- 湯川秀樹/日本人で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹
- /
- リンダ・バック/女性ノーベル賞受賞者たち
- /
- 小柴昌俊/理科好きにする“教師の力”
- /
- 江崎玲於奈(小学生向き)/失敗してもあきらめないことが成功の鍵
- /
- 江崎玲於奈(中学・高校生向き)/自分の個性を生かすことが創造性につながる
- /
- とっても楽しい理科工作 (第12回)
- エコワットを使った白熱灯型蛍光灯の節電効果の検証実験
- /
- 新指導要領で授業をつくる―焦点はここだ (第12回)
- 理科の新しい内容区分の考え方
- /
- 読解力を鍛える理科テスト問題づくり (第12回)
- 小学校/日々の授業で「記述」を鍛え,さらにテストで強化する
- /
- 中学校/入試問題で読解力を鍛える
- /
- 理科好きにする実験観察のヒント (第24回)
- 金属の融解と氷つくり
- /
- 〜鉛のペンダントつくり/水が凍る瞬間を見よう!〜
- わかる実験・わかる教え方―基礎基本が定着する授業づくり― (第12回)
- 子どもの気づきから論理を形づくる
- /
- 〜水溶液の性質〜
- 編集後記
- /
- こだわり教師の実験教室―100円ショップで実験ネタ― (第12回)
- 蛍光ペンで書いた文字を宝探し
- /
編集後記
○…先生にとって,この1年間はどんな年でしたでしょうか.
この数年の教育界は,まさに激動の時代といっても過言ではない世論の批判の矢面にたたされっぱなし―という状況におかれています.
それにしても,昨年は,国際的な学力調査の結果から,日本の子どもの学力が低下しているという衝撃から始まり,ここに来て,必修科目の未履修問題や,いじめ問題と,ひっきりなしにさまざまな問題が起っています.
ところで,理科授業をめぐっては,指導要領の改定で授業時数が増える?とか,「A,B,Cの区分」が変わるとかの憶測は流れていますが,未だに,いつ改定の方向が発表されるのかもはっきりしていない状況です.
ま,早い話,現場では,最早,指導要領はあまり関心をもたれない存在になっている(未履修問題がこれだけ広く行われているということは,それを裏づけているともいえる)のかも知れません.
ところで,本号が出る頃は,この1年のあゆみを総括する時機でもあります.
最近は,授業内容の定着を図る,指導事項がちゃんとついているかどうか,子ども自身が自己確認できるような授業場面を用意し,楽しく確認できるような学習イベントを構想する先生が増えているようです.
そこで本誌では,1年間のまとめを,楽しい学習イベントとして,どういう活動を用意していけばよいのか,ご紹介いただきました.
(樋口雅子)
-
 明治図書
明治図書















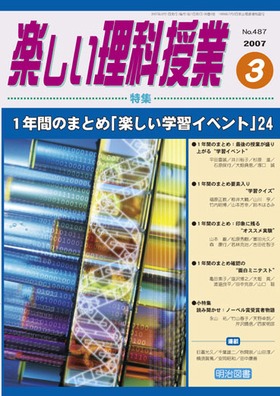
 PDF
PDF

