- 特集 生活指導入門―大きい子ども集団と小さい子ども集団―
- 巻頭メッセージ
- 子どもたちが求める公共性と学校づくり―相互信頼をネットワークによる民主的集団づくり―
- /
- 特集1 子ども集団づくり
- インタビュー 「子ども集団づくり」について考えよう―竹内常一氏に聞く
- /
- 特集2 生活指導のイロハ
- ほめること・叱ること―子ども・グループをどう評価するか―
- 子どもの気持ちにフィットし、子どもどうしをつなぐ評価を
- /
- 指示すること・命令すること
- 子どもの行動をつくるイロハ
- /
- まず、やってみせてやらせてみた
- 心地よい集団のトーンを創りだすために
- /
- 励ますこと・助言すること
- 「あたなが主役」だからこそ
- /
- ケアーすること・管理すること
- 子どもとの向き合い方のイロハ
- /
- 聞くこと・話すこと
- まず、聞いて、受け答えする仕方
- /
- 指導のアイデア
- 教師の引き出しと雑学のススメ
- /
- 特集3 〈子ども集団づくり〉が描き出す地平
- 孤立から対話へ
- *対話とその方法―「対等」な関係をさぐっていこう
- /
- 子ども集団のリーダー
- *少数者に応答するリーダー集団―正樹と、直子たち
- /
- 子ども同士の関係をつくり、関係性を変える
- *グループづくり・班づくり―知ることで変わること
- /
- 子どもの生活現実からネットワークをつくる
- *子ども集団のネットワークづくり―有志ダンスチーム「忍風」が巻き起こした風
- /
- 大人・社会との出会い直し
- *社会と向き合う子ども集団づくり―政治的判断力と子どもたち
- /
- 子育て・共同をつくる
- *親(保護者)が参加する子ども集団づくり
- /
- 学びが紡ぎ出す子ども集団
- *学びと子どもたち
- /
- 子ども集団と学校づくり
- *子どもの意欲と学校の在り方―学校って僕らの力で変わるね!
- /
- 子ども集団づくりが描き出す地平
- *生活の創造と自治の全域的展開
- /
- コーヒータイム ちょっとひといき
- こってます。子ども達の写真に
- /
- 先生、算数の時間さ、つまんないから体育にしてよ
- /
- 赤信号 みんなで渡るな オレはオレ
- /
- 「今、怖い気持ちが一杯です。」
- /
- オリジナル写真ハガキで応答発信
- /
- 第45回全生研山形大会 常任委員会報告
- 人とつながる山形大会
- /
- 第45回全生研山形大会 現地実行委報告
- ゆうきある実践を ゆめある仲間と ゆっくり語り合おう 山形の湯で
- /
- 編集後記
- /
巻頭メッセージ
子どもたちが求める公共性と学校づくり
――相互信頼とネットワークによる民主的集団づくり――
常任委員 折出 健二
生活指導の可能性
長年にわたって、「公共」は権力による民衆の自由の制限という性格が強いものとされ、「公共」の押しつけにたいしては既存の制度・機関の民主化こそが重要だと、民間教育研究運動ならびに市民的運動では捉えられてきました。
しかし、いま、「公共」は市民的自立のふかまり・ひろがりによって、子ども・父母・市民と教職員が「共につくる公共(相互信頼による市民のための自治)」の世界を学校の内外に実現していく、というように変わりつつあります。この変革の意義をとらえ、そこに不可欠の、対話と討議の身近な民主主義的関係性を生活指導の教育内容として受け止め、それにともなう子ども観のとらえなおしと〈子ども集団づくり〉論を深めること、ここに全生研運動の斬新さ、新たな地平への果敢ないどみかかりがあるといえます。
新自由主義による協力・共同の社会の解体化があらゆる面で進むとき、これを問題としつつ、同時にこの否定的現実をバネに、むしろ根源的な諸要求でむすばれる共同と公共的空間をたちあげていく学校づくり・子ども集団づくり・地域づくりにこそ、わたしたちの教育研究運動の未来があります。
「学級集団づくり」から子ども集団づくりへ
「学級集団づくり」は、集団による決定という制度プロセスに着目し、その民主性・集中性・文化性を育てることを追求してきています。
しかし、今日、子どもたちは制度としての学級や学校を相対化し、時には拒否することさえしながら、他者(なかま)発見・自分発見をはげしく求めています。その背景にはいわゆる「個人責任」原理に立つ競争の徹底・拡大のもとで、子どもの生活環境破壊がすすむ現実があります。教育行政の側には、教育制度の弾力的運用を次々と発するものの、子どもたちにとっての安定した学びと発達の拠点づくりを避けてきた根本の問題があります。他方、これらと交差しながら、父母・市民の中から、学級や学校を制度の外側の視点からとらえなおし、教職員とともに権威的で権力的な学校体質を、市民社会にひらかれた、市民どうしを結ぶ公共性の世界に変えていこうとする動きも現れています。
このように、教育を取り巻く状況は、今日、社会的にも学校制度上もはっきりと転換してきています。この現実を生きるちいさな市民的主体である子どもたちが、制度としての学級・学校を相対化するようになっていることは何を意味するのでしょうか。
子どもたちが求める公共性
子どもたちは、学級や学校という制度枠にとらわれない関係性をさぐり、自分たちの意見表明の可能性をもとめているのです。制度のもとめる価値規範や行為の基準を超えて、自分たちがいま切り開こうとしている生き方をみずから定義する試みをしています。その定義(自分の存在価値をみつめること)の試みは、言葉だけではなく、身体や、関係性そのものによっても行われています。
そうだとすれば、かれらの自己定義を子ども集団にひらくように促し、そこにある共同的な〈問い〉を契機に自分たちの「明日」を定義し直す(思想化する)ことを通して、たしかな相互信頼とネットワークによる集団をつくりだしていくことができます。
「学級集団づくり」概念だけで捉えるのではおさまりきらない研究課題がここに発生しており、それを全生研は〈子ども集団づくり〉として創造的に編み出しているのです。
それは、子どもたちがいま多様なネットワークをとおして、自分たちが主人公である生活と学びの公共性とは何かを問うものであると同時に、これに応えながら、教職員も子どもの生きる目線から学校の公共性を問い直していく営みなのです。
-
 明治図書
明治図書















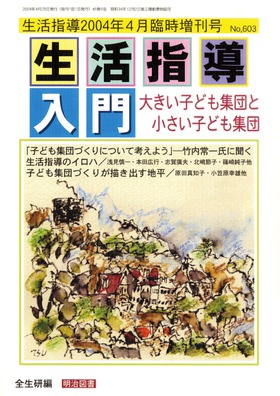
 PDF
PDF

