- 特集 子どもが伸びたと実感した時
- 提言・子どもが伸びたという実感―何を基準に判断するか
- 達成感を基礎に、意欲的になるとき
- /
- ユーモアあふれる文章表現がみられるようになったとき
- /
- 子ども自身の内部に主体的な自己を蓄積する
- /
- 小さな変容が見えること
- /
- 学級づくりの過程で子どもが伸びたと実感した時―小学校
- 躾の三原則が達成できたときである
- /
- 「交流」と「励まし合い」で子どもが伸びる
- /
- 級友の良さを認めあえる
- /
- 学級づくりの過程で子どもが伸びたと実感した時―中学校
- 教室がシンとなり、鉛筆の音だけが響いた一〇分間
- /
- 子どもが伸びたと実感した時
- 国語の場合
- 一年の終わりに感動する事実を作る
- /
- 指名なし討論ができるようになったとき
- /
- 山を越える―量が質へと転換するとき
- /
- 算数・数学の場合
- 私の必需品・百玉そろばん!
- /
- それは、子どもが自分の力で問題解決ができるようになった時
- /
- 褒めて励ますことで生徒はどんどん伸びる
- /
- 社会の場合
- 「よく書けるようになった」とレポートを読み返すとき
- /
- ノートづくりで子どもの成長をとらえる
- /
- “予定外”の授業が生まれる雰囲気
- /
- 理科の場合
- 観察した項目が増える
- /
- モノの持ち込み・ノートの変化・テストの向上
- /
- 意欲、こだわりが表れる
- /
- 図工の場合
- 野放しの授業では、「できる子ができるようにならない」TOSS酒井式との出会いがA子を変えた
- /
- 「すべての子」に「伸び」を期待できる方法は
- /
- 酒井式描画指導法で「できそうにない」「難しい」と思っていたことを克服させたとき
- /
- 体育の場合
- 成功体験の繰り返しが、子どもに3つの変化を起こす
- /
- 教えればできる。教えないからできなかった。
- /
- 超苦手なA君がこうもりふりおりを達成
- /
- 楽しいクラスをみんなで創る (第4回)
- 分かるからこそ楽しいクラス!!
- /
- 心を育てる言葉かけ
- 『心』を味わうと「春の味」がする
- /
- 7月の仕事
- 充実した夏休みにするための段取り
- 事前指導の充実を図る
- /
- 拙速巧遅に如かず
- /
- 書くことを楽しむ夏休みの葉書作戦
- /
- 見通しを持った夏休みにするために
- /
- やったことを増やしなさい
- /
- 学期末保護者会成功に向けて
- 保護者会は授業参観とセットで
- /
- 保護者へのお土産を用意せよ
- /
- 一味違った保護者会をしよう!
- /
- 具体物を提示して保護者を納得させる
- /
- 事前の準備とちょっとした工夫で成功させる
- /
- 学級の教育力を生かす学習集団の再構築 (第4回)
- 学力の向上を支えあう学級づくり
- /
- 子どもは仲間集団によって育つ (第4回)
- クラスを越えた遊び集団の機能
- /
- 「学級経営力」を高める私の修業 (第4回)
- 学級崩壊の再建はリズムとテンポで空白時間を廃止するところから始めよ。音楽のプロもそれを同様に実証していた
- /
- 酒井式で子どもの絵が変わる (第4回)
- 酒井式マンガ学習のモデルを提起します
- /
- 効果的な勉強法のすすめ (第4回)
- 小学校低学年/合唱指導で生き方を教える
- /
- 小学校中学年/地図帳の活用能力を高める
- /
- 小学校高学年/一度覚えたことを忘れないようにする勉強法
- /
- 学級担任の責任を問う (第4回)
- 一年生担任の責任は重い
- /
- 編集後記
- /
編集後記
〇…子どもは絶えず変化すると言われています。昨日の子どもは今日の子どもではないと言われていても、この子どもの変化をとらえることは容易ではないようです。いじめから不登校、非行、学業不振など問題の背景には、必ず子どもの変化があると言われています。しかし、この小さな変化をとらえることは難しいようです。そのために絶えず「子どもに迫る」ことの必要が強調されています。
〇…子ども一人ひとりの興味や関心、才能、能力、性格、感性、意欲、態度、思考力、判断力、さらには技能、表現、知識、理解などを把握するためには、子どもの成長・変化をとらえる「確かな眼」が必要とされているわけです。
〇…子どもの成長・変化をどう見るか。まずは日常の教育活動に注目したいものです。第一に、授業中の学習活動の様子の観察も大事になるでしょう。第二に、ノート、学級日誌、日記、成績物などの点検、第三に、友だちからの訴えや他の教師からの助言なども無視出来ないでしょう。さらには累積された記録や検査票と比べて見ることも成長・変化を知るために必要でしょう。
〇…学級集団内での個とのかかわりも無視出来ないでしょう。やる意欲がない、集中力に欠けている。友だちの中で遊ぶことが出来ない、テストの結果を極端に気にするなど、注意を怠ってはいけない問題が必ずあるはずです。子ども一人ひとりの成長・変化を見取る教師の姿勢に問題があるとの指摘もあります。固定した概念や既成の学説にとらわれていて、型にはまった物差しで子どもを見ていないかとする警告です。
〇…指導の過程を大事にしていかなければ、子どもの成長・変化を発見することは出来ないといわれるゆえんです。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















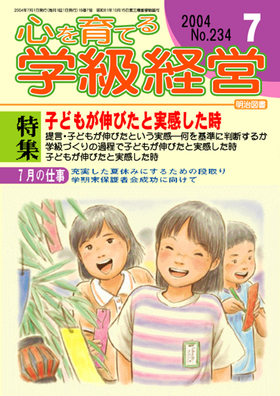
 PDF
PDF

