- 特集 ネット時代の「言葉のしつけ」を考える
- 提言・ネット時代の「言葉のしつけ」を考える
- しつけからメディア教育へ
- /
- 日常言葉の正しい使い手に―自己中心でなく相手本位に―
- /
- 「言葉のしつけ」の不在が原因
- /
- 「君たちがいて私もいる学級」づくり―助け合い救い合う心の言葉―
- /
- 正しい言葉遣いの環境をつくる
- /
- 学級で教える「言葉のしつけ」
- 下学年児にはこれだけは教えたい
- 自立を促すことばのしつけを
- /
- 上学年児にはこれだけは教えたい
- 心を通わせる三つの言葉
- /
- 中学生にはこれだけは教えたい(1)
- 「初対面の敬語」と「受信の危機管理スキル」を教える
- /
- 中学生にはこれだけは教えたい(2)
- 明るい言葉を使いなさい、人生が明るくなります
- /
- 国語の授業で教えたい「言葉のしつけ」
- 日本語文化の魅力に気づかせる〜正しい日本語の使い手を育てるために〜
- /
- 学習用語で子供が向上的に変容する
- /
- 「文化」と「コミュニケーション」の視点から
- /
- 道徳・特別活動で教えたい「言葉のしつけ」
- 誹謗・中傷に歯止めをかける指導
- /
- 「コミュニケーション&心配り・感謝の心」の初歩を育てるネタ
- /
- 一人の人間の後ろには、多くの人間の思いがあるのだ
- /
- 「言葉」を豊かにする学級での指導
- 伝え合いが言葉を育む
- /
- 日常生活で繰り返し教える!
- /
- 「戦争の授業」の子どもを追って
- /
- 交流によって言葉を豊かにする
- /
- 「言葉のしつけ」5つの原則
- /
- 「話し言葉」を集団で楽しむゲーム
- コソコソおしゃべりを楽しもう
- /
- ポイントは、「楽しく」「繰り返す」こと
- /
- コミュニケーションの楽しさ実感
- /
- 三つのヒントと三つの質問で言葉当てゲーム
- /
- 「口パク」で伝え合う
- /
- 楽しいクラスをみんなで創る (第9回)
- 「学校での一日」はストレスのない一日
- /
- 心を育てる言葉かけ
- 「百の努力、千の名人」
- /
- 12月の仕事
- 二学期の反省・自己評価のさせ方
- 一週間続けて行う自己評価
- /
- あまり欲張らず、基本的なことに絞る
- /
- チェックシートと詰めの作業で
- /
- 自信につながる反省・評価
- /
- 明確な自己評価をさせる
- /
- 二学期の学級経営をチェックする
- 「体ほぐし」の運動で仲間意識を更に高める
- /
- 学習内容の定着具合を授業中にチェックする
- /
- 子どもの「ほんのわずかな変化」に気づくことができるか
- /
- 「担任の通知表」で生徒に問う
- /
- 楽しい上にも楽しい時間が過ごせているか
- /
- 学級の教育力を生かす学習集団の再構築 (第9回)
- 授業の充実が心を育てる
- /
- 子どもは仲間集団によって育つ (第9回)
- 通学合宿で子どもが育つ
- /
- 「学級経営力」を高める私の修業 (第9回)
- できないことをできるようにさせていくところに修業の道とドラマがある
- /
- 酒井式で子どもの絵が変わる (第9回)
- 「あやとり」顔と手を使った教材の第二弾
- /
- 効果的な勉強法のすすめ (第9回)
- 小学校低学年/正月は五色百人一首を楽しむ
- /
- 小学校中学年/4年・理科「月」の効果的な導入
- /
- 小学校高学年/記憶に残りやすい勉強法
- /
- 学級担任の責任を問う (第9回)
- 不審者侵入防犯訓練
- /
- 編集後記
- /
編集後記
〇…ネット時代を迎えて、従来の生活指導という概念では対応できない新しい事態が数多く発生しています。ネットの活用は利便性とともに危険もあるわけですから、危機を予防するための対策を早急に立てる必要を強く感じます。
〇…そこで、「言葉のしつけ」にしぼってこの問題を学級経営の時点で考えてみたいと思いました。「言葉のしつけ」は、父母がわが子に対して、教師(学級担任、国語科担当)が児童、生徒たちに対して、さらには地域(社会)の人たちが地域(社会)に居住する児童、生徒たちに対して、それぞれ行うとされてきました。
〇…特に学級における「言葉のしつけ」の中心目標は、発言力、聞き取りの力、話し合う力をしっかり身につけさせることにねらいがあるとされてきました。しかし最近のように私語があふれて、静かに耳を傾けて聞こうとしない児童、生徒が多く見られる状況では、集団で話を静かに聞くことが困難になっているとの指摘もあります。これは「言葉のしつけ」不在を意味しており、さらには生活不在、人間不在へとつながっていくとの警告すら出されています。
〇…「言葉のしつけ」を態度、習慣の面から考えた場合、次のような人間のしつけと重なる五つの基本的な事項が大切にされる必要があると強調されています。(大橋富貴子氏の「言葉のしつけ」論)。第一は、相手を尊重して理解し合おうとする誠実さ、第二は、感情に流されずに言葉を選ぶ冷静さ、第三は、筋を通して話し聞く論理性、第四は、責任を持って話す主体性、第五は、向上意欲を持って聞く積極性、などです。
〇…教師は言語環境そのものであるとの指摘さえあります。本号はネット時代を迎えて「言葉のしつけ」を考え直してみたいとする特集です。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















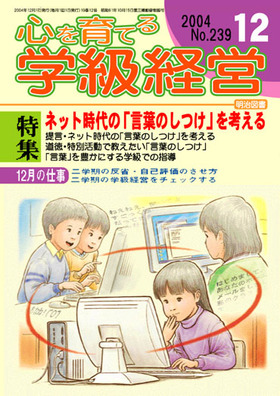
 PDF
PDF

