- 特集 臨界期までに身に付けさせたい「しつけ」総ざらい
- 巻頭論文
- しつけの大事さ
- /
- 臨界期までにどうしても身に付けさせたいしつけと学習習慣
- 高学年担任で痛感したしつけ不足
- しつけのポイントが理解できていない
- /
- 生活する力の積み上げが大事
- /
- 自分勝手に生きてきた子どもたち
- /
- 時と場に応じた言語使用をさせること
- /
- 約二年、靴をしっかりしまえるようになるまで
- /
- 高学年から、何とか挽回したしつけ術
- 高学年では遅すぎるが、教師が指導しなければならない
- /
- 教科書チェックと箇条書きの指導
- /
- 「納得」「モデル」「システム」「ほめる」
- /
- 「引き出しに常に本」「隙間時間の活用」「読書量の確認」
- /
- 「きちんと提出する」ということの大切さを教える
- /
- 臨界期までにしつけたい学習習慣
- 文字を丁寧に書く子は大きく成長する
- /
- ノート指導を通して「ていねいさ」を育てる
- /
- 「丁寧」は臨界期までに身に付けさせたい
- /
- 大切な学習習慣
- /
- 低学年のうちに聞く力を付ける
- /
- 臨界期までにしつけたい生活習慣
- 低学年では基本的な学校生活の習慣を
- /
- あいさつと後始末をしつける
- /
- 席を離れる時には、椅子を入れる
- /
- たかが「いす」「掃除道具」されど…
- /
- 素直さと我慢強さを身に付ける
- /
- 中学校これは助かる小学校からの学習習慣
- 学校は勉強するところ、授業中は勉強する時間
- /
- おもちゃ筆箱をなくし、勉強のための筆箱を
- /
- この習慣で大きな差が出る
- /
- 机の前に座る習慣が家庭学習の習慣につながる
- /
- 下敷き・鉛筆・ミニ定規を定番にしてほしい
- /
- 中学校これは助かる小学校からの生活習慣
- 部活動に適応できる生活習慣を身に付けておく
- /
- しつけの三原則が守れること
- /
- 中学生になっても残る生活習慣
- /
- ぞうきんが洗える子ども
- /
- 最後まで、きちんと話せること
- /
- 誰にも聞けないしつけのこだわり大公開
- 若葉マーク先生のドタバタ日記
- あとでやろう…ではなく、すぐやろう
- /
- グラビア
- 第2期女教師☆向山型算数DEEP研究会活動報告
- /
- 教室にあると便利なもの・便利な掲示 (第9回)
- /
- 巻頭言
- 愚痴は言いはじめると、とまらない
- /
- 辛口の応援歌―男先生からみた“女先生の教師修業”
- 我流の女性教務主任、研究主任は、学校を沈滞させる
- /
- すぐ使えるファックスページ
- 算数ぬりえシリーズ
- 1年用/「さかな」は「ひき」と数えます
- /
- 2年用/誰でもできる!かんたん算数パズル
- /
- 3年用/何かな、何かな?
- /
- 4年用/何が出てくるかな?
- /
- 5年用/四角形の中から台形を見つけよう
- /
- 6年用/あじさいに色をぬろう
- /
- すぐ使えるイラストページ
- 低学年動物キャラ
- /
- 運動会
- /
- 夢とのギャップを乗り越える20代
- 狂気する勇気
- /
- 家庭との両立を目指す30代
- 30代でとびこんだ障害児教育!
- /
- 学校の重責をスマートにやりこなす40代
- 1回のチャンスを濃いものにする
- /
- 教育改革を乗り切る50代
- TOSSで学び続けていれば怖くはない
- /
- 読み聞かせ文庫
- 低学年/雨の日に咲く花
- /
- 高学年/幸せの青い鳥
- /
- 女教師授業修業への道
- 褒めることに絞って修業する
- /
- 女教師のやる気 (第9回)
- 女教師の病気と弱気とやる気
- /
- 女教師は見た (第9回)
- 人生初体験~一人で講座に参加する~
- /
- 保健室奮闘記 (第19回)
- 「TOSS養護教諭ネットワーク」立ち上げに向けて!
- /
- 女教師喫茶室
- /
- 編集後記
- /
- 酒井式描画指導
- 屋根の上の白い猫
- /
巻頭言
愚痴は言いはじめると、とまらない
本誌編集長 石川裕美
人によっては、話し方がさわやかな場合と、聞いていられない場合がある。話し言葉はその人を表す。いつだって不満を全身に表し、人を批評している人がいる。苛立ちはあふれ出て、まわりじゅうに散らばっていく。
ベテランになればなるほど、人のミスが目にとまる。同じことを言っても、心地よい語りになる人と、そうでない人がいる。
なんでも我慢するのが良いとは言わない。だがいつもマイナスに受け取り、怒りばかりを訴えれば、ついつい話をしたくなくなる。
子どもだって、それはわかるものである。
明るいのが一番である。力がなくても、明るく子どもに話しかけることができるだけでよい。
周りを見渡そう。せっかくの職場、何を好き好んでつまらなくしているのか。
何事も、プラス方向に進んでいければ良い。素直に人の意見に耳をかたむけ、真摯に努力する。
うまくいかなくてもいいのである。日々、少しずつ積み重ねよう。それはきっと身になるはずである。
うまくいかない時、指導が空回りした時、イライラして必要以上に叱ってしまった時、落ち込むより、深く反省するより、新しい気持ちで明日出直そう。深呼吸をして、楽しそうな授業を探し、気持ちを切り替え、明るく出直そう。
そのほうが深く反省するより、ずっと効果がある。子どもは毎日新しい。我々より新しい。
職場の小さなマイナス面を見るより、子どもたちの中の、小さなプラス面を見つけるほうがどれだけいいかわからない。気持ちの切り替えが、最後は勝利を生み出すのである。
子どももきっとついてくる。
-
 明治図書
明治図書















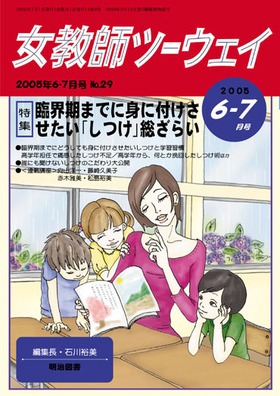
 PDF
PDF

