- 特集 授業づくりの実践・私が大切にしていること
- 授業づくりの方法論と今日的課題
- /
- 授業づくり ステップ・アップのための方法
- /
- 「授業で大切にしているもの」―生活科の授業の中から
- /
- 書きこみ学習からみえてくるくらし―『書く・聴きあう』
- /
- 子ども自らが学ぶ授業を追求するためには……
- /
- NEW BORN (第14回)
- /
- 一年めの出会いを心にとめて(後編)
- /
- 【資料】部落を解放する教育内容の創造と、学習の保障のために 一九七二・四・十八
- /
- 共生のトポス (第86回)
- 正しい教育が子どもに還元されるために
- /
- 〜金相文(キムサンムン)さん(後編)〜
- 【コラム】ジェンダー論の練習問題 (第49回)
- やおい/BL入門のために(4)
- /
- 〜「リアルゲイ」をめぐって〜
- 編集部の本棚
- まだまだ、だまってられへん (第2回)
- そうか、まだこんなところに隠れていたのか
- /
- 子どもを見る眼 (第2回)
- 子どもを見る眼を養ってくれる職員室
- /
- 映画をみる、映画でみる (第2回)
- 「国境」とは何か
- /
- 【コラム】ノリきれない国際公務員のつぶやき (第14回)
- やみつきになる理由
- /
- 小西先生の『学級革命』を読む (第14回)
- 子どもに寄り添う名人のワザ
- /
- まいにち? マイニチ!
- 北のおるた〜北海道からの便り〜 (第6回)
- アイヌ民族の辿ってきた歴史を振り返る
- /
- おもちゃばこ (第26回)
- さわやかな風にここちよい言葉をのせて(1)
- /
- 〜気持ちを知ることから始めよう〜
- 解放教育・バックナンバー
- 485号〜496号・二〇〇八年四月号〜二〇〇九年三月号
- 編集後記
- /・
編集後記
▽「学力」問題に何かと注目が集まる昨今ですが、ふだんの授業実践のステップ・アップをいかに図るべきか、という基本的な課題について、もっと積極的に議論されるべきではないでしょうか。自校や自分がおこなっている授業の到達点・改善点はいったいどこなのか。この点をきびしく省察し、授業実践の力量を相互に高め合うことが今こそ重要課題だと思えてなりません。
▽もちろん子どもたちが豊かに学び合うために、学校現場では日々さまざまな創意と工夫がなされています。とりわけ人権の視点を大切にして、教室で学び合い、学習力を着実に高めていくために、多様な実践が追求されていることも確かです。
▽そこで、本特集では「どの子どもも学びたがっている。とりわけ『しんどい子ども』ほど学びたがっている」という事実をいま一度確認し「学び合い高まり合う授業」を展望しつつ「学ぶよろこびが共有できる授業」「思考力・表現力・活用力が育つ授業」を行うために、教師はどのような視座と方法を保持すべきなのか。この基本課題を元に、これからの授業実践の方向性と具体的な内実について探りました。明日からの実践の糧となることを期待します。
(園田)
▼資料の「四認識」に関する全同教事務局の文書は、いまから四〇年近く前のものです。この文書以後、三〇年以上にわたって全同教はこの枠組みに従って教育研究集会で分科会を組織していました。学力保障と人権学習の統合を考えるとき、この文書の観点を抜きにはできません。多重知能論を参照しても、フィンランドの学力観である「学び学習力」に学んでも、この文書の意義は色あせません。この文章を挟んで、読者の間で議論が広がれば嬉しいです。
▼教員養成の未来を切り開くためには、暗記主義的な知識観を越えて、ふりかえりを通して自らを再構築するような知識観に移行する必要があります。つまり、新しい知識を得ることにより、それまで持っていた世界観を再構成できるような学習こそ求められているということです。これは、二一世紀の現在、求められている学力観そのものだといえます。
(森)
-
 明治図書
明治図書















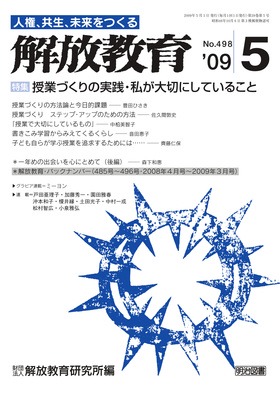
 PDF
PDF

