- 特集 年末・年始の行事やならわしを教材化する
- 巻頭論文
- 行事や雑煮を教材化する
- /
- 年末の行事・ならわしの教材化
- 北海道地方/雪囲いと冬支度
- /
- 東北地方/さむーい地方のあったかーいネタ
- /
- 関東地方/大晦日に便所で夕食を食べる…
- /
- 中部地方/「我が家」が育む子供の取材力
- /
- 近畿地方/生の喜び 神々への感謝
- /
- 中国地方/天下の奇祭「笑い講」を歴史学習に
- /
- 四国地方/脇町の三味線もちつき
- /
- 九州地方/飾りから見える願いと迷信
- /
- 新年の行事・ならわしの教材化
- 九州地方/「皿ごま」の教材化
- /
- 四国地方/伝統行事「弓祭」の教材化
- /
- 中国地方/お正月は「ふぐ料理」で
- /
- 近畿地方/行事を探って、地域の「意外」に気づく
- /
- 中部地方/「さいの神」の教材化
- /
- 関東地方/ふるさとを大事にする子を育てる
- /
- 東北地方/「団子さし」でたのしいおやつの授業
- /
- 北海道地方/「下の句カルタ」からみえるフロンティア・スピリット
- /
- 日本各地の雑煮の教材化
- 北海道地方/丸餅での味噌仕立てがほとんどないのはどうしてか
- /
- 東北地方/だしは「土地」で決まる
- /
- 関東地方/「わが家の雑煮」で家風が見える
- /
- 中部地方/東西文化の交流の様相が見えてくる
- /
- 近畿地方/京都の雑煮,教材化の3つの視点
- /
- 中国地方/雑煮はその地域の「食のよさ」を集めた食べ物
- /
- 四国地方/お雑煮で立身出世
- /
- 九州地方/宮崎特製の雑煮を考える
- /
- わたしの家の年末・年始の迎え方
- 奄美大島/人とのつながりを大切にしたい
- /
- 岐阜県/恒例! 翠家の正月行事
- /
- わたしの家の雑煮
- 新潟県/ワラビが入る具だくさん
- /
- 宮城県/わが家の雑煮は石巻風?
- /
- 沖縄地方の年末・年始のならわし
- 祖先崇拝の思想が強い沖縄の年末・年始
- /
- ファインダーがとらえた授業診断
- 鎌倉時代を創る?
- /・
- 有田編集長のメッセージ
- /
- はてな?出題 こんな内容をどう教えるか
- テスト問題でどう学習させるか?
- /
- コンピュータ授業への誘い (第9回)
- 画像を入れた名刺を作ろう
- /
- 授業に役立つホームページ
- 総合的学習/(情報教育)『ネチケット』は言葉だけじゃだめ
- /
- 教科学習/インターネットで調べ学習
- /
- 私の教材発掘 読者とのツーウエイ
- 理科/正しい順番に並べ換えなさい
- /
- 社会/地域によって味が微妙に違うカップ麺
- /
- 子どもが本気で取り組む難問と解説 (第9回)
- 国語低学年/谷川俊太郎の詩を読む―擬態語は面白い
- /
- 国語中学年/修飾語に強くなろう
- /
- 国語高学年/案内状の返事が正しく書けますか?
- /
- 社会中学年/むかしの道具しらべ
- /
- 社会高学年/歴史学習を“難問”で締めくくろう!
- /
- 算数低学年/冬休み―算数パズルに挑戦!
- /
- 算数中学年/12月・覚え難問・探し難問
- /
- 算数高学年/「わりあい」とむずかしい難問
- /
- 理科中学年/上皿てんびんで調べよう
- /
- 理科高学年/「大地のつくり」の難問
- /
- 子どもの笑いをさそうユーモア小話
- 子どもとの日々は楽しさいっぱい
- /
- めがねをなくしたので川の名前がわからない!
- /
- わたしの書評
- 『「頭のカルテ」で子どもをとらえる技術』
- 子どもを見る目が変わる
- /
- すぐ役に立つ子どもを見る技術
- /
- いい本みつけた!
- おじいちゃん 戦争のことを 教えて
- /
- 歩いてみよう東京
- /
- わたしが見た面白い授業
- 静岡市立一番町小学校4年
- /
- 〜ネタに「長いもの」を取り上げると子どもの意欲が喚起される〜
- 教材・授業開発研究所情報
- /
- 基本・国語科授業入門 (第31回)
- 文語調の文章に親しむ実践
- /
- 〜「山のあなた」(4)〜
- 総合的学習の教材開発 (第9回)
- 「トイレから世界が見える」の授業(7)
- /
- 編集後記
- /
- 写真構成・総合的学習の教材開発 (第9回)
- My big farm−私の中の大きな畑(一人一坪栽培活動)−
- /
総合的な学習の時間を楽しく演出するネタ満載!
有田編集長のメッセージ
一年間で、日本の伝統的な行事やならわしが最も生きているのは、年末・年始です。
大そうじや餅つきをしたり、しめ縄や松を飾ったりとふだんとはちょっと違うことを年末には行います。地域によって行うことが違います。これはどうしてでしょうか。
三一日には、除夜の鐘が一○八つかれます。これはどんなことからおこったならわしでしょうか。
「正月」という行事は、いつ頃から、どんなきっかけでおこったものでしょう。「正月三が日」とは、何をするのでしょう。
「松の内」とは正月の松飾りのある元旦から七日までの間をさしますが、この七日間、どんなことをするならわしがあるのでしょう。
わたしの田舎では、「鬼火」を行うならわしがあり、子どもの楽しみの一つでした。
正月に食べる「雑煮」(食べない地方もある)も、地方によって大きく違います。丸餅を入れる地方、切り餅や角餅を入れる地方、それも焼いて入れる地方や煮る地方があります。
汁も「みそ」(白・赤がある)を入れるところや「清汁」のところもあります。
「だし」や「具」に至っては、ここでは書ききれないほど多種多様です。まさに「所変われば品変わる」です。
地方ごとに違いがあると同時に、浜名湖の湖口の東と西でも雑煮が全く違うように、同じ地方でも違いがあります。
ならわしや行事の違いは、地域の気候・風土、産業などからくるのではないでしょうか。
地方ごとの特徴を出していただくことによって、これを比べてみるとその違いの大きさに驚くことと思います。
日本の伝統的な行事やならわしを教材化して学習することは、地域の歴史を知る上からも、自分の生活をふりかえる上からも意味のあることです。
今まで何気なく行っていたことが、実は昔から伝わっていることで、それなりの意味のあることだとわかれば、行事の見方も、参加のしかたも変わってくるはずです。わたしにとっても楽しみな特集です。
-
 明治図書
明治図書















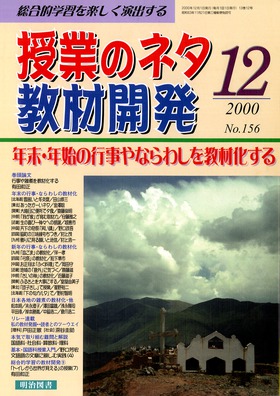
 PDF
PDF

