- 特集 「基礎的な教材」としての教科書の新しいとらえ方
- 巻頭論文
- 教科書の中の基礎基本と発展教材を考えておく
- /
- 「基礎的な教材」はと問われて考えることは?
- 面白く、追究可能
- /
- 基礎的な学力を身に付けられるもの―子供たちが切実な問題としてとらえ考えることのできる教材
- /
- それは教師自身が創るもの
- /
- 読み、書き、計算ができ、日常生活に活かせること
- /
- 教科書は基礎的な教材といえるか
- 国語/言語技術を育てようとしない国語の教科書
- /
- 社会/その子にとっての「問題解決のための力」を
- /
- 算数/レディネスのチェックと養成を組み込んだ展開を
- /
- 理科/教科書を上手に使って基礎的な教材にしよう
- /
- 教科書を教えていれば基礎学力はつくか
- 国語/基礎学力をどうとらえ教材の中にどう見いだすか
- /
- 社会/教科書も含めた「教材化」で基礎学力はつく
- /
- 算数/教科書を教えていなければ基礎学力はつかない
- /
- 理科/内容面と機能面の両面を教科書でとらえて
- /
- 教科書で「子どもの学び方」は育つか
- 国語/学習の手だてが示された教科書を
- /
- 社会/教科書だけでは子どもの学び方は育たない
- /
- 算数/くらしとむすびつく学習
- /
- 理科/新学習指導要領の趣旨を理解し、教科書を読みとる努力を!!
- /
- 今の教科書は子どものニーズにマッチしているか
- 最後は教師の腕である
- /
- 教師次第
- /
- 興味に応じ学びをグレードアップしていける教科書
- /
- 「知りたい」というニーズに応える
- /
- 教科書は子どもの味方といえるか
- 教科書は子どもの味方といえる
- /
- 子どものために教科書だって維新前進
- /
- 教科書は、マジンガーZであり、ゴレンジャーである
- /
- 教科書 生かすも 殺すも 腕次第
- /
- 古くて新しい問題・教科書「を」か「で」か
- 「を」から「で」へそして「も」へ
- /
- 教師の立ち向かい方が問われている「新たな問題」
- /
- 「を」「で」を場合に応じて使い分ける
- /
- 教科書を教えられるか子どもの事実を正視しているか
- /
- 有田編集長のメッセージ
- /
- ファインダーがとらえたこの授業ここが素晴らしい
- 伴一孝氏の「総合」授業
- /
- 〜インターネットを使った最先端の授業〜
- 教科の基礎学力をつける指導 (第7回)
- 国語/「書くこと」の基礎学力を考える
- /
- 社会/子どもとともに創る「もう一つの教材」
- /
- 算数/「書く活動」を算数の授業に取り入れる
- /
- 理科/深層海流を授業に生かす
- /
- 授業を楽しくする「はてな? 不思議」発見 (第7回)
- 生活・総合/今こそ、学習支援ボランティアの導入で意識改革を図るとき
- /
- からだと健康/ふしぎなふしぎな“お通じ反射”の秘密!?
- /
- 面白い本みつけた
- 『ペリー提督日本遠征日記』
- /
- 『学習技能を鍛える授業』
- /
- 授業・生徒指導に生きるユーモア小話
- 子どもたちにユーモアを探させよう!
- /
- 私の教材発掘 読者とのツーウエイ
- 総合的な学習/「知っているつもり」をゆさぶり、追究の鬼を育てよう
- /
- 生活科/生活科を成功させるための教材発掘
- /
- わたしの学級づくり
- よろこびを力に
- /
- 教材・授業開発研究所情報
- /
- 手の内公開・教材研究と発問づくり (第7回)
- 道徳「生きる意味」の授業(上)
- /
- 〜4年生から中学生ぐらいまで〜
- 総合的学習の教材開発 (第19回)
- 山葵日本一(中伊豆町)を教材化する(1)
- /
- 編集後記
- /
- 総合的学習の教材開発 (第19回)
- 総合的な学習の時間で、中学1年生で身につけるべきスキルとは
- /
有田編集長のメッセージ
新しい学習指導要領は、あくまでも学習内容の最低基準を示すものであるということになっています。
この「学習内容の最低基準」を具体化して子どもに教えられる内容と方法を示したものが「教科書」です。
学習指導要領の示す最低基準をクリアしているか、内容を逸脱していないか、内容の落ちや間違いはないか、と文部科学省の厳しい検定を通ったものが「教科書」として教育現場に提供されています。
こういうことから、「教科書こそ基礎的な教材である」と考えることができます。しかし、これは文部科学省の考える基礎的な教材であって、他の立場から見ればおかしいということもあります。
事実、地球産業文化研究所(平岩外四理事長)などでは、新しい学習指導要領では学力低下は目に見えているので「新学習指導要領全面中止せよ」と提案しています。
つまり、基礎学力のとらえ方が文部科学省とは異なるのです。
教科書は、検定を合格しなければならないので、学習指導要領に忠実です。が、著者はぎりぎりのところまで挑戦しています。だから、各社によって特色が出ています。
来年度から新しい学習指導要領にのっとった新しい教科書が使用されることになっています。この時期に、教科書の新しいとらえ方を検討してみたいと考えました。
教科書は基礎的な教材といえるのか。教科書を教えていれば基礎的学力はつくのか。また、教科書で「子どもの学び方」は育つのか。といったことについて、教科書使用度の高い四教科で検討を加えて、新しいとらえ方や使い方を提案してみたいと考えました。
さらに、今の教科書は子どものニーズに本当にマッチしているのか、教科書は子どもの味方でなければならないのだが、味方になっているといえるのか、子どもをいじめる材料になっていないか、といったことも検討してみたいと考えました。
最後に、古くて新しい問題、教科書を教えるのか、教科書で教えるのかについても検討を加えてみたいと願いました。
-
 明治図書
明治図書















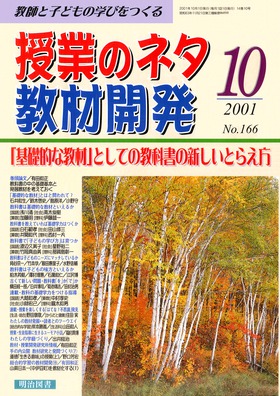
 PDF
PDF

