- 特集 新教育課程に向けた授業を創る⑩ 「算数的活動」を通した問題解決の授業
- 実践化に向けて
- 「算数的活動」を活用した問題解決
- /
- 特集に基づく実践事例
- 小学1年/算数的活動の連続を図る授業(たしざんとひきざん)
- /
- 小学2年/図形の見方・考え方を育てる算数的活動(三角形と四角形)
- /
- 小学3年/かかわりの中から問いの深まりを生む(わり算の筆算)
- /
- 小学4年/垂線のかき方を発見しよう(垂直・平行と四角形)
- /
- 小学5年/見方を広げる指導(四角形の面積)
- /
- 小学6年/輪投げで勝負,どっちが勝った?(資料の調べ方)
- /
- 小特集 次への学習の楽しみを引き出す授業の工夫
- 特集の解明
- 教師の工夫が次への学習の楽しみを引き出す
- /
- 実践事例
- 2年/もっとやりたいな「形当てゲーム」(三角形と四角形)
- /・
- 3年/三角形作りから問いが連続する(三角形と角)
- /
- 6年/きまりを発見する学習プリントの工夫(立体の性質)
- /
- 算数HOTサイト (第22回)
- 線(点)対称バトル
- /
- 算数教育ビギナー講座 (第10回)
- Q・分数のわり算はなぜ分母と分子をひっくり返して掛ける?
- /
- 算数が好きになる問題
- 小学1年/さんかくだけで さかなをつくろう
- /
- 小学2年/自分の方法で求めよう
- /
- 小学3年/あんごうをとこう!
- /
- 小学4年/かわればかわる!?
- /
- 小学5年/順序よく考えよう
- /
- 小学6年/見方を変えると?
- /
- 授業への活かし方
- 算数教育最前線・これからの授業方式を探る (第10回)
- 新聞(NIE)で算数をしよう!
- /
- 問題解決とその指導をはっきりさせよう (第4回)
- 自力解決時における指導はどうあるべきか
- /
- 21世紀の算数教育・時代を担う研究者のアプローチ (第16回)
- 子供に問題づくりの機会を
- /
- 難教材の克服法 (第4回)
- 1にあたるのはどこ?
- /
- ~6年「分数のわり算」(続)~
- 21世紀の教育課程を考える (第34回)
- 教育課程審議会の中間まとめ
- /
- 楽しい問題 子供の挑戦コーナー
- 9月号挑戦者及び解答
- 編集後記
- 楽しい問題 子供の挑戦コーナー
- 形を変えて面積を半分に!
- /
編集後記
本号では,問題解決において算数的活動をどう生かしていったらよいかということについて特集しました。
算数の学習はほとんどが問題解決の活動なので,そこで算数的活動を通して,これがなされなくてはならないことは言うまでもありませんが,例えば文章題や興味ある問題を取り上げて,この問題解決に算数的活動がどのようにそのよさを発揮するか,更にこのような問題を子供たちで作ったり,新しい問題に発展させたりしていくときに,算数的活動がどうなされるべきかを示しました。
算数的知識や技能を使っていくだけでなく,数学的な考え方を生かしていくことが,その主役になるでしょう。この点がよく表れるような具体的事例を豊富に示していただきました。
「活動の楽しさ」や「数理的な処理のよさ」を味わうことのできる授業を大切にしていくことが,より一層大切になってきています。知的な喜びがあふれた授業ということでしょう。
さて,そのようなことが望まれるとき,その1時間1時間内だけの楽しさやよさの味わいだけではなく,更には「この続きをしたい」「次はどんなことをするのかな」,あるいはまた,次の時間が始まろうとするときに「先生,今日何やんの」と子供たちから思わず声がかかるような授業を試みたいと思います。
-
 明治図書
明治図書















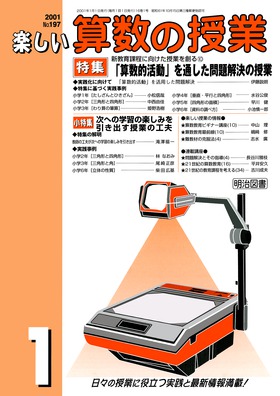
 PDF
PDF

