- まえがき
- 序章 「探究」で変わる子どもたち
- 第1章 『あなたの学びは、あなたが決める』
- ヒント 01 学びの舵を握るのは学び手本人
- ヒント 02 問いや意欲のために〝余白〟を持つ
- ヒント 03 サービスせず、サポートする
- デザイン01 「自分で決める」のバランスを悩み続ける
- 小学校/関わり方・あり方
- デザイン02 生徒が「自律型学習者」として学べるような教師の役割とカリキュラム
- 中学校/関わり方・あり方
- デザイン03 なぜ学ぶのか?~自分で決める~
- 中学校/高等学校/関わり方・あり方
- 自分たちでルールを決めた子どもの声
- 第2章 『あなたの一歩が、あなたを変える』
- ヒント 04 子どもたちは一歩踏み出したがっている
- ヒント 05 自分の問いをもつ
- ヒント 06 試行と失敗を歓迎する・当事者意識が全ての基盤
- デザイン04 「プロジェクト型の学び」で一歩踏み出す
- 小学校/授業デザイン
- デザイン05 「何のために」学ぶのか、社会や未来を考えるツールの活用
- 中学校/授業デザイン
- デザイン06 できるの繰り返し/仲間と一緒ならできる
- 高等学校/授業デザイン
- 新聞を活用したチーム探究によって成長した子どもの声
- 第3章 『あなたの学びで、だれかとつながる』
- ヒント 07 学びを〝内〟(自分/学校)に閉じ込めない
- ヒント 08 つくることで学ぶ・行動することで学ぶ
- ヒント 09 社会とつながる・社会に届ける
- デザイン07 「学ぶってすごい!」を演出する
- 小学校/授業デザイン
- デザイン08 未来を見据えたバックキャスト
- 中学校/授業デザイン
- デザイン09 社会と接続する授業
- 高等学校/授業デザイン
- プロジェクト活動で社会と繋がり、変容した子どもの声
- 第4章 『あなたの想いを、だれかに届ける』
- ヒント 10 「好き」「楽しい」が最強であると信じる
- ヒント 11 「誰かのために」は探究の限界を押し上げる
- ヒント 12 未来づくりという視点をもつ・完成度よりも熱意
- デザイン10 「一人ひとりの尊重」と「全員のエネルギー」を両立する
- 小学校/授業デザイン
- デザイン11 地域や社会につながり、共創者を得る
- 中学校/授業デザイン
- デザイン12 旅から新たな問いが生まれ、自分の「在り方」を問う
- 高等学校/授業デザイン
- 社会に「想い」を届け、行動も変化した子どもの声
- 第5章 『学びの文化を、みんなでつくる』
- ヒント 13 ひとつのすごい授業より、学びの文化をつくることを大切に
- ヒント 14 大人も子どもも、誰一人取り残さない
- ヒント 15 学びは続いていく
- デザイン13 一人で行くよりも、みんなで行く
- 小学校/学校システム
- デザイン14 目的で合意し、様々なステークホルダーと共創する
- 中学校/学校システム
- デザイン15 生徒も交えた教員研修・プロフェッショナルラーニング
- 中学校/高等学校/学校システム
- 教員の伴走を受け、文化を醸成している子どもの声
- 終章 それでも「探究」に悩むあなたへ
- 悩み 01 成績ってどうつけたらいいの?
- 悩み 02 基礎学力は大丈夫? 進路はどうなるの?
- 悩み 03 できない子はどうするの?
- 悩み 04 保護者や同僚の先生の同意はどのように得たらいい?
- 悩み 05 どのような準備をしたらいいの?
- あとがき
- 執筆者紹介
まえがき
「教師の側から知識を授けるよりも、まず知識を求める動機を子どもたちがもつような学校が、真の学校である」
これはアメリカの哲学者であるジョン・デューイの言葉です。ジョン・デューイは20世紀の前半に活躍をしました。学校教育がまだまだ前時代的だった時期に色々と新しい提言をしており、他にも次のような発言・考え方がありました。
「教育のすべては児童から始まる」(児童中心主義)
「学習の本質は、自ら問題を発見し、解決していく能力を身につけていく点にある」(問題解決学習)
「Learning by doing!」(経験主義)
これらの発言は、現代において日本をはじめ世界中でのテーマとなっている新しい教育観へのアップデートを予言していたようにも見えます。実際にジョン・デューイは「探究学習の元祖である」と言われることもあります。
私たち新渡戸文化学園では「未来の学校をこの世に描き出す」という目標を立てて、2019年を境に探究学習を軸にした学びへの進化に取り組んできました。新しい学校をデザインするにあたり、これから迎える不透明な未来に向かう子どもたちに相応しい学校像を思い描きました。未来からバックキャスティングしたデザインです。
一方で、私立学校には建学の精神があります。新渡戸文化学園は1927年に創立された学校で、「女子経済専門学校」が当初の学校の姿です。当時教育が行き届いていなかった女性に教育を、そして良妻賢母を目指すだけではなく社会で活躍することを願って創立された学校です。女性が初めて選挙に投票したのは1946年のことですので、それより遥か前に女性活躍をテーマに学園を創立したことは、非常に誇らしい成り立ちだと感じています。その創立者の一人が新渡戸稲造博士でした。新渡戸文化学園初代の校長先生です。
新渡戸稲造校長の言葉にこのようなものがあります。
「教育とは新しい知識を教えることでなく、新しい知識を得たいという気持ちを起こさせることである」
この言葉を聞いて、何か気づくことはありますか。よろしければ冒頭のジョン・デューイの言葉を今一度ご覧ください。いかがでしょうか、とても似ていないでしょうか。
新渡戸稲造博士は、校長の就任時に「教職員心得」を書いています。その中には、「学課を授くるに智育のみに偏せざるよう思慮と判断力の養成に努むること」という言葉がありました。知識の詰め込みばかりにならないように、子どもたちが思考をしたり、判断をしたりする重要性が述べられています。この言葉はおよそ100年前に書かれたものですが、現代の文部科学省でも学習指導要領において「思考力・判断力・表現力」の育成を掲げていますので、これもまた新しい教育観に通ずるものがあると感じます。私たちはこのような創立者たちの願いにも立ち返りながら新しい学校のデザインを行いました。未来と過去の両方から現代にあるべき「新しい学校」の姿を描いたのです。
私自身は、新渡戸文化学園の目指すものがジョン・デューイの考えと非常に近く、同時に初代校長の新渡戸稲造博士とジョン・デューイの発言も考えが一致するものが多いことを感じていました。そしてある時、書物を読んでいて次のような文を発見しました。
「ジョン・デューイは1919年に日本に来日、友人である新渡戸稲造が学長をつとめる東京女子大学の宿泊施設に滞在した」
ジョン・デューイと新渡戸稲造は友人だったのです。これを初めて知った時には、背筋に電流が走る思いでした。新渡戸稲造博士は教育観において、おそらくジョン・デューイに大いに影響を受けていたのだと想像します。そして新渡戸稲造校長を通じて、ジョン・デューイの魂は新渡戸文化学園に今でも息づいているのです。新渡戸文化学園が「探究」を軸にした学校に進化していくことは、偉大な先人たちの導きだったのかもしれません。
私は私立学校の役割は「イノベーション」だと考えています。日本中の学校の進化のために、必要なチャレンジを先陣切って行い、そこで得られた知見もうまくいかなかった経験も余すところなく全国の学校に還元したいと願っています。
「日本中を幸せにする学校をつくりたい」という目標を掲げ、おかげさまで現在では、年間で100件を超える視察が学園に訪れています。
本書は、新渡戸文化学園の小中高の先生がこれまでのチャレンジの中で得られた「学びが変わる」ための大切なヒントを、またそのためのデザインを、惜しみなくお伝えをしています。書かれていることはすべてリアルな熱量のある実践であり、そこから私たちが核となる部分を抽出し、言語化した大切なノウハウです。
どうか本書が日本中の教育関係者に届き、学校のアップデートにつながり、生徒と先生の幸せにつながっていくことを心から願っています。気になるところからでも、最初からでも、どこから読み進めていただいても大丈夫です。ワクワクする「未来の学校」を思い描きながら、どうか楽しんでお読みください。探究の旅へいってらっしゃいませ!
2024年12月 /平岩 国泰














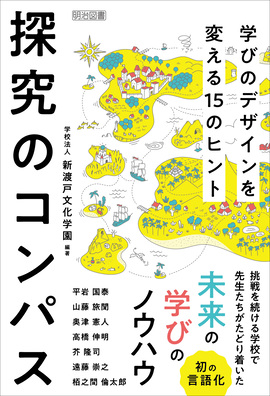
 PDF
PDF


コメント一覧へ