- はじめに
- 第1章 いい学級にあらわれる教室の姿
- 条件01 いい学級の教室は…和やかさと規律が調和している
- 条件02 いい学級の教室は…きれい
- 条件03 いい学級の教室は…教師の「色」が息づいている
- 条件04 いい学級の教室は…子どもたちの「色」が鮮やかに重なり合っている
- 第2章 いい学級にあらわれる子どもの姿
- 条件05 いい学級の子どもは…幼く見える
- 条件06 いい学級の子どもは…ゆるやかにつながり合っている
- 条件07 いい学級の子どもは…自ら進んで学んでいる
- 条件08 いい学級の子どもは…トラブルをたくさん起こしている
- 条件09 いい学級の子どもは…給食をよく食べている
- 条件10 いい学級の子どもは…自由にタブレットを使っている
- 条件11 いい学級の子どもは…大きな声で話し合いをしていない
- 条件12 いい学級の子どもは…気持ちのいいあいさつをしている
- 条件13 いい学級の子どもは…自分たちで学級づくりをしている
- 条件14 いい学級の子どもは…教師の枠を超えて成長している
- 第3章 いい学級をつくる教師の姿
- 条件15 いい学級の教師は…子どもたちとたくさんコミュニケーションを取っている
- 条件16 いい学級の教師は…同僚との関係が良い
- 条件17 いい学級の教師は…新年度に保護者へ教育観を丁寧に伝えている
- 条件18 いい学級の教師は…保護者とたくさんコミュニケーションを取っている
- 条件19 いい学級の教師は…どんな子どもを育てたいかのイメージがクリアだ
- 条件20 いい学級の教師は…まず子どもをリードしている
- 条件21 いい学級の教師は…学級のルールを子どもたちと決めている
- 条件22 いい学級の教師は…様々なことを「見える化」している
- 条件23 いい学級の教師は…子どもに合わせて対応を変えている
- 条件24 いい学級の教師は…個性的な子どもが孤立しないようにフォローしている
- 条件25 いい学級の教師は…「自分らしさ」を大切にしている
- 条件26 いい学級の教師は…しっかりと教え込みもしている
- 条件27 いい学級の教師は…授業中の脱線も大切にしている
- 条件28 いい学級の教師は…威厳で信頼を得て親しみで安心感を与えている
- 条件29 いい学級の教師は…子どもに「自己選択」をさせている
- 条件30 いい学級の教師は…学びに遊びがある
- 条件31 いい学級の教師は…やらせっぱなしにしていない
- 条件32 いい学級の教師は…「語り」がうまい
- 条件33 いい学級の教師は…意図的に抽象的な指示を出したりもする
- 条件34 いい学級の教師は…自分を変えようとしている
- 条件35 うまくいっていない学級の教師は…子どもを見ていない
- 参考文献・参考資料
はじめに
「いい学級」や「いい教師」というものは、果たして本当に存在するのでしょうか。
今もこの問いに明確な答えを見つけられずにいます。もしかすると、そんな理想は存在しないのかもしれません。
9月のはじめ、ちょうどこの単行本を脱稿しようとしていた日のことです。庭で遊んでいた息子が突然嬉しそうに叫びました。
「パパ! あさがおが咲いてるよ!」
私は耳を疑いました。確かに6月の終わりに、家族で花壇にあさがおの種をまきました。しかし、この夏は異常な暑さが続き、芽は出たものの、花は一度も咲きませんでした。息子は毎日心を込めて水をあげ、花が咲くのを心待ちにしていましたが、その願いは結局叶うことはありませんでした。そして、7月が過ぎ、8月も終わり、昼間は依然として残暑が厳しい日々が続いていましたが、いつの間にかセミの声は消え、朝夕にはかすかに秋の気配が漂い、涼しい風が吹くようになっていました。この頃には、誰も水をあげることもなくなり、雑草が生い茂り、花壇はすっかり子どもがいなくなった団地の一角にある公園のように寂しげでした。あさがおのことなんてみんなが忘れかけていました。そんなとき、花壇の端っこに、ひっそりと、申し訳なさそうに一輪のあさがおが咲いていたのです。それは、まるで夏の最後の贈り物のようで、息子の願いがわずかに叶ったかのようでした。
この出来事を通して、私は教育も同じだと感じました。どれほど厳しい環境でも、子どもたちはふとした瞬間に、誰も予想しない形で花を咲かせることがあります。誰もが「もうダメだ」と諦めかけた状況の中でも、子どもたちは静かに、自分の力で成長を遂げることがあるのです。一方で、いくら手をかけて育てても、思うように花が咲かないこともあります。整った条件でも、悪条件でも、何がその子にとってプラスになるか、どんな出来事が彼らの成長を促すのかは、誰にもわかりません。
私たちが「これが正しい」と信じて与えたものが、必ずしも成果を生むとは限らず、時にはマイナスに作用することさえあります。予期しなかった状況の中で、子どもたちは自ら芽を出し、私たちに気づかせるかのように花を咲かせることがあるのです。
だからこそ、「これがいい教育だ」「これがいい教師だ」と決めつけること自体、もしかしたら教師の傲慢なのかもしれません。「いい教育」や「いい教師」は、子どもたちが感じるものであって、教師の意識だけがそれを左右するものではないはずだからです。もっと言えば、子どもに「教える」といった上意下達のマインド自体がそもそも間違っているのかもしれません。
では、なぜ一見矛盾するかのような本書を上梓したのか。その理由は、私が初任の頃に経験した学級崩壊寸前の苦い体験にあります。あのときの悔しさは大きく、自分を深く反省するきっかけとなり、それが私の学びの原点となりました。それ以来、「いい学級とは何か」「いい授業とは何か」「いい教師とはどのような存在か」という問いを抱えながら、実践を重ねてきたのです。その答えを探し求めるために、私は様々な教師の教室を積極的に見学してきました。
興味深いことに、「いい学級」と評される教室に入ると、どの学級にも共通して温かさと安心感が漂っていることに気づきました。教師の教育観や授業スタイルが異なっていても、その共通点はほとんど変わらなかったのです。教室全体に穏やかな雰囲気が広がり、何よりも子どもたちが本当に生き生きとしていたのです。私は、こんな学級をつくりたいと強く思うようになりました。多くの子どもたちにとって毎日が楽しく、心も体も大きく成長できる場を提供したいと強く考えるようになりました。
そこから、「なぜ教師の指導スタイルが違うのに、学級の雰囲気がこんなにも似ているのか」「どうすれば、こんな居心地のよい学級をつくれるのか」という疑問を解き明かしたいと考え、2017年に奈良教育大学教職大学院に進学しました。「いい学級」とは何か、そしてそれをつくるために必要な指導技術とは何なのか。その答えを探るため、2年間で約80近くの教室を訪問し、研究に取り組みました。
本書では、私の経験や研究から得た知見、訪問先での具体的なエピソードを交えながら、「いい学級」とは何かを、教室や子どもたち、教師の様子から解説しています。
本書が読者のみなさんにとって何らかの助けとなれば、それは私にとって望外の喜びです。そして、子どもたちの成長と幸せを願いながら、共に「教育」という果てなき問いに思いを巡らせるきっかけとなれば、これ以上の幸せはありません。
著者 /小野 領一
-
 明治図書
明治図書- うんうんとうなづきながら読みました。ハウツーが書いてあるわけではありませんが、校内にいい!と思う先輩がいない場合にはちょうど良い書籍だと感じます。2025/4/520代・小学校教員
- 学級づくりについて丁寧に書かれていて勉強になりました。2025/4/120代・小学校教員
- いい学級を目指したいです2025/3/2620代・小学校教員














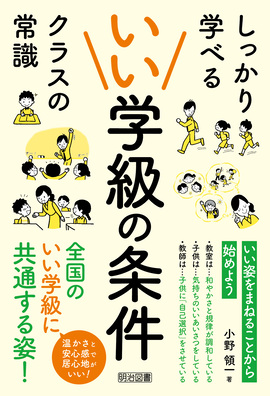
 PDF
PDF

