- �܂�����
- ��P�́@�l�ނ��琬���邽�߂̐S�̍\��
- �y⼌��P�z�@�u�P�v�����ł��Ȃ��Ȃ�C�u1.1�v�ł���悤��
- �y⼌��Q�z�@�t�オ��͂P��ڂ��ł�����c
- �y⼌��R�z�@�S�Ă̐E�����g�ő���h����������
- �y⼌��S�z�@�����������100�_�������ɔC����70�_
- �y⼌��T�z�@����́u�T�v�ŖJ�߁C�����́u�U�v�ŖJ�߂�
- �y⼌��U�z�@�J�߂�͗ʂɑ卷�Ȃ��E����͗ʂɑ卷����
- �y⼌��V�z�@�u�쑗�D�c�����v�Ɓu�t���b�O�V�b�v�����v
- �y⼌��W�z�@�u���M�̐c������琬�v�Ɓu��点��琬�v
- �y⼌��X�z�@�Ō�̂P�l�̈琬������܂ł�99�l�̈琬
- �y⼌�10�z�@�l�ވ琬�́u�w���ƕ]���̈�̉��v��
- ��Q�́@�Z�����g�́u���X�̍\���v�����߂�
- �y⼌�11�z�@�Z���͎������q�ώ����镪�g���K�v
- �y⼌�12�z�@�Z���͂�����@���ł��邱��
- �y⼌�13�z�@�Z���̊�͏�ɐE�����猩���Ă���
- �y⼌�14�z�@�Z���ɂ́g���߃[���t�h���K�{
- �y⼌�15�z�@�Z���͑傫�Ȃ��̂����ł��̂�����
- �y⼌�16�z�@�Z���́g����ƍN�h�C��w���Ȃ�
- �y⼌�17�z�@�Z���͒P���̈����d�������Ă͂Ȃ�Ȃ�
- �y⼌�18�z�@�~�X�����炸�C����c���n�߂�
- �y⼌�19�z�@�O�����Ɂu�Áv�ł��邽�߂ɓ��̒��́u���v
- �y⼌�20�z�@�Z���͊���o���̂��d��
- ��R�́@�Z�����g�́u�w�Z�o�c�́v�����߂�
- �y⼌�21�z�@�Z���̎d����99�����}�l�[�W�����g
- �y⼌�22�z�@���j�̓g�b�v�_�E���C��̂̓{�g���A�b�v
- �y⼌�23�z�@�����̓{�g���A�b�v�C�L���̓g�b�v�_�E��
- �y⼌�24�z�@��ɍň���z�肷��
- �y⼌�25�z�@�����̕������ł͂Ȃ��C�����̕�������
- �y⼌�26�z�@�Z�łłȂ��E���{���ŗ͂̂���E��
- �y⼌�27�z�@�G�[�X�i��C�j����Ă�
- �y⼌�28�z�@�u����v���Ƃ邩�u�`���v���Ƃ邩�c
- �y⼌�29�z�@�l���������l���Ȃ�w�Z�������o��
- �y⼌�30�z�@������č������
- ��S�́@�E���́u�ڋ��E�@�ߏ���́v�����߂�
- �y⼌�31�z�@������ܐ�܂Ō����Ă���ӎ���
- �y⼌�32�z�@�d�b����E���́u�w�Z�̊�v
- �y⼌�33�z�@�d�b��������E���́u�w�Z�̊�v
- �y⼌�34�z�@�N���[���ɑΉ�����E���́u�w�Z�̊�v
- �y⼌�35�z�@�Ӎ߂ƃN�b�V�������t�͊�@�Ǘ��ɂȂ�
- �y⼌�36�z�@�s���v���ɑΉ�����E���́u�w�Z�̊�v
- �y⼌�37�z�@99���ł��P��×�Ȃ�v���I�Ȑ��E
- �y⼌�38�z�@��������邽�߂ɂ́C���������܂܂��
- �y⼌�39�z�@�ň��̎��Ԃ�z�N������
- �y⼌�40�z�@�u�X���Ƒ�v�ł͂���܂����c
- ��T�́@���t�́u�d���p�v����Ă�
- �y⼌�41�z�@�d���̑����������̑������Ƃ肩����̑���
- �y⼌�42�z�@�d���ōł��d�v�Ȃ̂̓}�l�W�����g
- �y⼌�43�z�@���W���J���Ē��g������
- �y⼌�44�z�@�d�����ו������C���e�ƌv�����������
- �y⼌�45�z�@�܂��́u����v�Ǝ蒠�ɋL��
- �y⼌�46�z�@���͖{��������
- �y⼌�47�z�@�ɂ���Čv����p���E�C������
- �y⼌�48�z�@�d���ʁ�100�_����遃�~�X�����߂�
- �y⼌�49�z�@������M���邩�C�M���Ȃ����c
- �y⼌�50�z�@�A�E�g�v�b�g���ǎ��ȃC���v�b�g��
- ��U�́@�����ナ�[�_�[�́u�g�D�^�c�́v�����߂�
- �y⼌�51�z�@���[�_�[���]��ƁC���̂��Ƃ��ł���
- �y⼌�52�z�@�w�N��C��l��100�_���w�N����80�_
- �y⼌�53�z�@�g�D�I�Ή��Ƃ͂����Ȃ���̂������L����
- �y⼌�54�z�@�W����������C�C�Q���������Ŏw������
- �y⼌�55�z�@�w������̂͋����C�J�߂�͍̂Z��
- �y⼌�56�z�@�Z���́g�ēh�ł����ł͗����Ȃ�
- �y⼌�57�z�@�c�E�b�E�`�܂łł�������Ƃ��Ă͈ꗬ
- �y⼌�58�z�@������l×20�l�O��20�l×��l�O�̎d��
- �y⼌�59�z�@�Z����⍲���遁�傢�Ȃ��Ď҂ƂȂ邱��
- �y⼌�60�z�@�Z���Ƌ����ŊG�i�y���j��`��
- ���p�E�Q�l����
- ���Ƃ���
�܂�����
�@�`�����玄���ő�ϋ��k�Ȃ̂ł����C2014�N����̒����ɂ킽�鋳��s���i�Ďq�s����ψ�����ǁj�Ζ����o�āC2024�N�t�C����11�N�Ԃ�ɕĎq�s�����w�Z�ɕԂ�炭���Ƃ��ł��܂����B���ꂪ�u���@�v����u�Z���v�ւƑ傫���ς��͂��܂������C�悤�₭�O��ł������w�Z����ւƖ߂邱�Ƃ��ł����킯�ł��B
�@���āC2024�N�R��31���ɁC���̎|�𐔔N�Ԃ��Facebook�ɂĕ����Ƃ���C�S���̑����̐搶������C��ς��肪�������b�Z�[�W���������Ղ��܂����B���̓��e�����邱�ƂȂ���C�u10�N�ԁC���M���R�����g���قƂ�ǂ��Ȃ����Ȃ̂��Ƃ��C�悭���݂Ȃ���o���Ă��Ă����������v�ƁC�������������Ă���ƁC�R�����g���̍ʼn����ɍT���߂ɏ����ꂽ�C���̃��b�Z�[�W�ɖڂ����܂�܂����B
�@�u���h�]���߂łƂ��������܂��B����10�N�ɂȂ�̂ł��ˁB�܂����͓Y�����C�ǂ�����낵�����肢�������܂��I�v
�@���̑���傱���C�����}���o�ŕҏW�҂ł���C�܂���10�N�O�C���̂悤�ȕГc�ɂ̖}�l���t�̐ق����H�����̖ڂ����邱�ƂɂȂ����ő�̌��J�҂���y�쐽�����̐l�ł����B
�@�u�y�삳��C���肪�Ƃ��������܂��B���҂����������܂������C�����11�N�Ԃ�̂��˗��ł����i�j�B�c煘r�ҏW�҂̂��ƂŁC�܂��������Ă����@������Ȃ�]�O�̍K�r�ł���v
�ƁC�����F�߂������ĕԐM���Ă݂͂����̂́C���̙��߁C�w���ɗ�⊾�������̂������܂����B
�@10�N�O�ɏo�ł��ꂽ������C�w�X�y�V�����X�g���`�I�@���w�Z�@�N���X�Â���̊j�ɂȂ�w���ʐM�̋ɈӁx�i2014�j�ɒ[���āC�w�i���j���������ҁx�i2016�j�C�w�X�y�V�����X�g���`�I�@�q�ǂ��̐S�ɕK���͂����t�����̋ɈӁx�i2015�j�𐢂ɑ���o�������Ɣ�ׁC�����́u���@�v�ƌ��݂́u�Z���v�Ƃ�������̈Ⴂ�����邱�ƂȂ���C�����́u���@�v��10�N�Ԃ́u����s���E�v�Ƃ������e��Ȃ�����̈Ⴂ�C����Ɍ���I�ȁu�i���H�́j���ꂩ�痣�ꂽ�N���v�̈Ⴂ�c�ȂǁC�v���I�ɋ������ς���Ă��܂��������C���X����������Ƃ����̂��c�BICT�͂��߁C���i�����̎��ƋZ�p�ɂ��Ď��̂悤�ȁu�Y�����Y�v�����������Č���̃j�[�Y�ɉ�����ׂ����Ȃ��c�B���Ƃ����āC�����10�N�Ԃ̋���s���o���œ����m�����ڂ炩�ɂ���킯�ɂ��Ȃ�Ȃ��c�B
�@���̈���ŁC10�N�Ԃ�̎��̘_���ɑ��Ċ��҂������Ă�������y�쎁�ւ̊��ӂ̎v�����`�ɂ������C����10�N�Ԃœ����m�����C���J�ɑς�����͈͂őS���̐搶���ւ��͂����邱�ƂŁC���ׂƂ��錻�݂̋���E�ɋ͂�����ł��v���������C�c�����l���Ă��邤���ɁC�u�������B�����܂ł��C�Z���Ƃ����g�̏�ɍ���Ȃ��v�E���������������ւ̉��߂Ƃ��āC�����āC�������g�̍���̐����̂��߂ɏ������Ƃ���`�Ƃ��C�����悤�ȉۑ�ӎ������搶���ւ̒�ĂƂ����`�ł���C���̂悤�Ȏ҂��㈲���铹�������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����v���ɍs�������܂����B�K���s�K���C����10�N�Ƃ����Ό��́C�����Ċw�Z����ɂ��������ł͌����Ȃ����E��C�����Ȃ������ł��낤�m����ɂ͏\���Ȏ��Ԃł����B�����C�������U�̎t�Ƌ��C�Ďq�s����ψ���E�Y�ю����璷�ɂ��d�����钆�ŁC�{���̃e�[�}�ł���u�l�ވ琬�v�ɂ��ẮC�U�N�Ԃ̊Ǘ��E�o���i�w���W���P�N�C�w�Z����ے��S�N�C����ψ�����ǎ����P�N�j�̒��œO��I�ɒ@�����܂�C��ϑ����̊w�т܂����B���������o����w�т����ЂƂ����`�ŃA�E�g�v�b�g�ł���̂́C����E�L���ƌ����ǂ���قǑ����͂Ȃ����낤�c�C�Ȃ��������Ƃ������e�ł��`�����Ă������B����Ȏv���Ɍ㉟�������`�ŁC�d�����M���Ƃ錈�ӂ���������ł��B
�@���āC�{���͂U�̏͂ō\�����܂����B�O�q�̂Ƃ���C���̐ق��Ǘ��E�o���œ������Ƃ̒��ŁC����Ƃ����Љ�����S�̍\���E�l�����Ȃǂɂ��āC����E�݂̂Ȃ炸�C�e�E�̒����l���B�̎v�z�E�����J�Ɉ��p���C���əG�z�Ȃ���C�u�l�ވ琬�p�v�i�u⼌��v�j�Ƃ��āC�e��10���ځC���v60���ڒ��Ă��������Ǝv���܂��B
�@�܂��P�͂ɂ����āC�u�l�ނ��琬���邽�߂̐S�̍\���v�Ƃ��āC�l�ވ琬�Ɍ��������[�_�[�̐S�̍\���ɂ��Ċnj����q�ׂ���C�����Q�`�R�͂ɂ����āC�Z�����g�́u���X�̍\���v��u�w�Z�o�c�́v�ɂ��āC�܂��Ɏ������g�ւ̉��߂Ƃ��āC��Ǝv���邱�Ƃ��L�������Ǝv���܂��B���̏�ŁC�S�͈ȍ~�ɂ����āC�u�ڋ��E�@�ߏ���́v�C�u�d���p�v�C�u�g�D�^�c�́v�Ȃǂ��e�[�}�ɁC�Ⴂ���t��i�������܂ށj�����ナ�[�_�[������Ƃ��āC�S�Ă̋��E�����琬�����ł̊����ɂ��Ē�Ă��Ă��������Ǝv���܂��B
�@���͂����̑��ɂ��C�Ⴆ�u���Ɨ́v�ł���Ƃ��C�u���k�w���́v�ł���Ƃ��C�u�Z�����s�\�́v�ł���Ƃ��C�w�Z�̋��E�����g�ɕt����ׂ����e�͑���ɂ킽��܂��B�{���ł���C�����������e�ɌW��l�ވ琬�p�ɂ��Ă�����Ă������̂ł����C�����̓s���ŕʂ̋@��ɏ��邱�ƂƂ��܂��B�ǂ������e�͊肢�܂��B
�@�Ȃ��C�{���ɂ����ẮC�l�ނ��琬����s�҂��C���Ҏ��g�̗���ł���u�Z���v�Ƃ����C�Z���E�ȊO�̎w���I����ɂ���搶���i�����C������C�C�w�N��C�C������C�C�������[�_�[�Ȃǁj�ɓǂ�ł��������Ă�����������e��z�肵�Ă��邱�Ƃ���C�u���[�_�[�v�u�Ǘ��E�v�u��i�v�Ƃ������p������I�Ɉ������ƂƂ��܂��B���������āC�ǎ҂݂̂Ȃ���Ƃ͈قȂ闧��̗p��ł������Ƃ��Ă��C�K�v�ɉ����āC�����g�̗���ɓǂݑւ��Ă���������K���ł��B
�@�c��̐���̑�ʑސE��C�u�u���b�N�v�̈ꌾ�ŋ��E����������Љ�S�̂̕��������钆�C���猻��ɂ�����l�ވ琬�͂��͂�҂����Ȃ��̏ɂ���܂��B����ȍ������炱���C�������́C�P�ɐl�ނ��m�ۂ��邱�Ƃɗ��܂炸�C�M�d�Ȑl�ށi�����j��l�ЂƂ肪�L�тċP���悤�Ɉ�ĂĂ����Ȃ���Ȃ�܂���B�{���́C���̂悤�Ȋϓ_����C�����ׂ肪���Ȑl�ވ琬�̗��Ƃ����ʋ��t�Ƃ��Ď��グ�C����ׂ��l�ވ琬�̊������C�J�e�S���C�Y���Ē��悤�Ƃ������݂Ȃ̂ł��B
�@�{�����C�u����S���̐搶���̂����ɏ����ł������C���{�S���̑����̐搶���C�Ђ��Ă͎q�ǂ������̏Ί�Ɋ�^���邱�Ƃ��ł���Ȃ�C����͖]�O�̊�тł��B
�@�@�@�^�����@����
-
 �����}��
�����}��














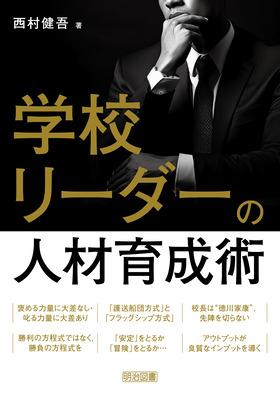
 PDF
PDF

