- はじめに
- 第1章 自己調整方略とは
- 1 自己調整学習の概観
- 2 自己調整方略
- 3 自己調整方略リスト
- 4 第2章から第4章の構成
- 第2章 「見通す」フェーズの自己調整方略
- 1 課題を分解する
- 2 課題の関係を考える
- 3 解決策を考える
- 4 課題を身近なこと,知っていることと結びつける
- 5 課題を解決するとどのようなことがわかるのか,できるようになるのかを考える
- 6 課題を解決したときの自分への褒美を考える
- 7 問いを広げる
- 8 問いを順序立てる
- 9 問いを絞る
- 10 目標を達成するとどのような能力が高まるのかを考える
- 11 目標を達成するために,どのようなことをすればよいかを考える
- 12 学習の最後につくり出せるもの,理解できること,身につけることができることを予想する
- 13 長期課題・目標を基に短期課題・目標と学習の活動を決める
- 14 方法・方略を決める
- 15 時間配分を決める
- 16 学習計画を基に,学習をうまく実行することができるかを考える
- 第3章 「実行する」フェーズの自己調整方略
- 17 学習に適切な道具を選択する
- 18 学習に適切な人数や役割を考える
- 19 情報を収集する
- 20 情報を関連づける
- 21 情報を多面的に見て,吟味する
- 22 情報を構造化し,考えをつくる
- 23 新たな価値を創造する
- 24 創造した価値を発信する
- 25 大切な情報を繰り返し言ったり,書いたりして理解を深める
- 26 学習が課題・目標からずれていないかを確認する
- 27 実行している方法・方略が適切かを確認する
- 28 計画を基に時間配分を確認する
- 29 学習に取り組みやすい物的・人的環境になっているかを確認する
- 30 自分に質問するようにして,学習の進捗を確認したり,内容の理解を深めたりする
- 31 学習に向かう自らの気持ちを確認する
- 32 学習の進捗について確認したことや,学習中に大切だと思ったことを記録する
- 33 学習活動を調節する
- 34 方法・方略を調節する
- 35 計画を基に時間配分を調節する
- 36 学習が進みやすい物的・人的環境に調節する
- 37 学習がうまく進まなかったり,時間が足りなかったりした際に他者に相談する
- 38 困難な課題をやりがいのある挑戦であると考える
- 39 得意なところや簡単なところ,興味深いところを見つけて取り組む
- 40 不快な感情のとき,その原因や理由,意味について考える
- 41 不快なことがあったとき,そのことをどのようにすれば解決できるかを考える
- 42 不快さを感じたら,休憩したり,別のことをしたりする
- 第4章 「振り返る」フェーズの自己調整方略
- 43 取り組んだ学習の成果と課題を考え,自己評価する
- 44 評価結果の原因や理由を考える
- 45 自らの学習結果に納得したうえで,その後の学習に活かせることを考える
- 46 次の学習に活かすことを考える
- 第5章 自己調整方略とレギュレイトフォーム
- 0 自己調整方略を組み込んだレギュレイトフォーム例
- 1 「見通す」フェーズ
- 2 「実行する」フェーズ
- 3 「振り返る」フェーズ
- 4 レギュレイトフォームを活用した小学校の授業実践
- 5 レギュレイトフォームを活用した中学校の授業実践
- 参考文献,参考実践・資料
- おわりに
「はじめに」より
本著のタイトル「自己調整方略」は,「学習者が自ら学習を調整するための学び方」を提案するために,学校教育における課題を解決し,学習者が主体的に学ぶ授業を実現していきたいという思いで名づけた書名です。
教育心理学の言葉に「自己調整学習方略」という言葉がありますが,本書の「自己調整方略」と「自己調整学習方略」は「自己調整方略≒自己調整学習方略」といった関係であると考えています。本書を「自己調整方略」と名づけたのは,これまで教育心理学の研究で明らかにされてきた知見を,できるだけ日本の学校教育になじみのある言葉に置き換え,教育現場に生じている問題の解決に活かしていきたいと考えたからです。学校で,児童生徒主体の学習が実現するためには,先生方の授業改善に対する意識の高まりが非常に重要です。そのためには,授業改善に挑まれる先生方にとって,児童生徒の姿をイメージしやすい言葉や文章にする必要があると考えました。
これらのことから,本書では,教育心理学で明らかにされている「自己調整学習方略」の知見を参考に,教育工学的なアプローチから導き出した,学習者が主体的に学習に取り組むための手法を「自己調整方略」としてまとめていきます。
(中略)
本書では,前著からの流れを引き継いだうえで,学校現場において学習者の主体的な学びを実現するために,児童生徒が身につけてほしい学び方を「自己調整方略」として,一つひとつ解説します。そして,学習者がそれらの方略を活用しながら学び,身につけていくことにつながる新しいレギュレイトフォーム例を提案します。これにより,児童生徒が自己調整学習者へ至るための道筋が明らかになると考えます。
本書で紹介する「自己調整方略」が,学校現場における自己調整学習の実現につながれば幸いです。
2024年7月 /木村 明憲
-
 明治図書
明治図書- 自己調整学習とセットでより効果を発揮します。2025/2/2730代 静岡県小学校教諭
- 具体的な授業の構想を1時間レベルでイメージできて、とてもわかりやすかったです。2024/8/2930代・小学校教員














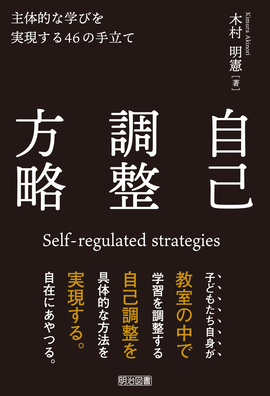
 PDF
PDF

