- はじめに
- 1章 特性に応じた指導のための仕事術
- 優位な特性に対応する
- 認知処理の特性に対応する
- 障害の特性に対応する
- Column 「子どもを観察すること」のテクニック
- 2章 学級担任が困ってしまう
- 「子どもの行動」への仕事術
- 「キレる」への支援の方法
- 「ルール」への支援の方法
- 「切り替え」への支援の方法
- 「話を聞けない」への支援の方法
- 「練習をしない」への支援の方法
- 「集中」への支援の方法
- 「注目」への支援の方法
- 「不安な気持ち」への支援の方法
- 「過敏」への支援の方法
- 「離席」への支援の方法
- 「安全面」への支援の方法
- 「無気力」への支援の方法
- 「発達障害×○○」への支援の方法
- Column なぜ,あの子だけいいの?
- 3章 発達障害のある子どもが過ごしやすい学級経営の仕事術
- 発達障害のある子どもと学級経営
- 発達障害のある子どもと教室の座席
- 発達障害のある子どもと掲示物
- 発達障害のある子どもとトラブル
- 発達障害のある子どもと支援員
- 発達障害のある子どもが複数いる学級
- Column ほめるためのリフレーミング
- 4章 特別な支援が必要な子どもの保護者対応の仕事術
- よりよい面談をするには
- よりよい保護者会をするには
- もしも保護者の要求への対応が難しかったら
- もしも特別支援学級への転学を進めるときは
- Column インクルーシブな学校組織のデザイン
- 5章 通級・特別支援学級との連携の仕事術
- 子どもを通級につなぐときは
- 通級の先生が授業参観に来るときは
- 通級の先生と面談するときは
- 特別支援学級の子どもが授業に参加するときは
- 特別支援学級と行事で交流するときは
- Column 「個別の教育支援計画」をどのように活用するか
- 6章 「個別の指導計画」作成の仕事術
- 「子どもの様子」の欄を書くには
- 「目標」の欄を書くには
- 「手だて」の欄を書くには
- 「評価」の欄を書くには
- Column スタンダードとオプション
- 7章 教科指導における特別な支援の仕事術
- 国語科での特別な支援の方法
- 「漢字のとめ・はねが書けない」子どもへの支援の方法
- 「漢字を文章の中で使えない」子どもへの支援の方法
- 「漢字を書く意欲が低い」子どもへの支援の方法
- 算数科での特別な支援の方法
- 社会科での特別な支援の方法
- 理科での特別な支援の方法
- 体育科での特別な支援の方法
- 音楽科での特別な支援の方法
- 図画工作科での特別な支援の方法
- 家庭科での特別な支援の方法
- 道徳科での特別な支援の方法
- 総合的な学習の時間での特別な支援の方法
- 授業にだんだんついていけなくなっている子どもへの支援の方法
- どの授業にも困難がある子どもへの支援の方法
- おわりに
- 参考文献
はじめに
「困っている子どものために特別な支援をしてあげたい。だけど,とても手が回らない! そんな時間も余力もない!」
そんな悲鳴があちこちの学級担任から聞こえてきます。学級担任の努力不足でしょうか? そんなことはありません。
したいことはある。でも,その時間や余力がない。
それならば,なるべく近道をして最適解にたどりつくための「仕事術」があるとよいのではないでしょうか。
本書は,特別支援教育の視点で学級担任の100の「仕事術」を集めてみました。この「仕事術」が,「困っている子どものために特別な支援をしてあげたい」という学級担任の先生方の思いに応えられたら幸いです。
さて,学級担任にとって,特別支援教育の視点での「仕事術」とは,どのようなものなのでしょうか。
学級担任にとっては,まず学級の「集団」を動かすテクニックが必要です。その上で,日々の授業を回していく教科の学習への理解も欠かせません。
一方,特別支援教育の視点だと,「集団」というよりは,一人ひとりの「個」の子どもたちを考えます。
そう考えると,特別支援教育の視点での学級担任の「仕事術」とは,「集団」に対しての指導を行うにあたって,「個」の子どもに柔軟に対応するテクニックであるということができます。
そのような視点で,本書では,特別支援教育の視点で考える「仕事術」を,ジャンルごとにわかりやすく編集しました。
1章は「特性に応じた指導のための仕事術」です。学級の「集団」の中には,様々な特性のある子どもたちがいます。とはいえ,その多様な子どもたち,すなわち「個」にどのように対応していけばよいのでしょうか。
まずは,比較的よく知られている特性についての知識を得ることです。そして,その特性ごとの指導・支援のポイントをつかむことです。それが「特性に応じた指導のための仕事術」になります。
2章は「学級担任が困ってしまう『子どもの行動』への仕事術」です。通常の学級の「集団」の中ではなかなか対応しきれない子どもの「個」の行動に困ってしまい,本書を手にとった方も多いのではないかと思います。
ここでは「キレてしまう」「切り替えができない」「集中できない」など,教室でよく見られる子どもの行動面について,1つはすぐ問題解決につながるようなトラブルシューティング的な対応,もう1つは問題が大きくならないようにする未然防止のための方法,この2つを考えてみました。
3章は「発達障害のある子どもが過ごしやすい学級経営の仕事術」です。今,どの学級にも発達障害のある子どもがいることが前提となっています。ですので,発達障害のある子どもにとって過ごしやすい「集団」をつくっていくことが必要です。
「教室の座席」や「掲示物」といった「集団」全体に関わることが,「個」の子どもにどのように影響するのか。どのように工夫すれば,発達障害の子どもも過ごしやすい学級になっていくのかということを考えてみます。
4章は「特別な支援が必要な子どもの保護者対応の仕事術」です。保護者対応で多くの時間や労力を必要とすることも多いのではないでしょうか。
保護者対応もある意味で「集団」と「個」を意識する必要があります。特に特別な支援を必要とする子どもの保護者対応は,「個」を考えがちですが,保護者全体の「集団」とのバランスをとることも大切です。
5章は「通級・特別支援学級との連携の仕事術」です。通級指導教室はまさに「個」に特化した学びの場ですが,そこでの学びを学級の「集団」につなげていくためには,学級担任の細やかな仕事術が必要です。
また,校内に特別支援学級がある場合,特別支援学級という「集団」と通常の学級という「集団」の交流には,やはり仕事術が欠かせません。
6章は「『個別の指導計画』作成の仕事術」です。当然,「個別の指導計画」は,作成すること自体が目的ではありません。いかに「個」の子どものために有益な資料にしていくかが問われます。
「個」の子どもの実態が異なるからこそ,「個別の指導計画」の作成にあたって苦労されることも多いでしょう。作成に必要な仕事術を身につければ,よりスムーズに作成することが可能です。
7章は「教科指導における特別な支援の仕事術」です。教科指導において,「集団」に対する指導と「個」に対する指導を両立させるのはなかなか難しいことです。
しかし,教科の特性に応じた特別な支援の方法を考えることによって,そのハードルは下がるかもしれません。本章は,学習指導要領解説に記載された事項をわかりやすく表現し直しました。
このようなバラエティに富んだ仕事術の本ですので,どこからでも,必要な箇所からお読みください。
-
 明治図書
明治図書- 日頃の授業でのヒントになるものがたくさんありました。もっとたくさんのイラストや、写真などがあるとより分かりやすいです。2024/6/130代・小学校教員
- 今から読んで仕事にいかしたい2024/3/130代・中学校教員
- 特別支援教育の視点はすべての教師に必要です。具体的な子どもの様子を思い浮かべて読むとより本書はより活用できると思います。2023/9/24たかし














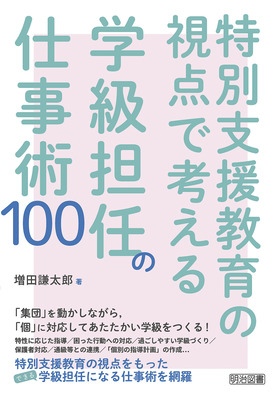
 PDF
PDF

