- はじめに
- 第1章 なぜ,学級経営にウェルビーイングなのか
- 1 ウェルビーイングとは
- 1 ウェルビーイングの経緯
- 2 ウェルビーイングが必要な背景
- 3 ウェルビーイングの構成要素
- 4 日本的幸福と北米的幸福
- 2 学級経営とウェルビーイングとの関係
- 1 学級経営の内容
- 2 21世紀型学級経営を見据える
- 3 OECD ラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030から読み解く
- 4 ファシリテーションの視点から考える
- 3 今後待たれる,具体的な実践と研究
- 第2章 ウェルビーイングを高める他者への関心と WE 視点
- 1 ウェルビーイングが高まった子ども達に見られた2つの共通点
- 1 どこをどう見て,どう解釈するか
- 2 日記に現れる他者の存在
- 3 WE 視点の獲得
- 2 ウェルビーイングが高まるきっかけを生みだす実践例
- 1 学級開きから継続して対等感を強調する
- 2 全員で掲示物を組み立てる「学級目標完成式」
- 3 みんなの言葉で学級の物語を創る「思い出総選挙」
- 4 学級への参画を促す「お楽しみ会運営」と「司会グループ」
- 5 ウェルビーイングと他者の姿
- 第3章 幸せな人生のヒントは,共同体感覚の育成にあった
- 1 「なんちゃってウェルビーイング」からの脱却を!
- 1 ダイバーシティ化するウェルビーイング
- 2 ウェルビーイングと共同体感覚は仲良し関係?
- 3 共同体感覚を高めるためにできる“4つのアプローチ”
- 2 共同体感覚向上を目指した学習デザイン
- 1 共同体感覚を育むソーシャルスキルトレーニング(SST)
- 2 共同体感覚を育む協同学習
- 3 SST と協同学習でバッテリーを組む
- 3 「共同体感覚」は「幸せ」に向かうための「やる気スイッチ」
- 第4章 集団の意思疎通システムとしてのクラス会議
- クラス会議を学級に用いるとなぜウェルビーイングが高まるのか
- 1 クラス会議が持つ場の力
- 1 整理整頓ができない先生
- 2 妹がちょっかいをかけてくる女の子
- 2 集団の意思疎通システムとしてのクラス会議
- 1 個に徹底して寄り添う
- 2 安心・安全な場
- 3 クラスとしての意思決定
- 4 職員会議は機能していますか?
- 3 ウェルビーイングとクラス会議
- 1 ハッピーサンキューナイス
- 2 輪になって座る
- 3 トーキングスティック(全員参加の話合い)
- 4 議題の提案と解決
- 4 投票率の低下を考える
- 1 投票率向上にクラス会議が寄与する
- 2 沖縄県でのクラス会議
- 3 学力ではない大切なもの
- 5 共同体感覚をクラス会議で育む
- 1 共同体感覚が高い教室
- 2 クラス会議の研修で
- 3 先生達の共同体感覚を高める
- 4 共同体感覚が高まった状態で
- 5 クラス会議でなぜ共同体感覚が育まれるのか
- 6 深夜ラジオとクラス会議
- 6 クラス会議で夢を叶える
- 1 夢を叶える仕組み
- 2 クラス会議で夢を叶える
- 3 悩みもするする解決する
- 4 目の前の姿から
- 5 真の意味でのウェルビーイング
- 第5章 ウェルビーイングとポジティブ行動支援
- 1 ウェルビーイングとポジティブ行動支援の関係
- 1 ポジティブ行動支援とは
- 2 ウェルビーイングとポジティブ行動支援の関係
- 3 ポジティブ行動支援のねらいは「行動レパートリーの拡大」と「環境調整」
- 4 ポジティブ行動支援の基本的な考え方
- 2 ポジティブ行動支援で集団のウェルビーイングを高める
- 1 ポジティブ行動支援による集団支援・学級経営
- 2 子ども達とともに,生活・学習の行動のABCを考える
- 3 「行動」と「結果事象」への支援がウェルビーイングには重要
- 4 様々な教育実践と融合することでよりウェルビーイングが高まる
- 3 子どもの主体的な行動調整を実現する「自分研究」
- 1 学級全員が自分の行動について考える「自分研究」
- 2 子どもに応じた支援を実現する
- 第6章 ウェルビーイングと地域づくり
- 1 学級づくりのその先は?!
- 2 ウェルビーングを構成する5つの要素
- 3 キャリア ウェルビーイングと学校づくり
- 1 自己決定度・学校づくり
- 2 対等な選択肢としての学校づくりの実践
- 4 コミュニティ ウェルビーイングと地域づくり
- 1 地域のつながり感の現状
- 2 社会・他者への関心と当事者意識
- 3 つながり感育成のための地域づくりの実践
- 5 キャリア ウェルビーイング,コミュニティ ウェルビーイングと学級経営の共通点
- 第7章 ウェルビーイングを高める教室の構造
- 1 あなたの「大きな石」
- 2 世界の中の日本の幸福度
- 1 世界における日本の幸福度
- 2 日本の幸福度の内訳
- 3 格差に不満を募らせ,それを解消する術を持たない国,日本
- 3 経済発展は幸福度を高めるのか?
- 4 子どもの幸福度を高めるための「大きな石」
- 第8章 対談
- 教室のウェルビーイングを守り育てる教師と学級の在り方
- 1 自己選択や自己決定を拡張するファシリテーション
- 2 ウェルビーイングの高い子どもの共通点
- 3 ウェルビーイングを高めるエビデンスベースドの要因と手だて
- 4 誰かに話を聞いてもらえる場や環境の保障
- 5 先生達のウェルビーイング
- 6 自分の行動の価値を見出す習慣「人生にご褒美を!」
- 7 頑張っても報われない時代を生きる
- 8 自己決定していない先生達?
- 9 選択肢の一つとしての学校
- 10 平等だけど公平ではない学校
- 11 選択と強制の狭間で
- 12 そこに危機感はあるのか?
- おわりに
「はじめに」より
皆さん,こんにちは。この書籍は,学校教育におけるウェルビーイングに焦点を当てています。本書の読者の多くが教員の方々だと思われますが,皆さんは,子ども達の成長と幸福をサポートするため日々奮闘なさっていることでしょう。きっと皆さんの教室では,今日も子ども達の歓声が上がり,たくさんの笑顔が見られていることでしょう。しかしその一方で,日本全体を見渡せば,子ども達の問題行動や不適応などは増え続けています(令和4年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では,小中学校の不登校児童生徒数が,10年連続で増加し,30万人に迫り,小中高等学校におけるいじめの認知件数,暴力行為の発生件数,自殺も過去最多)。
このような状況で,中央教育審議会は,令和5年3月8日の第134回総会において「次期教育振興基本計画について(答申)」を取りまとめ,中心となる2つのコンセプトの1つとして「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を掲げました。この計画は,簡単に言うと日本の教育政策の基本方針を示すものです。わが国の教育の中軸に,ウェルビーイングの向上が据えられたということでしょう。
ウェルビーイングとは,同答申によれば「身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい,短期的な幸福のみならず,生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むもの」であり,また「個人のみならず,個人を取り巻く場や地域,社会が持続的に良い状態であることを含む包括的な概念」であると説明されています。
ウェルビーイングについては様々な議論がなされていますが,ウェルビーイング学会から出されている「ウェルビーイングレポート日本版2022」から,その意味するところを大まかに整理しておきたいと思います。
ウェルビーイングという言葉は,1940年代に世界保健機関(WHO)の健康の定義の中で使われたのが最初だと言われています。WHO 協会では「健康とは,病気でないとか,弱っていないということではなく,肉体的にも,精神的にも,そして社会的にも,すべてが満たされた状態にあること(日本 WHO 協会訳)」としています。
似ている言葉に,ハピネス(happiness)や幸せがあります。ハピネスは,幸せよりも狭い意味で使われており,感情としての幸せ,楽しさ,嬉しさを表す言葉です。また,幸せという言葉は,「辛いことも大変なこともあったが幸せな人生であった」などと言うときに使われるように,感情的に良好な状態のときだけでなく,包括的な意味で使用されることがあります。
それに対して,ウェルビーイングは,感情面,つまり心理面だけでなく,身体面,健康面を含み,また個人的に良好な状態のみをいうのではなく,自分を取り巻く社会的状況を含み,さらに今ここの良好な状態のみを指すのではなく,それが持続することも包含する意味が広いものであることがわかります。つまり,ハピネスよりも広い意味を持つのが幸せ,そしてさらに広い意味を持つのがウェルビーイングとなります。
今なぜ,ウェルビーイングなのでしょうか。
答申には,先行きの見えない時代の到来を受けて,社会のウェルビーイングの実現が,経済先進諸国の共通の「目的地」であることが述べられています。裏を返せばそれは,経済的な豊かさの追求は,ウェルビーイングの実現には十分に寄与しなかったという現実のもとに,改めて人の幸福を考えようという反省が公文書で述べられたということではないでしょうか。こうした世界的な流れもありますが,学校現場に目をやれば,国際調査では日本の子ども達の幸福度の低さが指摘され,国内調査では,「学校離れ現象」が加速しているような状況が明らかとなっています。
私達日本人の市民生活には,宗教や政治,ジェンダーの話に象徴されるように「忌避されがちな話題」があると感じています。そうしたタブーの一つに「幸せ」に関する話があるように思います。「幸せとは?」といった話をすると,「幸せを他人に定義されたくない」などといった感情的な反応が起こったり「人の幸せは人それぞれ」といったあいまいな結末に落ち着かせようとしたりする場面を数多く見てきました。学校は,教育機関という性格からさらにその傾向が強まる場になっているのではないでしょうか。
しかし,学校においては,「学力向上=子どもの成功」というステレオタイプなモデルを相対化したり棚上げしたりして「幸せな学校とは?幸せな教室とは?そもそも幸せとは?」(ここでは厳密な意味ではなく幅広い意味で)といったことについてもっと子ども達とともに議論してきてもよかったのではないかと思います。個人としての幸福は人それぞれであっても,みんなが幸せな状態とはどのような状態なのか,共通解を探索するような場がもっとあっていいように思います。
「幸福とは?」という問い対する答えを自分の頭で考え,自分の言葉で語ることを避けてきたツケが,学校周辺のみならず日本全体を取り巻く閉塞感の要因の一つになっているのではないでしょうか。子ども達が自分と社会の幸せを描くことができる学校教育の再構築のときが来ているのだと思います。そのためには,子どもに関わる大人の考え方,教室環境や教育プロセスを見直し,幸せを実現する在り方や方法を模索する必要があるでしょう。
本書では,以下の2点を探求します。
1 ウェルビーイングをどう捉えるか
ウェルビーイングの概念はこれからまだまだ議論が必要な概念です。したがって,まず執筆者がそれぞれの捉えのもとにウェルビーイングについて語ります。読者の皆さんなりのウェルビーイングに対する捉えを描いてみていただければと思います。
2 ウェルビーイングを高める実践とは何か
各章の執筆者がそれぞれのウェルビーイングの捉えにもとづき,それを向上させるための具体的なヒントを述べます。皆さんの実践の何らかのヒントになれば幸いです。
ここに示すものは正解ではありません。各章での主張に共通点もあれば,異なる点もあることでしょう。最終章は,執筆者7名による対談となっていて,それぞれの章で言い足りなかったこと,また,他の主張に対して質疑応答をしています。1章から7章までお読みになった上で,最終章では,議論に参加するようにして読んでいただければと思います。そして自分なりのウェルビーイングの捉えを言葉にし,目の前の子ども達と一緒にウェルビーイングな環境の在り方や創り方を構想していただければと思います。
子ども達が沈んだ顔をしている教室で,教師のウェルビーイングの実現が成り立つはずはありません。その逆も真なりで,子ども達のウェルビーイングのみが高くて教師のそれが低いという状態も「それは違う」と言わざるを得ないでしょう。ウェルビーイングは,周囲との関係性を含めた良好な状態です。子ども達のウェルビーイングを探究することは,教師のそれを考えることにつながるはずです。
本書が,読者の皆さんと子ども達のウェルビーイングを実現する一助となれば幸いです。
2024年7月 執筆者代表 /赤坂 真二














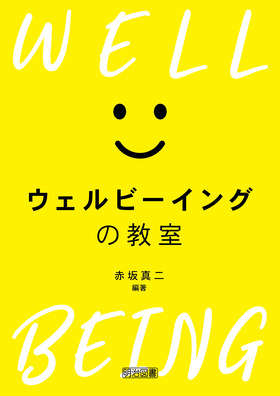
 PDF
PDF


学校や教室におけるウェルビーイングを考えるきっかけになる一冊であった。
本誌を参考にしながら、今、目の前にいる子どもたち及び同僚と一緒に、ウェルビーイングな教室(職場)環境を作り上げていきたいと思います。
また、著者の先生方の個性がでていていいです!