- はじめに
- 第1章 「子ども主体」の算数授業を阻むもの
- 1 教師主導の算数授業の実態
- 2 子どもたちが自ら動き出さないのはなぜか
- 3 算数授業の“当たり前”は本当に当たり前なのか
- 第2章 無理なく取り組める単元内自由進度学習のデザイン
- 1 算数授業と単元内自由進度学習
- 2 家庭学習の取り組み方を見直す
- 3 単元内自由進度学習を進めていくための思考スキル
- 4 思考ツールを活用する
- 5 思考スキルを働かせる算数授業のつくり方
- 6 単元計画のあり方を見直す
- 7 「教えるところ」と「考えさせるところ」
- 第3章 単元内自由進度学習の実践例
- 単元計画のつくり方
- 1年の実践例「形あそびをしよう」
- 2年の実践例「三角や四角の形を調べよう」
- 3年の実践例「長い長さをはかって表そう」
- 4年の実践例「箱の形の特徴を調べよう」
- 5年の実践例「図形の角を調べよう」
- 6年の実践例「およその面積や体積を求めよう」
はじめに
「どのような授業を,子どもたちと一緒につくっていきたいですか?」
この質問に対して,皆さんならどのように答えますか。
「子どもたちが自分で課題を見つけて,それを解決していくような授業をつくってみたい」
「子どもたちが『今日の授業,楽しかった!』と思えるような授業をつくってみたい」
「子どもたちが友だちと関わる中で,課題を解決していくような授業をつくってみたい」
多くの先生たちが,このような「子ども主体」の授業づくりを目指していきたいと考えているのではないでしょうか。
2024年12月25日に,学校の教育内容などを定めた学習指導要領の改訂に向けた検討が,中央教育審議会(中教審)に諮問されました。主な審議事項として,以下の4つがあげられています。
①質の高い,深い学びを実現し,分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方
②多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方
③各教科等やその目標・内容の在り方
④教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合うことを含む,学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策
「②多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方」の中には,「興味・関心や能力・特性に応じて子供が学びを自己調整し,教材や方法を選択できる指導計画や学習環境デザインの重要性,デジタル学習基盤を前提とした新たな時代にふさわしい学びや教師の指導性」の在り方があげられています。
中央教育審議会が提唱する「令和の日本型学校教育」の中で,個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実が掲げられましたが,ここでも,子ども自身が興味・関心や能力・特性に応じて自己調整しながら学んでいく授業づくりが求められています。
以上のことからも,これからの授業づくりにおいては,教師主導のみの授業から,子ども主体の授業に授業観をアップデートしていく必要があることがわかります。
子ども主体の授業づくりの重要性については,多くの先生が実感していることと思います。しかし,実際にやってみようとしても,どのようにすればよいのか迷ったり,悩んだりしてしまうのではないでしょうか。
実際,子ども主体の授業の大切さについて先生たちと話をしていると,こんな声が聞こえてきます。
「『子ども主体』にすると,授業がグダグダになってしまうんじゃないかな…」
「全部子ども任せにしてしまうと,学習内容がしっかり身につくか心配だな…」
「一人ひとりの子どもたちの学習進度に応じた教材を準備しないといけないのかな。そうすると,準備に時間がかかり過ぎてしまうな…」
「子どもたちが自由に発言すると,本当に引き出したいことは出てくるのかな…」
「学年が上がるほど子ども同士の関わりは固定的になってくるから,相談するときも,子どもたちにすべて任せてしまうと,遊んでしまうのではないかな…」
「子どもたちが自分のやりたいことをやっていると,一人ひとりが何をしているのかを把握することが難しそうだな…」
このように,新しい取組に対していろいろな不安や疑問がわいてくるのは当然だと思います。
私自身も,はじめて「自由進度学習」の研究を行っている学校を参観したときに,「今まで自分がやってきた授業とは全然違うな」と感じました。しかし,そこで授業をしている先生と話をさせていただいたとき,「それって,今まで私が授業づくりをしていくときに大切にしてきたことと一緒なんじゃないか」と気づかされました。それは,授業の中での子どもたちの思いや気づきを大切にし,それらを基に子どもたちが考える時間を取り,子どもたち自身が解決しやすい方法を選択していくことを大切にする授業づくりでした。
この気づきから,「自由進度学習」を,まったく新しい授業スタイルではなく,今行っている授業スタイルを少し違う視点から捉え直し,教師主体で進めていた部分に,子ども自身が自ら考え,選択する「子どもたちに任せる活動」を取り入れたのが,本書で提唱する「自由進度学習」のスタイルです。
今目の前にいる子どもたちの10年後の姿を想像してみてください。想像した子どもたちが「様々な課題に出合ったときに,自ら考え,自ら動く人」になるように,小学校の段階でどのような授業を行っていくことが大切なのかを一緒に考えていきましょう。そして,子どもたちの目が輝く授業づくりを目指して,様々なことに挑戦していきましょう。
2025年3月 /今井 啓介
-
 明治図書
明治図書














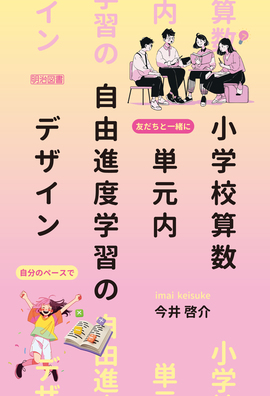
 PDF
PDF

