- プロローグ なぜ修業が必要なのか
- Chapter1 授業力を養うための成功法則
- 1 授業に関する修業の道程
- 1 修業の出発点
- 2 力量の差を最も感じたもの
- 3 良い授業には共通性がある
- 4 客観的に自分の授業を見ることができるようになる
- 5 授業の質を高めるサイクルの始まり
- 2 どの子にとっても学びやすい授業を考える
- 1 発達障害への対応を考える
- 2 「できる・楽しい授業」は最低限保障する
- 3 子どもの反応で授業の良し悪しを判定する
- 3 授業における具体的な修業法
- 1 新卒時代の授業をどう行ったか
- 2 授業への熱中具合を反省する
- 3 討論の状態を意図的につくる
- 4 どんな発問を行っていたか
- 5 どんな授業展開の工夫を行っていたか
- 6 授業展開と教材、学習環境を工夫する
- 4 授業をより良くするために気を付けていたこと
- 1 追試で気を付けていたこと
- 2 授業を「創造・開発」する力を付けるために
- 5 水泳が苦手な子を泳がせるための授業開発
- 1 ある種のみじめさ
- 2 水泳指導の技量向上への挑戦
- 3 水泳指導の手順
- 4 泳げない子を泳げるようにするための指導のシステム
- 5 水泳指導システムの効果
- Chapter2 学級経営力を養うための成功法則
- 1 集団づくりの力を養う
- 1 集団づくりのゴールへのイメージ
- 2 ゴールから逆算した中間のゴールを考える
- 3 学級集団の状態を記録する
- 4 わずか一ミリの成長をとらえる目を養うために
- 2 個別の成長に注目し記録する
- 1 個別の子どもの様子を記録する
- 2 次々と生じるトラブル
- 3 長い目で子どもの進歩をとらえる
- 3 学級経営上の子ども対応で気を付けていたこと
- 1 一人ひとりの子どもにスポットライトを当てる
- 2 一人ひとりのゴールを共有し、ゴールを達成できるよう導く
- 4 学級マネジメントの力を磨く
- 1 ある不思議なこと
- 2 学級の状態の違い
- 3 担任としての戦略が全てを決める
- 5 その他の学級経営の工夫
- 6 教師のリーダーシップを養うために
- Chapter3 子ども対応力を養うための成功法則
- 1 子どもが見えるとはどういうことか
- 1 わざと鉛筆を落とした子
- 2 「子どもを見る」とはどういうことか
- 3 教室にいる様々な子の様子が見えているか
- 4 まずは子どもを見ることから指導は始まる
- 5 子どもが見えるための条件
- 6 子どもの実態をつかむための「ものさし」
- 7 指導の成否は子どもが見えるかに左右される
- 2 子どもを正確につかむための修業
- 1 一人ひとりの成長を記録する
- 2 個別の目標シート
- 3 少人数のクラスでの経験
- 4 一人ひとりに注目するようになって変わったこと
- 3 発達障害をもつ子への対応
- 1 我流での対応は通用しない
- 2 「子どもの事実」から対応方法を考える
- 3 自分の授業を分析する
- Chapter4 学校全体の教育を進めるための力を養う成功法則
- 1 学校全体の教育を進めるための力とは
- 1 学校全体の教育を進める力がなぜ必要か
- 2 学校全体の教育を進める力とは
- 3 若い頃はとにかく仕事を引き受ける
- 4 仕事は一極集中する
- 5 抵抗は生じるもの
- 2 研究の力をつける
- 1 研究の力をつける取り組み
- 2 研究依頼を断らない
- 3 他の学級でも授業を行う
- 4 学校を研究の場にするメリット
- 5 研究結果をまとめることの大切さ
- 3 地域・社会との連携
- Chapter5 教師の姿勢を磨くための成功法則
- 1 一年目から守りたい教師の心得
- 1 百年前から教師の心得は現場にあった
- 2 一年目から意識してきた心得
- 2 先人の実践を否定することも教育の進歩には必要である
- 1 先人から学ぶ際の態度
- 2 修正の連続の上に科学の進歩は訪れる
- 3 自分の実践を見直すことも必要だ
- 3 教育研究会を立ち上げる
- 1 自前の研究会を組織する
- 2 研究会の活動記
- 4 力のある教師の背中から学ぶ
- 1 尊敬できる教師との出会い
- 2 力のある教師から学ぶ
- 3 師に教えてもらう場をつくる
- 4 恩師の影響
- 主な引用・参考文献
プロローグ なぜ修業が必要なのか
修業とは
本書は、教師力を向上させるために、新卒からどのような修業を自らに課してきたのかを紹介するものである。
学制以来百五十年間で、最も教育界に影響を与えた一人である、芦田惠之助の言葉に次のものがある。
教育の眞諦は自己を育てるにある。
行ずるといふことは、自己を育てる最捷徑である。
(芦田惠之助国語教育全集刊行会編〔一九八七〕『芦田惠之助国語教育全集24』明治図書、p.504)
「眞諦」とは、「究極の真理」を意味する言葉である。
「行ずる」とは、「修行する」の意味である。
「最捷徑」とは、「最も早道」という意味である。
「自ら成長する教師だけが、教壇に立てる」そのことを、端的に示した言葉である。
教師は、他人を教育する立場にある。その教師にとって、最も大切な姿勢は、「自らを教育する姿勢」であることを伝えている言葉である。
つまり、自分を鍛え、磨き続ける姿勢をもたなくてはならないのだ。
芦田惠之助は、「修行」という言葉を使用した。
本書では、「教師の仕事を身に付ける努力の継続が、自己を鍛え磨くことになる」という意味を込め、「修業」の方を使用する。
「修業」と「修行」の意味は異なる。
修業は「学問や芸術を習い身に付けること」を意味する。
修行は、「学問や芸術に励み、磨くこと」を意味する。
授業の方法や、学級経営の方法を修めるのは、「修業」である。
「修業」というと、「楽しいことを禁じ、苦行を続ける」イメージが浮かぶかもしれない。
しかし、本書で言う修業は、決して苦行ではない。それどころか、楽しみながらできることである。少なくとも、私や、私の周りの教師は、本書で紹介した修業を楽しく実行している。
修業によって、子どもの笑顔が増える。成長の事実が生まれる。
すると、教師の仕事に充実を感じるようになる。そうなると修業にますます熱が入るようになる。このような良いサイクルができあがるのである。
(後略)
-
 明治図書
明治図書














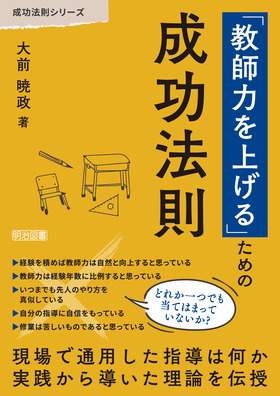
 PDF
PDF

