- 第1章 本当は大切だけど、誰も教えてくれない[学級開きと子ども対応]3のこと
- 1 「子どもの実態調査」には、大きな落とし穴がある
- 2 「未来の成長した姿」を簡単に描ける子ばかりではない
- 3 成否を分けるのは、「少し先の成長した姿」をイメージさせられるかどうか
- 第2章 本当は大切だけど、誰も教えてくれない[子ども理解]5のこと
- 4 ただ見ているだけでは、子どもの行動の意味は理解できない
- 5 学級で見せる姿だけが、子どものすべてではない
- 6 子どもの心を把握することは、子ども自身にさえ難しい
- 7 教師も子どもも、無意識のうちに「成長の限界」を決めつけている
- 8 教師の「よかれと思って」が子どものゴールをつぶしている
- 第3章 本当は大切だけど、誰も教えてくれない[子どもへの対応方法]6のこと
- 9 叱り方を変えても、繰り返される問題行動は解決しない
- 10 問題行動の根本的解決のカギは、ゴール側から考えることにある
- 11 短所に注目すると、短所がより強化される
- 12 「北風」の対応で子どもは変わらない
- 13 一番怖いのは、無意識に繰り返される「やってはならない対応」
- 14 問題行動は個性が原因ではなく環境が原因
- 第4章 本当は大切だけど、誰も教えてくれない[集団づくりと個別指導]4のこと
- 15 「集団の質」が一人ひとりに与える影響は、想像以上に大きい
- 16 「集団のもつ雰囲気」が、子どもの行動を大きく左右する
- 17 「足を引っ張る」行為の背景には、集団の強固な心理が働いている
- 18 「互いを下げ合う集団」を変える第一歩は、集団のゴールを新しくすること
- 第5章 本当は大切だけど、誰も教えてくれない[子どもの自立を促す対応]5のこと
- 19 手厚い指導や支援が、子どもの自立を阻害する
- 20 集団づくり、授業づくりには、「順序性・系統性」がある
- 21 自分で決めたゴールや方法なら、子どもは自分から歩みを進める
- 22 「軌道修正する力」を養うカギは、教師が示す評価規準
- 23 「教える」と「任せる」には中間の段階がある
- 第6章 本当は大切だけど、誰も教えてくれない[子ども対応の方向性]6のこと
- 24 問題行動への対応に注力しても、問題行動は減らない
- 25 「信頼」のない状況での指導で、「信用」すら失ってしまう
- 26 教師は無意識のうちに、自身の価値観や信念で子どもを裁いている
- 27 一枚岩を求めることが、学級の「心理的安全性」を脅かす
- 28 「未来」を重視し過ぎると、「今」の充実が損なわれる
- 29 「マイナス→0」と「0→プラス」では、対応が大きく異なる
- 第7章 本当は大切だけど、誰も教えてくれない[教師の姿勢]6のこと
- 30 短期的な成果が、ゴールへの最短距離とは限らない
- 31 行動変容を望むなら、子どもの思いや願いの確認は不可欠
- 32 教室の子どもの姿は、教師の行動を映し出す「鏡」
- 33 「知る」→「行動が変わる」までには多くの段階がある
- 34 教師のもつ「哲学」は、無自覚のうちに子ども対応に反映される
- 35 自己評価を高める言葉をかけ続けると、変化は急に訪れる
- 引用・参考文献一覧
はじめに
「子ども対応」には、よい対応と悪い対応があります。
よい対応とは何か。それを紹介するのが、本書の役割です。
教師が情熱や愛情をもって接しているからといって、それが必ずしもよい対応とは限りません。
例えば、ある学校で、荒れた子に対して情熱と愛情をもって対応している教師がいました。
親身に寄り添い、毎日熱心に指導しました。
その結果、ますます荒れがひどくなってしまいました。生活面でも学習面でも、問題行動が増加してしまったのです。
このような例は、少なくありません。「教育への情熱」や「子どもへの愛情」がいかに大きくとも、間違った対応をするとよくない結果を生み出してしまうのです。
「子ども対応」には、理論と方法があります。ところが、それを学ぶ機会は多くありません。
授業や学級経営を学ぶ研修は多くあります。しかし、「子ども対応」に特化した研修は、少ないのが現状です。
そのため、各教師は自分の経験を頼りに子どもに対応せざるを得なくなっています。
教師としての経験、自分がこれまでに受けてきた指導の経験。それら自分の経験から正しいと思える価値観や信念に沿って対応しているのです。
知らず知らずのうちに、過去に自分が受けてきた指導をそのままトレースしていることも少なくありません。自分が厳しく叱られてきたから、教員になった今、子どもたちも厳しく叱っている、といった具合です。
ここでの問題点は、それが「無意識」であることです。無意識に、自分の経験に沿った対応になってしまっているのです。そのため、自分が正しいと信じている対応方法が万が一間違っていたら、今後も間違った対応をし続けることになってしまいます。
私たち教師は、「子ども対応」の理論と方法を、学ぶ必要があります。
また、自分がもつ価値観、信念をも振り返る必要があります。
本書には様々な人物が登場します。私の経験が主なのですが、他の人物も登場します。失敗例が多いこともあり、事例をぼかすため、三人称の人物を登場させ、エピソードを紹介しています。
本書では、「子ども対応」に関して、教師が知っておくべき内容を数多く紹介しました。
本書が読者諸兄の「子ども対応」の参考になれば、これに勝る喜びはありません。
2025年1月 /大前 暁政
-
 明治図書
明治図書- 自分が向き合わないといけないことがよくわかりました。的確に書かれていることで、自分の課題もはっきりとわかりました。2025/3/2430代 小学校教員
- 時々、子どもとの対応で「あれ!」と考える時があります。基本に立ち返る時に読むと良い本だと感じました。2025/3/2060代・中学校教諭














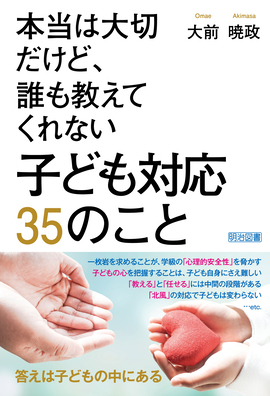
 PDF
PDF

